早期発見は難しいが化学療法の成否が予後改善のカギとなる 化学療法の進歩で効果を上げる卵巣がんの治療
化学療法30年の軌跡
このような治療によって予後改善がみられるようになってきたのも、化学療法のめざましい進歩があるからにほかならない。
1970年代に白金製剤(プラチナ製剤)に分類されるブリプラチン(もしくはランダ、一般名シスプラチン)が開発され、日本で発売されたのが80年。それからほぼ30年の歴史があるが、この薬を使うようになって死亡率の著しい減少がみられた。
また、タキソール(一般名パクリタキセル)に代表されるタキサン系抗がん剤は、単剤ではそれほどではないが、ブリプラチンと併用すると効果が大きいことがわかった。
GOG(Gynecologic Oncology Group)という米国の婦人科がんの臨床試験グループが行った「GOG111」という研究では、タキソール+ブリプラチンの併用療法(TP療法)が、それまでの標準治療だったエンドキサン(一般名シクロホスファミド)+ブリプラチンの併用療法(CP療法)より有意に優れているとの結果が示された。
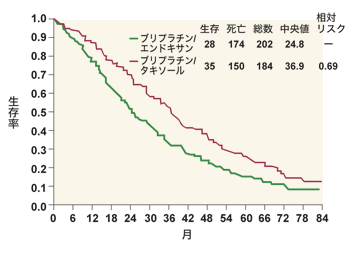
ブリプラチンのあとに開発されたのがパラプラチン(一般名カルボプラチン)だ。ブリプラチンは高い抗腫瘍効果を持つものの副作用も強く、最も深刻なのは腎毒性による腎不全などの腎臓機能の障害がある。ほかにも悪心・嘔吐、神経毒性なども強い。こうした副作用がブリプラチンに比べて軽いのがパラプラチン。普通、副作用が軽いとその分、効果も弱くなるものだが、抗腫瘍効果はブリプラチンと変わらないことがわかった。
「GOG158」という研究で、TP療法とタキソール+パラプラチン(TC療法)の比較試験が行われ、予後は同等に良好で、副作用はTC療法のほうが軽減されることがわかり、現在の標準治療薬はタキソールとパラプラチンの併用となっている。
| ブリプラチン | パラプラチン | |
|---|---|---|
| 消化器毒性 | +++ | + |
| 腎毒性 | +++ | ± |
| 神経毒性 | +++ | - |
| 血液毒性 | + | ++ |
| 血小板減少 | + | +++ |
毎週投与など投与法の工夫
このように、新しい抗がん剤の開発や併用療法によって、卵巣がん全体の5年生存率が90年代半ばまでには50パーセントに達するまでになったが、その後は頭打ちの状態となった。そこで、さらに効果を増強させるにはどうしたらいいかが模索されている。
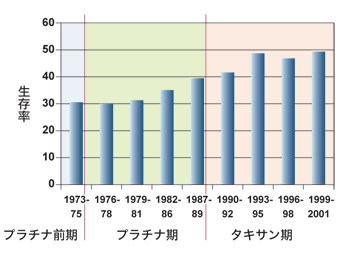
↓
エンドキサン+パラプラチン
↓
タキソール+ブリプラチン
↓
タキソール+パラプラチン
たとえば、TC療法にドキシル(一般名ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤)、ハイカムチン(一般名トポテカン)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)など、第3の薬剤を加えた3剤併用療法はどうかと大規模な臨床試験(GOG182)が行われた。
しかし、「生存率に有意差はなく、予後を改善するものではなかった」という結論だった。しかも、3剤にしたほうが副作用は増強した。
では、投与法の工夫で予後が改善されないだろうか。たとえば、ウィークリー投与、つまり毎週投与である。
日本で実施された臨床試験(JGOG3016)では、標準治療であるタキソール+パラプラチンを3週間ごとに投与する療法と、タキソールを毎週投与(パラプラチンの投与法は標準治療と同じで、タキソールの1回の投与量を減らす)する療法とを比較した。
結果は、毎週投与の療法は3週間ごとの標準治療と比較して、腫瘍の縮小率はあまり変わらなかったが、無増悪生存期間が改善され、約10カ月もの延長を示した。
この結果を受けて、今後、毎週投与が標準治療になる可能性もあるという。
腹腔内投与についても研究が進んでいる。タキソール+ブリプラチンの静脈内投与と、タキソール静脈内投与にブリプラチンおよびタキソール腹腔内投与を併用した場合の効果を比較した臨床試験(GOG172)では、後者のほうが無増悪生存期間と全生存期間の延長が有意に得られ、全生存期間は約16カ月の延長が認められた。
その一方で、腹腔内投与では消化器症状、神経毒性、好中球減少、感染などの副作用が多く認められることが問題になっていて、副作用を軽減する取り組みが課題となっており、今後ブリプラチンの代わりにパラプラチンが腹腔内化学療法用薬剤として有用であるかどうかを検証する臨床試験が世界中で開始される。
単剤でも効果のあるアバスチン
新しい薬の開発も進んでいる。注目されるのが分子標的薬であり、中でも卵巣がんに有効とされるのがアバスチン(一般名ベバシズマブ)だ。
VEGF(血管内皮増殖因子)というタンパク質を狙い撃ちして、がん細胞の血管新生を阻害して、がんの増殖を抑える薬である。
藤原さんは次のように話す。
「現在、国内では大腸がんで保険適用が認められ、海外では乳がん、肺がんについても認められていますが、必ずほかの抗がん剤との併用で承認されています。なぜかといえば単剤ではあまり効果が出ていないためです。ところが、卵巣がんには単剤で効いているとのデータがあります」
分子標的薬はほかにもあるが、単剤で卵巣がん治療に用いた場合の奏効率(有効率)をみると、ハーセプチン(一般名トラスツズマブ)は9.7パーセント、グリベック(一般名イマチニブ)は1.8パーセント、イレッサ(一般名ゲフィチニブ)では3.7パーセントに対して、アバスチンだけは18パーセントと高い奏効率を示している。
単剤でこれだけの効果なのだから、併用したらどうだろうかと、現在、初回治療でTC療法とアバスチンを併用すると予後が改善できるかどうかの比較試験(GOG218)が行われていて、日本も参加している。ヨーロッパでも同様の試験が行われており、結果が出るのは3年先とのことだが、注目される。
ドキシルへの期待
ところでがんでは、再発したり、長年化学療法を続けていることにより、がんが薬剤に対する耐性を持つことが問題になる。
そこで、薬剤耐性を持ったがんや、TC療法が効きにくいがんに有効な薬としてドキシルが期待されている。
以前から卵巣がんの適応拡大の早期承認が求められていたドキシルは、2009年4月、ようやく正式な承認がおりた。ドキシルは、すでに世界80カ国以上で使われていて、副作用も少ないといわれ、期待が高いのだ。
藤原さんは次のように語っている。
「たしかに、ドキシルは従来の薬と作用機序(仕組み)が違うし、副作用の出方も異なるので期待が持てますが、決して夢の薬ではありません。海外ではほかにも、分子標的薬をはじめ有望な薬が次々と検討されています。日本でも、開発の流れに遅れないよう、臨床試験など態勢の整備が今後ますます重要になってくると思います」
同じカテゴリーの最新記事
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線
- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待


