渡辺亨チームが医療サポートする:卵巣がん編
3c期の卵巣がんは、手術に加えて抗がん剤治療が不可欠
山中康弘さんのお話
*1 卵巣がんの組織分類
卵巣がんと一般的に言われているがんは、病理組織学的な分類でいうと腺がんというタイプです。腺がんの中にも、様々なタイプがあり、病気の進行具合である進行期のように予後と関係しています。たとえば明細胞腺がんというタイプの腺がんは、卵巣がんで最も多いタイプとされている漿液性腺がんなどと比較すると予後が悪いとされています。
| 漿液性腺がん | 卵巣がんの70~80%を占める最も多いタイプ |
| 粘液性腺がん | 腫瘍マーカーCA125が上昇しないタイプ |
| 類内膜腺がん | 子宮内膜から発生するがん(子宮体がん)に類似したタイプ |
| 明細胞腺がん | 抗がん剤への感受性が低いとされているタイプ |
*2 卵巣がんの進行期
卵巣がんと診断された場合、がんがどの程度転移しているかの検査が行われます。
その結果、がんの拡がりの程度に応じて治療方法が変わってきます。
このがんの拡がりの程度を進行期(病期とも)といいます。
腹膜播種のような転移を術前に画像診断で見つけることは難しいので、正確な進行期はあくまでも手術(腹腔鏡も含めて)による所見によって決められます。手術中、直接転移の有無を見ることができるだけでなく、手術後摘出物を検査した結果によって、進行期が決定されます。下の表ように分類されています。
| 1期 | がんが片側、あるいは両側の卵巣にだけにとどまっている状態 | |
| 1a期 | 腫瘍は片方の卵巣内部に限局され、卵巣をおおっている 卵巣被膜は無傷で腹水中にがん細胞はない | |
| 1b期 | 腫瘍は両方の卵巣の内部に限局され、 卵巣被膜は無傷で腹水中にがん細胞はない | |
| 1c期 | 腫瘍が片方または両方の卵巣の表面にもみられて 被膜には裂け目ができ、あるいは腹水が溜まって、 そのなかにがん細胞がみられる | |
| 2期 | 2a期 | がんが卵巣の周囲、つまり卵管、子宮、直腸、 膀胱などの腹膜に転移している状態 |
| 2b期 | 腫瘍は子宮または卵管、あるいはその両方にみられる。 その他の骨盤内の組織が侵される 2aあるいは2bのがんが存在すると同時に、 腫瘍細胞が片方または両方の卵巣の表面に現われて 被膜が裂け、あるいは腹水がたまって、 そのなかにがん細胞がみられる | |
| 3期 | がんが卵巣の周囲��骨盤内)の腹膜だけでなく 上腹部にも転移しているか、あるいは後腹膜 リンパ節に転移している状態 | |
| 3a期 | 腹膜表面に顕微鏡的な播種(腫瘍の転移)がある | |
| 3b期 | 腹膜表面が侵され、直径2cm以下の腫瘍の転移がみられる | |
| 3c期 | 直径2cm以上の腫瘍の転移があるか、 所属リンパ節にも腫瘍が広がっている | |
| 4期 | がんが腹腔外に転移しているか、 あるいは肝臓(実質)に転移している状態 |
*3 卵巣がんの生命予後
進行卵巣がんの生存期間の中央値は2年くらいです。生存期間の中央値というのは、その集団の中で、寿命の短い人から寿命の長い人まで順番に並べて、ちょうど半分にあたる人が生存している期間のことをいいます。つまり、生存期間の中央値の意味するところは、半分の人がその時点までに死亡し、半分の人がそれ以上生きる、ということになります。
患者さんの予後については、進行期、手術の内容、患者さんの全身状態や病理組織分類、抗がん剤治療への反応などに左右されます。
医師は患者さんから「自分はあとどのくらいか?」と聞かれることが少なくありませんが、実際にはそれはわかりません。患者さん1人ひとりの経過は同じようで違っています。ただ私は「身辺整理などをする必要があるのか?」とか、「仕事は退職したほうがいいのか?」というように具体的に聞かれる患者さんなどには、なるべく具体的に回答するようにしています。
国立がん研究センター中央病院の卵巣がんの進行期別患者数と治療成績は下表のように示されています。
(国立がん研究センター中央病院)
| 病期 | 患者数 | 5年生存率 | 10年生存率 |
|---|---|---|---|
| 1期 | 72 | 91% | 83% |
| 2期 | 23 | 72% | 66% |
| 3期 | 163 | 31% | 24% |
| 4期 | 65 | 12% | 9% |
(1980年から1997年までの症例の2000年4月までの治療結果)
*4 TJ療法
卵巣がんの標準治療とされているのが、TJ(パクリタクセル+カルボプラチン)療法です。パクリタキセルは開発時の名前であり、商品名になったタキソールという名前の頭文字と、カルボプラチンの開発時の名前の1つであるJM-8という名前の頭文字を取って名付けられています。
以前は、CP (シクロホスファミド+シスプラチン)療法とかCJ (シクロホスファミド+カルボプラチン)療法と呼ばれる抗がん剤治療が標準とされていましたが、北米でCP療法とタキソール+シスプラチン療法の有効性を比較する大規模な臨床試験が行われた結果、*無増悪生存期間、*生存期間についてタキソール+シスプラチン療法のほうが上回る結果となり、タキソールを含んだ治療のほうが有効であることが示されました。さらに、タキソールとシスプラチンを組み合わせるTP療法とタキソールとカルボプラチンを組み合わせるTJ療法を比較する臨床試験が行われ、その結果、両者は有効性に関して同等ということが示されました。
シスプラチンはカルボプラチンと比べ、吐き気や嘔吐、腎機能障害や聴神経障害などの副作用が多く、また治療に際して腎機能障害を予防するために大量の点滴を要することから、プラチナ系の抗がん剤としてシスプラチンに代わってカルボプラチンが好ましいと考えられるため、TJ療法が卵巣がん治療の第1選択とされることになりました。
TJ療法という2剤併用化学療法に、もう1種類の抗がん剤を加えた治療なども検討されていますが、現在のところTJ療法の成績を超える治療法は見つかっていません。今のところTJ療法は3週間隔で6コース行う方法が標準的とされています。
*無増悪生存期間=どちらかの治療を行うことが決定されてから病気が悪化するまでの期間
*生存期間=どちらの治療を行うことが決定されてから死亡までの期間
| タキソール | 175~180mg/㎡静注 | (3時間投与) |
| カルボプラチン | AUC=5~6静注 | (1~2時間投与) |
3~4週間隔で3~6コース
*5 DJ療法
TJ療法の副作用の1つに、手足のしびれなどの末梢神経障害があります。末梢神経障害は、タキソールの副作用の1つで、蓄積性があり治療を重ねるに従い、神経障害がひどくなる傾向があることに加え、治療を終了した後も回復しない、あるいは神経障害が残ってしまう場合があり、治療を行う上で大きな問題の1つとなっています。タキソールは、タキサン系の抗がん剤に分類されていますが、タキサン系の別の抗がん剤であるタキソテールとカルボプラチンを併用するDJ療法も卵巣がんに効果が示されています。
英国を中心としたヨーロッパでTJ療法とDJ療法を比較検討する臨床試験が行われ、両者の有効性はほぼ同等であり、副作用の種類と程度に違いがあるという結果となっています。末梢神経障害はDJ療法が軽度ですが、全身倦怠感とか吐き気などの症状はやや多く、骨髄抑制はDJ療法でより高度に出現するという結果でした。DJ療法では浮腫(むくみ)が蓄積毒性として多いこと、DJ療法で多くなる骨髄抑制、感染などの生命に危険のある副作用がやや多いこともあり、TJ療法、DJ療法のどちらも一長一短というところです。
TJ療法は、標準治療として臨床試験による有効性と安全性に関するデータが多く存在し、安全性について他の化学療法と比較して大きな問題となることがほとんどないことから、私は、卵巣がんの患者さんにはTJ療法をお勧めしています。
しかし、タキソールは製剤にアルコールを含んでいるため、お酒を舐めただけでも気分が悪くなってしまうような「アルコール不耐」と呼ばれる患者さんはTJ療法が難しい場合があります。また、レジ打ちやキーボード入力、楽器演奏や手芸などを専門的に行っているような方には末梢神経障害が残ることが大きな問題となることがあります。私は、その場合にはDJ療法を提示して、患者さんと相談の上で治療を決めています。
現在、私が勤務している病院ではTJ療法も外来診療で実施していますが、TJ療法は点滴する時間が約6時間かかりますので、外来で実施が困難で、以前勤務していた病院では1泊2日で実施していました。その点、DJ療法は点滴する時間が約3時間とTJ療法より短いため、入院したくない患者さんや遠方にお住まいの患者さんには点滴時間が短いという実施上の関係からDJ療法をオプションとして提示したりしています。ただし、繰り返しになりますが、基本的には臨床試験のデータが多い治療のほうがより確実と考えて、TJ療法ができる方にはTJ療法をお勧めしています。
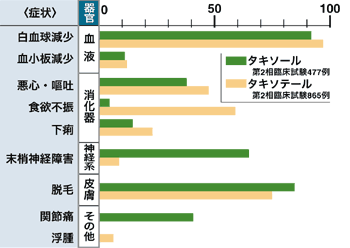
*6 腹腔内投与
卵巣がんに対する抗がん剤の腹腔内投与はこれまでいろいろな臨床試験が行われ、有効性及び安全性が示されています。臨床試験では抗がん剤の腹腔内投与の有効性について、静注投与(点滴)と比べて同じかやや優れるという結果が報告されています。ただし、これらの臨床試験では、比較する相手の治療が現在の治療と異なっていました。
また、腹腔内投与を行うための腹腔内リザーバーの閉塞や感染といったトラブルがあったり、腹腔内の癒着によりそこから薬を投与しても薬が腹腔内全体に広がらないような状態になってしまったりして投与できないケースもあり、結局腹腔内投与が行えない患者さんもいます。予定された治療が行えない患者さんの数が多かったりしたため、臨床試験の結果の解釈が難しく、現時点では実際に患者さんに行ったほうがいいのか、専門家の中でも意見が分かれている状態となっています。また、腹腔内投与する薬剤とその量、スケジュールについて最適な方法が不明なこともあり、海外では更なる臨床試験が実施・計画されています。
抗がん剤の腹腔内投与自体はそれほど目新しい治療というわけではありませんし、手術時に腹腔内リザーバーという器具を挿入し、そこから抗がん剤を投与するという方法であり、難易度が高いわけではありません。今のところ通常の点滴静注投与と比べて有効性について「上回る」、または「変わらない」という結果はありますが、「劣る」という結果はほとんどないため、将来的に有望な治療戦略の1つとなるかもしれません。
ただし、この話にある4期の患者さんで、しかも手術前に点滴静注による抗がん剤治療が行われた患者さんに腹腔内投与を行うことについてはデータがないので、根拠がない治療と言えなくもありません。
同じカテゴリーの最新記事
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線
- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待


