ASCO2006トピックス 進行卵巣がんの主要な薬剤は依然タキソール+パラプラチン
第3の薬を加えた最大規模の試験
「いずれにしろ、現在の標準治療はタキソール+パラプラチンであり、これよりもよい結果を出している試験はありません。唯一例外なのは腹腔内療法で、これはパラプラチンではなくシスプラチンと評価していますが、いずれにしろ現在のグローバルスタンダードはタキソール+パラプラチンです。そこで、今後さらに治療成績を向上させるにはどうしたらいいかというと、1つのアプローチは、新たな薬剤を追加するということです。私たちが使っている薬剤は自然から得られた薬剤ですが、これらの薬剤はそれぞれ細胞の標的が異なり、作用機序が異なっています。そして、薬剤耐性のパターンも、それぞれの薬剤によって異なります。2つの薬を併用すれば相互作用が起こり、その結果として毒性が増えることもあります。すると、タキソールとパラプラチンに、別の第3の抗がん剤を追加すれば、さらによい治療成績が得られるかもしれないし、毒性を相殺することも可能になるかもしれない、というので実施したのが『GOG182』という大規模な第3相試験です。国際的な試験であり、私が責任者となりました」
試験に用いられた薬はタキソール、パラプラチン、ハイカムチン(一般名トポテカン)、ジェムザール(一般名ゲムシタビン)、ドキシル(ドキソルビシンのリポソーム封入体)。それぞれに働きに違いがあり、ゲムシタビン、ドキソルビシンはDNAの合成を阻害する働きをするし、パラプラチンはがん細胞内のDNA鎖と結合してDNA合成及びがん細胞の分裂を阻害するものと考えられている。
それぞれを組み合わせたときの併用効果を調べようと5つの治療群が用意され、8コースの投与がどの群でも義務づけられた。治療群の内訳は(1)スタンダードのパラプラチン+タキソール群、(2)この2剤にプラスしてゲムシタビンを加えた群、(3)2剤にドキシルを加えた群(ドキシルは1コースおきに投与)、(3)最初はパラプラチンとトポテカンを投与し、後半4コースはパラプラチンとタキソールに変えた群、(4)最初���パラプラチンとゲムシタビンで、後半4コースはパラプラチンとタキソールに変えた群の5群。
「対象患者は、年に1000例を目指していましたが、それを上回って年1200例となり、最終的には4312例となりました。進行卵巣がんの臨床試験では最大規模のものになりました。80パーセントはアメリカ人で、あとはオーストラリア、ニュージーランド、イタリア、イギリスその他で、かなり幅広い参加が得られました」
生存率の有意差はなしの結論
注目すべき試験の結果だが、開始から約3年目の中間解析では、無進行生存率は中央値が15~16カ月とほとんど重なっていて、ハザード比も1前後でほとんどかわらないという結果だった。
全生存も中央値39~40・2カ月でほとんど変わらず、ハザード比もやはり1前後で有意差は認められず、各群治療法によるプラスマイナスはないという結果だった。
血液毒性の影響はどうかというと、安全性・忍容性が高いことがわかった。ただ、高用量を使うこともあって、ゲムシタビンでは好中球減少や血小板の減少、ドキシルでも好中球減少などがあらわれたが、発熱・感染症はそれほど多くなかった。非血液毒性では、神経毒性は(1)群よりも(4)(5)群のほうが発現頻度が低下していた。
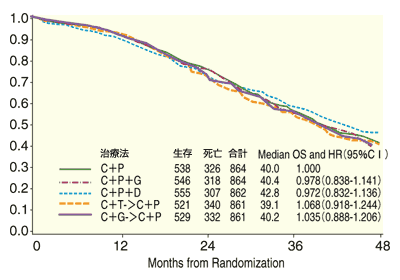
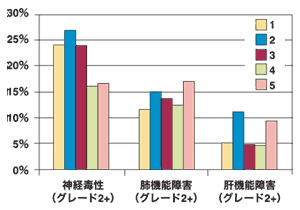
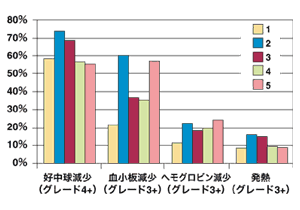
ほかにもさまざまな解析・検討が行われたが、今回の試験の結論として、ブックマンさんは語る。
「3剤目を追加することで、毒性はむしろ悪化していました。これは当初から予想されていたことであり、管理可能です。しかし、3剤目を加えても、無進行生存率、あるいは全生存でも、決して予後を改善するものではなかったというのが結論です。本治療法が導入されて10年以上たっているけれど、タキソール+パラプラチンが相変わらず進行卵巣がんにおいては主要な治療剤となっており、今後、別の新しい抗がん剤が開発された際も、この2つの薬の組み合わせが評価に大きな影響を与えると考えられます」
ブックマンさんによると、今年のASCOでは維持療法についても活発な論議が行われたという。標準化学療法を行って、その後に新たな化学療法を行うというもので、今年のASCOでの発表によると、タキソールを用いた試験の結果では、無進行生存率でみると、12カ月の治療を行っている患者のほうが、3カ月の治療よりもよりよい結果を示している。ただし、本試験では予定症例数の半分で無進行生存率に大きな差が出たため途中中止になってしまったためその時点での登録症例は3カ月群でも12カ月のタキソールを投与するよう勧告が出たため、全生存でみると3カ月群(12カ月投与の症例も含まれている)と12カ月群の差を検出することはできなかった。
「さらなる試験を行って、維持療法がどれだけ重要なのかを評価しなければならない」と語るブックマンさんによれば、GOGでも、タキソールと別の薬剤とを比較する試験を行っているところという。
「現在のところ」と前置きしながら、今年のASCOでの結論について、ブックマンさんは次のように語っている。
「何千名も参加していただいた多くの臨床試験がありますが、スタンダード・オブ・ケアということでは、いまだタキソール+パラプラチンです。しかし、グローバルな共同研究が進んで、新しい薬剤も登場してきており、今後、より有望な治療法があらわれるかもしれません。プラパラチンはとても優秀ですが、非プラチナ系抗がん剤の治療法も開発していくべきでしょう。われわれとしても研究を進め、将来、報告ができるようなよい結果を出したいと取り組んでいるところです」
同じカテゴリーの最新記事
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線
- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待


