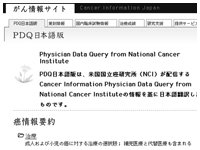進行別 がん標準治療 早期発見の難しい卵巣がん治療は、抗がん剤がカギを握る
再発した場合も抗がん剤を併用したほうがいい?
また、今年のアメリカ臨床腫瘍学会で新しい知見が発表されました。これまで卵巣がんが再発した場合、標準的な治療法はありませんでした。
「抗がん剤を単独で投与するほうがいいのか併用がいいのか、よくわからないままに、ただ毒性の面で単独のほうがいいのではないかと抗がん剤の単独投与が行われていたのです」と藤原さんは語っています。
ところが、今年6月のアメリカ臨床腫瘍学会でイギリスとイタリア・ドイツのグループから、「タキソールを併用してパラプラチンを使ったほうが生存率が高い」という研究結果が発表されたのです。ただし、初回の化学療法でパラプラチンとタキソールの併用化学療法が効いていることが条件です。
このように、卵巣がんの治療法は早期がんから進行がん、再発がんまで、かなり治療の標準化が進み、その効果も明らかにされつつあります。
しかし、逆にそこから新たな課題も見えてきました。藤原さんは、「治療成績を向上させるためには、分子標的治療薬も含めて、新しい抗がん剤の開発や遺伝子治療の進歩が必要です」と語っています。現在、肺がん治療に使われている分子標的治療薬イレッサのような、卵巣がんの特異的抗原CA125をターゲットとしたモノクローナル抗体などは、これから検討されていくそうです。
さらに「手術の面では、大きな手術をしなくても抗がん剤を投与しておけば大丈夫なのか、など適正な手術の術式を明らかにしていくこと、またそのタイミングを明らかにしていくことが必要です」と語っています。
卵巣がんの抗がん剤治療の変遷
藤原さんによると、昔はブリプラチン(もしくはランダ、一般名シスプラチン)とエンドキサン(一般名シクロホスファミド)という抗がん剤の組み合わせが中心だったといいます。 「しかし、96年にパラプラチンとタキソールとの併用のほうが5年生存率が10パーセントほど高いことがわかり、こちらが標準治療となったのです。ところが、その後、10年生存率でみるとどちらの組み合わせでも成績は同じことがわかったのです」
つまり、治療から5年後の時点では、タキソール併用の人のほうが生存者が多かったのですが、実際には治っていない人が多かったということなのです。そのため、長期でみれば、死亡する人は変わらなかったという結果だったのです。
ただ、ブリプラチンは日本でも80���代から使われだした薬で、当初は大きな卵巣がんも治ると脚光を浴びました。もっとも、実際には3年ぐらいで再発することが多かったそうです。一方で、ブリプラチンは吐き気や腎毒性が強く、新しい薬の開発が求められていました。そこから、出てきた抗がん剤のひとつがパラプラチンです。パラプラチンはブリプラチンに比べて副作用が軽いのが大きな利点です。
「おそらく、現在のタキソールとパラプラチンの併用でも、長期にわたって予後を検討するとブリプラチンの場合と同じ結果になるでしょう。しかし、副作用が軽いという点で標準的に使われているのです。そういう意味では、臨床試験でより効果が高いと評価される治療法の開発が求められます」と藤原さんは語っています。
卵巣がんのタイプと抗がん剤
卵巣がんは、厳密にいえば非常に種類が多いがんです。もっとも多いのは、漿液性のがんで、卵巣がんの半分以上を占めます。このタイプは、卵巣がんの中ではわりあい進行が早いとされていますが、抗がん剤が効きやすいがんです。この他、類内膜がん、粘液性のがん、明細胞がんなどがあります。タイプによってがんとしての性質は異なり、抗がん剤の効き方も違います。
中でも、明細胞がんは欧米人に比べて日本人に多く、抗がん剤が効きにくいがんです。
藤原さんによると、現在の卵巣がんの治療はこうしたがんのタイプによって分類できるほど細分化されてなく、全ての卵巣がんに対して同じ治療が行われるそうです。しかし、「明細胞がんの場合は、あまり抗がん剤の効きがよくないので、これをどうするかも今後の課題のひとつ」と語っています。
PDQを調べよう
http://cancerinfo.tri-kobe.org/database/pdq/index.html
PDQとは、米国国立がん研究所(NCI)が発信している大規模ながん情報のホームページ。Cancer Information Physician Data Queryの略称。アメリカが国の威信をかけて開発した高度ながん専門情報データベースで、世界中から最新の臨床試験結果を集めて作成され、高い信頼性を得ている。その日本語版のホームページも、今年5月、京都大学探索医療センター探索医療検証部の福島雅典教授が中心となって作られ、治療、スクリーニング(検診)と診断、予防、遺伝子学、支持療法等の信頼される情報が無料で公開されている(「がん情報サイト」)。
同じカテゴリーの最新記事
- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~
- 2つのPARP阻害薬の力で大きく進化! 卵巣がん治療最前線
- 卵巣がん化学療法に増える選択肢 適応拡大のリムパーザと遺伝子検査なしで使える新薬ゼジューラ
- 進行・再発卵巣がんに選択肢が増える 初回治療から分子標的薬リムパーザが使える!
- 無作為化比較試験(JCOG0602)結果がASCO2018で報告 進行卵巣がんにおける化学療法先行治療の非劣性認められず
- 子宮頸がんはアバスチンを加えた3薬剤、子宮体がんではダヴィンチ、卵巣がんには新薬リムパーザが
- 待望の新薬リムパーザ、日本でも承認・販売! 新薬登場で再発卵巣がんに長期生存の希望が見えてきた
- 根治性、安全性、低侵襲性実現のために様々な術式を開発、施行 婦人科がん手術の現状
- 婦人科がんの難治性腹水に対する積極的症状緩和医療 腹水を抜き、必要な成分だけ戻す「CART」に期待