ただし、効果は限定される。そして治療は新しい個別化治療へ 転移性膵がんにも希望の光か、膵肝同時動注療法という新手の登場
効く場合と効かない場合と
(奏効率・生存期間・生存率)
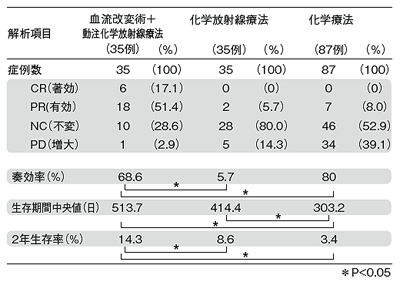
そこで、平山さんは、この動注化学放射線療法と、一般的に行われている化学放射線療法、全身化学療法(ジェムザール単剤)とを比較検討し、これらの治療がどういう場合に効いているのか、2つの因子に着目して調べました。2つの因子とは、肝転移と後腹膜(膵臓の背中側で腹部後方の膜)への浸潤です。後腹膜への浸潤があるとがん性腹膜炎が起こりやすくなります。
ちょっと複雑になりますが、まず、2つのがんの進行の種類(後腹膜浸潤と肝転移)で分けて考え、後腹膜への浸潤がある、疑いがある、ない場合の3つに分けます。また肝転移がある場合とない場合に分け、それぞれの3つの治療法の効果(奏効率と生存率)を比較して調べたのです。期間は2003年から2007年までの約4年半。治療法の内訳は動注化学放射線療法35人、化学放射線療法35人、全身化学療法87人。
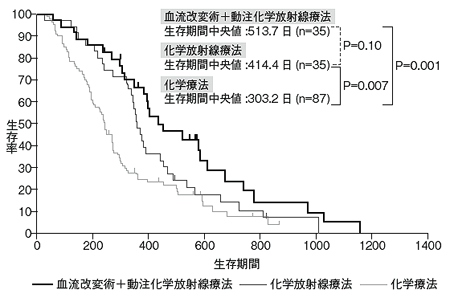
その結果、動注化学放射線療法は原発と肝転移の両方で高い効果があり、とくに肝転移では非常に高い効果が得られ、生存率も優れていました。しかし、後腹膜への浸潤がある場合は、動注療法はあまり効果がなく、化学放射線療法 のほうが高い効果があること、さらに後腹膜への浸潤が疑われるような中間の場合は、動注療法と化学放射線療法とは同程度の効果があることがわかったのです。
奏効率で示すと、動注化学放射線療法では69パーセント、化学放射線療法では6パーセント、全身化学療法では8パーセントで、動注化学放射線療法がダントツです。生存期間(中央値)では、動注化学放射線療法では514日、化学放射線療法では414日、全身化学療法では303日と、やはり動注化学放射線療法が優れていました。
「動注療法の効果が非常に高かったのです。しかし、動注療法では後腹膜まで達したがんには抗がん剤が届かないよ うで、これが後腹膜���の浸潤で動注療法が効かない原因です。その代わり、後腹膜に対しては放射線が効果があり、浸潤を防いでいることがわかりました。意外でした」
膵がんも個別化治療へ
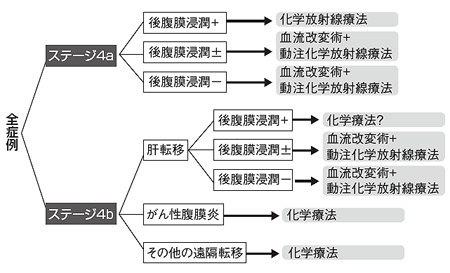
この驚くべき事実が明らかになったのは2005年のことです。それまで動注療法に期待をかけてあらゆる手術不能症例に対して推進してきた平山さんは、これ以降は、進行膵がんの治療選択の必要性についてこう提唱しています。
「こうした事実が明らかになった以上、膵がんの場合、患者さんの条件、すなわちがんの進行度や浸潤・転移の度合いによって、適切なより効果の期待できる治療法を個別で選んで治療に臨んだほうがいいでしょう」
患者さん個々の性格に応じて治療法を変えて行う「個別化治療」は、すでに乳がんや肺がんでは進んでいますが、この方法もその1つといえるかもしれません。
ただし、先の3つの治療法のうち、動注化学放射線療法はまだ標準治療ではありません。診療ガイドラインによれば、4a期でも切除可能なら手術、切除不能なら化学放射線療法か化学療法、4b期では化学療法かサポーティブケアが推奨されていて、この中に動注療法はまだ入っていないのです。
しかし、前記のように、動注化学放射線療法が化学放射線療法や化学療法よりも一段と優れた効果があるとすれば、治療選択に際して一考の余地がありそうです。ただし、この治療を行っている医療機関は限られています。病院選びには注意しましょう。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


