膵臓がん、これだけは知っておきたい基礎知識 手術だけでなく化学療法の進歩にも期待
食生活の欧米化に伴い年々増えている
膵臓は、消化液を分泌する横長の臓器で、その中央を主膵管が通っている。作られた膵液は、細い膵管を通って主膵管に合流し、最終的には胆管と一緒になって、十二指腸につながっている。
膵臓は、十二指腸に近いほうから、膵頭部、膵体部、膵尾部と呼ばれていて、それぞれの部位にできたがんを、膵頭部がん、膵体部がん、膵尾部がんと呼ぶこともある。
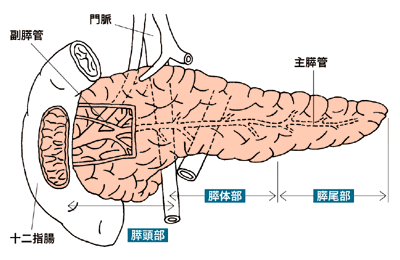
胆道がんのように、できる部位によってがんの性質が異なるということはないが、膵頭部にできたがんと、膵体部や膵尾部にできたがんでは、切除手術の術式は大きく異なっている。
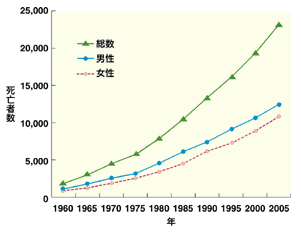
[膵がんのリスクファクター(現在までの報告)]
| 嗜好品 | 喫煙 飲酒 コーヒー |
| 食生活 | 肉類 高カロリー食 高脂肪食 砂糖 |
| 既往歴 | 糖尿病 慢性膵炎 遺伝性膵炎 膵石症 胃切除後 胆摘後 歯周病 ヘリコバクターピロリ感染 |
| 肥満(BMI↑) | |
| 職業(化学物質の被曝) | |
| 放射線 | |
| 家族歴 | 膵がん 遺伝性膵がん症候群 |
膵臓がんも、胆道がんと同じように、年々増えているがんの1つだ。
「各種のがんの罹患率の変化をグラフにすると、膵臓がんと大腸がんは、傾きがだいたい一緒になります。患者数は違うのですが、増加率がだいたい同じということ。大腸がんは食生活の欧米化や運動不足が関係しているのではないかと言われていますが、膵臓がんでもだいたい同じような疫学データが出ています。膵臓がんのリスクファクターとしてあげられているのは、高カロリー食、肥満、���尿病、喫煙などです」
胆道がんのリスクファクターとも、内容はほとんど重なっている。ただ、どのような人に多いのかがわかっても、早期発見のための有効な検査方法はないのが現状だ。
発見されたときには進行していることが多い。
膵臓がんは、早期に発見するのが難しい代表的ながんである。発見されたときには、すでに周囲に浸潤していたり転移していたりすることがほとんどだ。
「膵臓がんがステージ3、ステージ4で発見されることが多いのは、体の奥にある臓器で異変を発見しにくいこともありますが、膵臓がん自体の問題でもあります。通常、がんは大きくなると転移が起きやすくなりますが、膵臓がんは、かなり早い時期から遠隔転移を起こしてしまうのです」
そのため、発見されたときには、すでに進行がんというケースが多いのだ。さらに、膵臓がんには、周囲の組織に浸潤しやすいという困った性質がある。
「腫瘍が膨張するように発育するがんは、手術で切除しやすいですね。これを膨張性発育といいます。膵臓がんは、浸潤性発育といって、あちこちに手足を伸ばすように広がっていきます。こういった発育をするがんは、境界が不明瞭なので、手術で切除するのに苦労します。切除したつもりでも、思わぬところに手足を伸ばしていて、取り残すことになりかねないのです」
つまり、膵臓がんは、手術可能な早期の段階で発見するのが難しいし、たとえ切除手術ができたとしても、根治手術をしそこなうケースが少なくないのだ。
膵臓がんの手術は難しい手術の代表格
膵臓がんも胆道がんと同様、根治的治療となると切除手術しかない。切除手術は難易度が高く、専門性を要求されるので、膵臓がん手術の症例数の多い施設で受けることが望ましい。
「合併症の起きやすい難易度の高い手術では、症例数によって術後成績に大きな差が出ることが確かめられています。膵臓がんの切除手術も、経験による差が出やすい代表的な手術だといえます」
手術を受けるのであれば、どこで受けるのかを慎重に検討したほうがよいだろう。
ただ、手術が可能なケースは、残念ながらさほど多くはない。発見された時点で、手術はできないと診断されることのほうが多いのだ。手術できない膵がんには、局所進行しているケースと、遠隔転移しているケースがあり、それぞれ標準治療は異なっている。
局所進行している場合、つまり明らかな転移が見つからない場合には、化学療法が標準治療となっている。ジェムザール(一般名 塩酸ゲムシタビン)およびTS-1による治療と、場合により放射線療法も同時に進めることもある。
転移がある膵臓がんの標準治療は、ジェムザールによる化学療法だ。ジェムザールは、それ以前に使われていた5-FUに比べ、生存期間を延ばすだけでなく、痛みなどの症状を緩和する効果も認められている。
このジェムザールおよびTS-1に関しては、手術後の補助療法での効果を調べる大規模な臨床試験が進められている。治療が困難ながんだけに、診断や治療に関する新しい研究に期待したい。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


