『膵癌診療ガイドライン』のポイントをわかりやすく読み解く 最難関のがん。化学療法の進歩で大きく変わった
手術数の多い施設が治療成績も優れている
| 病院 | 場所 | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都中央区 | 74 |
| 2 | 名古屋大学病院 | 名古屋市昭和区 | 66 |
| 3 | 東海大学病院 | 神奈川県伊勢原市 | 65 |
| 4 | 東京女子医科大学病院 | 東京都新宿区 | 58 |
| 5 | 京都大学病院 | 京都市左京区 | 58 |
| 6 | 帝京大学病院 | 東京都板橋区 | 54 |
| 7 | 大阪府立成人病センター | 大阪市東成区 | 53 |
| 8 | 和歌山県立医科大学病院 | 和歌山市 | 49 |
| 9 | 県立静岡がんセンター | 静岡県長泉町 | 48 |
| 10 | 東北大学病院 | 仙台市青葉区 | 48 |
| 11 | (国)大阪医療センター | 大阪市中央区 | 47 |
| 12 | 北海道大学病院 | 札幌市北区 | 44 |
| 13 | 癌研有明病院 | 東京都江東区 | 41 |
| 14 | 熊本大学病院 | 熊本市 | 40 |
| 15 | 岡山大学病院 | 岡山市 | 39 |
| 16 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島市 | 38 |
| 17 | 九州大学病院 | 福岡市東区 | 37 |
| 18 | 都立駒込病院 | 東京都文京区 | 36 |
| 19 | 千葉大学病院 | 千葉市中央区 | 36 |
| 20 | 神戸��学病院 | 神戸市中央区 | 33 |
膵がんの切除手術は、合併症が起こりやすい難しい手術である。とくに膵頭部がんの場合、膵臓と消化管をつなぐ必要があり、これが極めて難しい。膵臓は膵液という消化液の分泌器官だが、つないだ部分から膵液が漏れ出すと、大変なことになる。膵液が血管を消化し、大出血を起こしたりするのだ。
「手術で合併症が多いのは、膵臓手術の宿命と言えます。ただ、外国で行われたいくつかの無作為化比較試験で、多数の手術を行っている病院のほうが、手術数の少ない病院より、合併症による死亡率が低いという結果が出ました。難しい手術では、経験を積めば積むほど悪いことが起こらなくなるし、たとえ困ったことが起きても、慣れているほうが正しい対処ができます。それが、合併症による死亡率を下げることに貢献したのでしょう」
これらの研究結果を踏まえ、ガイドラインには次のように記載されることになった。
「膵頭十二指腸切除など膵癌に対する外科切除術では、手術症例が一定以上ある専門医のいる施設では、合併症が少ない傾向があり、合併症発生後の管理も優れていると推察される(グレードB)。」
膵頭十二指腸切除とは、がんのできている膵頭部を切除する場合の術式で、膵がんの手術では最も難しいとされている。
では、どのくらい手術している施設なら安心なのだろうか。田中さんによれば、膵頭十二指腸切除を年間20~30例以上行っていることが目安になるという。多いほどいいと言っても、年間50例以上の病院となると、全国でもいくつもないからだ。
「最近は、手術のために病院を移る患者さんが増えてきました。日本人は、あまり病院を変えない傾向がありますが、膵がんの手術に関しては、患者さんが動くようになってきましたね。非常にいいことだと思います」 膵がんの手術は、難しい手術だからこそ、手術数の多い病院のほうが安心だ。
局所進行膵がんには化学放射線療法を推奨
転移はあるが遠くの臓器には転移していないステージ4aには、切除手術が可能な場合と、不可能な場合がある。そして、切除手術ができない場合を、局所進行膵がんと呼ぶ。遠くには転移していないが、動脈浸潤があって切除できないケースである。
このような場合に推奨されているのは、放射線療法と、5-FUによる化学療法を同時に行う化学放射線療法だ。ガイドラインには、次のように書かれている。
「局所進行切除不能膵癌に対する5-FU併用化学放射線療法は、有効な治療法であり、治療選択肢の一つとして推奨される(グレードB)」
この化学放射線療法は、効果の中心は放射線療法で、抗がん剤は放射線の効果を高める増感剤として作用しているという。
「無作為化比較試験の結果、放射線療法単独よりも、化学療法単独よりも、化学放射線療法が優れていたという結果が出ています。グレードBですから、この治療によって生存期間が延びることははっきりしています」
ただ、化学放射線療法には欠点もある、と田中さんは言う。それは、放射線療法のために、毎日病院に通わなければならない点だ。
かつてのように、膵がんに抗がん剤がほとんど効かない時代であればともかく、ジェムザール(一般名塩酸ゲムシタビン)やTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)のように、よく効いて副作用も少ない抗がん剤が登場してきている。化学放射線療法より、化学療法単独のほうがいいと考える人がいても不思議ではない。ただ、これらの抗がん剤を使った単独療法と、化学放射線療法を比較した大規模な臨床試験は行われていないという。
そこで、ガイドラインでは、局所進行切除不能膵がんに対する化学療法単独の治療は、標準治療として推奨するだけの根拠に乏しいとしながらも、「明日への提言」として、次のように書かれている。
「塩酸ゲムシタビンによる化学療法は、副作用が比較的軽く、外来治療が可能であるため、化学放射線療法に比べて患者への負担が少ないと考えられる。両者の比較試験が存在しない現段階においては、エビデンスが十分でないことを患者に説明した上、塩酸ゲムシタビンによる化学療法を選択肢の1つに加えることは可能と考える」 局所進行膵がんの治療は、よく効く抗がん剤の登場によって、過渡期を迎えていると考えていいようだ。
化学療法の進歩で膵がん治療が変わった
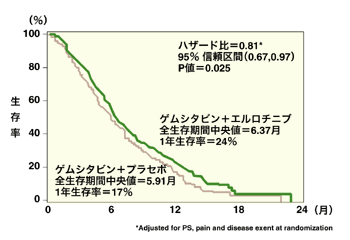
遠くの臓器に転移しているステージ4bの膵がんに対しては、化学療法が標準治療である。使われる抗がん剤はジェムザール。ガイドラインでは、次のように推奨されている。
「遠隔転移を有する膵癌に対する一次化学療法としては、塩酸ゲムシタビンが推奨される(グレードA)」
ジェムザールの登場によって、膵がんの治療は大きく変わった。切除手術のできないケースが約9割を占めるだけに、効果的な抗がん剤の登場は、膵がん治療に大変革をもたらすことになったのだ。
「ジェムザールの登場以前は、多くの患者さんが半年ほどしか生きられませんでした。それが、年単位で生きられるようになってきたのですから、大変革です。それも、入院したままではなく、わずか2~3週間で退院。通院は必要ですが、生活を制限されることは少なく、仕事をする人もいるほどです」
ジェムザールの効果は明らかだが、それと並んで期待されているのがTS-1である。このガイドラインでは推奨されていないが、臨床試験は進められているという。
「切除手術を行えなかった膵がんに、ジェムザールとTS-1を、どう使えばいいか調べる大規模な臨床試験が行われています。ジェムザール単独、TS-1単独、最初から両者の併用。この3つのグループで試験が勧められています」
この無作為化比較試験の結果によって、ステージ4bの化学療法は、新しい局面を迎えることになるだろう。
次の改訂の目玉は術後補助化学療法の記述
また、手術後の補助化学療法も、大きく変わろうとしている。このガイドラインには、術後補助化学療法について、このように書かれている。
「塩酸ゲムシタビンによる術後補助化学療法の延命効果は、現時点では確定していない(グレードC)」
勧めるだけの根拠が明確でないということだ。ただ、「明日への提言」として、次のような記述が加えられている。
「現在進められている臨床試験により、本療法(塩酸ゲムシタビンによる術後補助化学療法)の延命効果が確定すれば、本ガイドラインにおいても、推奨度がより高く位置づけられるものと予想される」
この臨床試験の結果はすでに出ていて、術後補助化学療法でジェムザールを使うことで、少し生存期間が延びることが明らかになっている。「明日への提言」で予想されたように、ガイドラインの改訂版(2009年刊行予定)では、ジェムザールによる術後補助化学療法を推奨する内容に変わるという。
「ガイドラインは3年ごとに改訂していく予定になっていますが、現在の時点で、8割くらいまで改訂作業は進んでいます。改訂の目玉となるのは、ジェムザールによる術後補助化学療法ですね。それから、TS-1という飲み薬が出てきたので、その部分も新しく加わることになります。飲み薬の登場で、患者さんの闘病生活がさらに制限の少ないものになっていく可能性があります」
多くのがんの中でも、膵がんはとくに治療の困難なことで知られている。それが劇的に変わることはなさそうだが、着実な進歩を見せている。来年刊行される改訂版には、3年分の進歩が書き加えられることになる。
(構成/柄川昭彦)
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


