膵臓がんの治療の中心は化学療法か化学放射線療法か ジェムザールを凌ぐ治療法の研究が着々進む
研究が進む放射線治療
放射線治療の研究も進んでいる。重粒子線治療が膵臓がんに対して行えないか、放射線医学総合研究所で現在、臨床試験が行われている。この場合の組み合わせは、ジェムザール+重粒子線治療になる。重粒子線治療のメリットは「ピンポイント照射が可能なこと」(奧坂さん)にある。
また、5-FU系列の抗がん剤であるTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)に放射線治療を加えた化学放射線療法の臨床試験も現在、日本で行われている。
4期の標準治療はジェムザール。併用療法に期待が
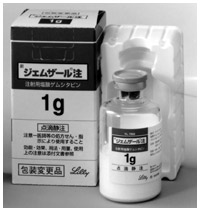
4期、すなわち転移がんの化学療法は具体的に何が行われているのだろうか。
「ジェムザールの単独治療が事実上の標準治療です。ただし、さまざまな併用療法が研究されています」(奧坂さん)
ジェムザールは膵臓がんの治療に承認されているため、保険が適応になる。ほかに膵臓がんの治療に承認されている抗がん剤にはTS-1がある。そのため、ジェムザール+TS-1の治療を行っている施設もある。しかし、ジェムザール+TS-1のエビデンス(科学的根拠)は、まだ確立されていないため“見切り発車”的な治療であることも否めない。
海外の臨床試験でさまざまな試みが
ある程度、成果の出ている臨床試験も幾つかある。
1つは、ジェムザール+タルセバ(一般名エルロチニブ)の2剤併用療法。カナダの研究グループが実施した国際共同治験の結果では、ジェムザール+タルセバのほうがジェムザール単独よりも生存期間が10日ほど延びたという。
ジェムザール+ゼローダ(一般名カぺシタビン)の2剤併用療法も期待されている。
「イギリスの研究グループが実施した臨床試験で、ジェムザール単独よりも1.4カ月ほど生存期間が延びました。ただし中間報告で、最終的なデータはまだ出ていません」(奧坂さん)
また、同様の臨床試験を行ったスイスのグループの結果では、ジェムザール単独に比べて有意な差はなかったという。
ジェムザール+エルプラット(一般名オキサリプラチン)の2剤併用療法の臨床試験は、フランスとアメリカの研究グループがそれぞれ実施した。いずれのグループの結果も、ジェムザール単独に比べて統計学的な差はなかったが、よい傾向は見られたという。
エルプラットに限らず、プラチナ系の抗がん剤はこれまで4期の膵臓がんに有意な効果は出ていない。しかし、「エルプラット+ジェムザールやランダ+ジェムザールなど、プラチナ系の抗がん剤+ジェムザールの臨床試験結果をトータルで解析すると、統計学的にも、ジェムザール単独に比べ生存期間が延びるという結果になる」(奥坂さん)。
とはいえ、ジェムザールにプラチナ系の抗がん剤を加えるのが望ましいとまでは、まだ言えない状況でもあるようだ。
分子標的薬であるアバスチン(一般名ベバシズマブ)やアービタックス(一般名セツキシマブ)の臨床試験も行われている。
アバスチン+ジェムザール、アービタックス+ジェムザール、それぞれの2剤併用療法とジェムザール単独の比較試験では、統計学的な差はなかった。
3期と4期、両方のステージの患者を対象にして、TS-1の臨床試験も行われている。
「日本と台湾で現在、ジェムザール単独、TS-1単独、ジェムザール+TS-1、それぞれの比較試験が行われています。比較試験を行う前に、ジェムザール+TS-1の臨床試験が行われましたが、その結果が良好だったため、比較試験でのTS-1の治療成績も期待されています」(奧坂さん)
ほかに新しい成果や動きはあるのだろうか。
「アキシチニブ(一般名)という新しい分子標的薬があります。アバスチンに似た血管新生阻害薬で、昨年、小規模な比較試験において良好な傾向が確認されました」(奧坂さん)
アキシチニブの試験対象は3期と4期の患者である。現在は、日本も参加している大規模な臨床試験(国際共同治験)が行われていて、もしその結果、治療成績に有意な差が出れば、今後、アキシチニブが使われるようになることもありうるという。
ジェムザールの術後補助療法で再発延長効果
先述のとおり、1期と2期は手術の適応になる。では手術後、再発予防のために補助療法を行ったほうがよいのだろうか。
「手術後の再発のリスクを抑えるために、ジェムザールを行うべきかどうかという比較試験がドイツと日本で行われました。いずれの試験でも、手術後にジェムザールの補助療法を行ったほうが再発までの期間を有意に延ばせることが判明しました」(奧坂さん)
生存期間に関しては、手術後にジェムザールの補助療法を行ったほうがよい傾向が認められたが、統計学的な差までは見られなかったという。
手術を受けた患者は補助化学療法を受けるべきかどうか、判断に迷いそうである。
「基本的には、医師と患者さんが十分に話し合って、患者さんが納得して判断されるべきことです。ただ現状では、ジェムザールの術後補助療法を行っている施設のほうがずっと多いと思います」(奧坂さん)
再発するまでの期間が延びること自体は喜ばしいが、少ないとはいえ、ジェムザールの副作用の問題もある。そのため、補助化学療法は再発した場合に初めて行えばよいと考える専門医もいる。再発した際に行う化学療法も、第1選択はジェムザールである。
国立がん研究センター中央病院では、術後補助化学療法を受けている人はどれぐらいいるのだろうか。
「データを示し、インフォームド・コンセントをしっかり行ったうえで、およそ半数ほどの患者さんが受けています。
私たちの施設では、ご希望によって補助化学療法の臨床試験に入っていただくこともあります。また、治療を始めた後、副作用の状態などによっては、治療を中止することもあります」(奧坂さん)
膵臓がんに対する化学療法や化学放射線療法の治療成績は、少しずつではあるが、向上してきている。非常に厳しいがんであることに変わりはないが、治癒の可能性を探る努力は日夜、続けられている。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


