進行別 がん標準治療 手術で治癒を、放射線化学療法、抗がん剤治療でできるだけの延命を
膵臓がんの手術
拡大手術をすれば合併症増加
膵臓がんでは、手術が唯一治る可能性のある治療法です。そのため、かつては血管浸潤があっても拡大手術が行われていました。
しかし、木下さんによると「結局、拡大手術をしても治療成績は向上せず、合併症が増えるばかりと判明した」といいます。アメリカでは、70年代にフォートナーが血管の合併切除と広範囲のリンパ節郭清による拡大手術を提唱しましたが、入院死亡率が高く、治療成績が上がらないため、ほとんど振り向かれませんでした。しかし、日本では広範囲リンパ節郭清と血管周囲の神経鞘、つまり神経をくるむサヤをぐるりと全周にわたってむく拡大手術が効果があると長く主張されてきました。木下さんによると、神経鞘をまるごとむくと、ひどい下痢が必発し、腹部大動脈周囲のリンパ節まで拡大すると、手術時間が長くなり、そのぶん合併症も増えるといいます。
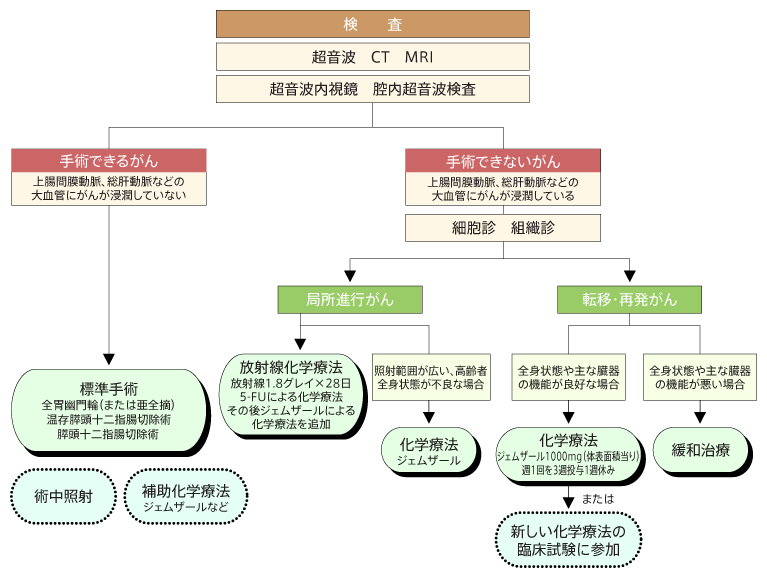
そこで、欧米では標準的な手術と拡大手術を比較する臨床試験が行われ、基本的には拡大手術を行っても意味がないというデータが出されています。日本でも5年ほど前に、相前後して2つの比較試験が行われています。一方は、拡大手術を受けた患者と標準手術を受けた患者100例以上を対象に解析を行ったものです。その結果、両者の治療成績には全く差がありませんでした。つまり、無理をして拡大手術を行っても、結果は標準手術と同じという結論だったのです。
同じ頃、切除可能な進行膵臓がん(4A期)を対象に、外科手術と放射線化学療法を少数例で比較、手術をしたほうが延命期間が長いという結果が報告されています。しかし、これは、少数での報告でもあり、疑問を呈する向きもあります。
木下さん自身は「膵臓がんは、厳しいがんでおのずと限界もあるのです。拡大手術には意味がないと私自身は考えており、東病院でも行っていません。全国的にもこうした考えで手術を行っているところが多い」と語っています。ただし、今でも拡大手術を行っている施設もあるそうです。
膵臓がんの標準手術

木下さんの執刀による手術シーン
膵臓がんの手術は、標準手術でも周辺臓器を一緒に切除します。膵臓がんは、大半が膵臓の頭の部分、つまり膵頭部にできるため、膵頭十二指腸切除術と呼ばれる手術がよく行われます。以前は、膵頭十二指腸、隣接する胃の3分の2、空腸(小腸)の一部、下部胆管、胆嚢を切除するのが、一般的でした。しかし、胃に関しては「がんが胃袋近くにありリンパ節転移をしている場合は胃まで切除する必要がありますが、ふつう膵臓がんが胃の周囲にまで及ぶのは、かなり進行してから」(木下さん)だといいます。
そのため、ここ20年ほどは術式の見直しが行われ、胃と幽門(十二指腸につながる胃の出口)を残す全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術と呼ばれる手術が一般的になっているそうです。ただし、木下さんによると「全部胃を残して再建すると、胃の排出遅延が起こりやすいので、最近は幽門輪を切って胃と腸をつなぐ人が増えている」そうです。
また、欧米ではリンパ節は膵臓についているものだけを切除しますが、日本では可及的にとれるものはとるのが基本。がんも、門脈に浸潤している程度ならば、とりにいくことが多いそうです。
ただ、これまで膵臓がんの手術には合併症が多いことが知られていました。木下さんによると「膵臓は、胃や腸と違って実質臓器なので、その難しさがある」といいます。膵臓を切断すると、その断面では主膵管だけではなく、無数の細い膵管が切断されています。この断面を胃や腸とつないで再建すると、膵管からもれた膵液が傷の治癒を妨害し、傷口の縫合不全を起こすことがあるのです。膵液は、タンパク質を消化する消化液であるため、漏れた消化液が動脈を消化し、手術して2~3週間後に突然大出血を起こすことがありました。これが、入院死の大きな原因にもなっていたのです。
しかし、「ここでは、吻合のしかたや膵液を排出するドレーンの留置をシンプルにして、傷口の治癒を妨げないようにすることで、ほとんど重い合併症は起こらなくなりました。入院期間も2~3週間で、以前なら考えられないほど短期間になっています」と木下さん。ただ、現在でも全国的にみると、入院死が5~10パーセントを超えるところも珍しくないといいます。したがって、「膵臓がん手術になれた病院で手術を受ける」ことが、大切なのです。
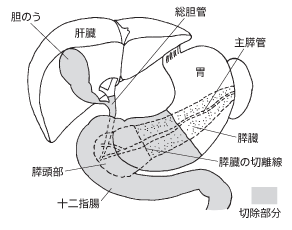
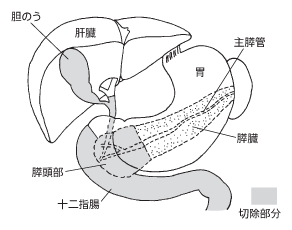
再発リスクを抑える術後補助療法
このように手術は安全に行えるようになっていますが、それでも浸潤性膵臓がんの5年生存率は16パーセント程度と他のがんに比べてかなり低いのが現状です。「きれいにとったようでも、8割5分はがんが残っているということです」と木下さん。そこで、再発のリスクを少しでも抑えようと、補助療法の研究が行われています。
木下さんは、現在放射線の術中照射、つまり手術中に、がんの摘出後膵臓のあった後腹膜などを中心に放射線を照射することが、再発予防に効果があるのかどうかを、検討しています。この他、国内では術後補助化学療法としてジェムザールを投与する群としない群で比較試験が進行中です。
一方、イギリスなど欧州を中心とした研究グループでは、術後補助療法を行わない、術後5-FUとロイコボリンによる補助化学療法を実施、術後5-FUを中心に放射線を併用する放射線化学療法を実施する、という3つのグループに分けて、大規模な比較試験(ESPAC-1=Euroean Study Group for Pancreatic Cancer)が行われました。その結果、5-FUとロイコボリンによる補助化学療法のみ効果があったと報告されています。そこで、現在は5-FUとロイコボリンのグループとジェムザールのグループで比較試験が行われているところです。
アメリカは、伝統的に放射線を中心に治療が考えられていますが、現在術後、放射線を照射してから5-FUを投与、続いてジェムザールを投与する試験が進行中で、間もなくその結果が出る予定です。
このように、まだ補助療法が有効なのか、あるいはどういう補助療法がいいのか、研究されている最中です。古瀬さんは「日本ではポジティブな結果はまだ出ていませんが、イギリスのグループを中心にした比較研究でいい結果が出てきているので、補助化学療法を行う方向になるかもしれません」と語っています。
現在は、補助化学療法を行う人と術後には行わず再発時に行うという人に分かれているそうです。ちなみに、国立がん研究センター東病院では、放射線の術中照射の臨床試験が行われ、再発時には再発形式に応じ、放射線治療や化学療法を実施するという方法をとっているそうです。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


