進行別 がん標準治療 手術で治癒を、放射線化学療法、抗がん剤治療でできるだけの延命を
局所進行がんの治療
放射線化学療法が標準治療
血管浸潤などがあって手術できない局所進行がんの場合、治療は放射線と抗がん剤を併用する放射線化学療法が標準的です。
80年代には放射線単独より放射線化学療法(抗がん剤は5-FU)が優れていると報告されていますが、化学療法単独と放射線化学療法ではどちらが優れているのか、まだはっきりした結論はないのが実情です。
しかし、1997年にジェムザールと5-FUの比較試験の結果、ジェムザールの奏効率は5.4パーセントと低かったものの、疼痛などの症状緩和効果が高く、生存期間も長かったため、化学療法では現在ジェムザールが第1選択になっています。そのため、今後は「ジェムザール単独化学療法と放射線化学療法の比較試験が必要」と古瀬さんは語っています。
化学療法は、全身的ながんの制御と同時に、放射線の感受性を高めて効果を増幅する効果があると考えられています。実際には「放射線を多くかけてもあまり延命効果はないので、化学療法のほうにウエイトが置かれている」と古瀬さんは語っています。切除不能がんの場合、放射線で局所のがんを制御しても、7~8割は遠隔転移という形で進行していきます。すでに、画像では見えない転移が存在していることも多いのです。そこで、全身的効果を期待できる化学療法にウエイトがかけられているのです。
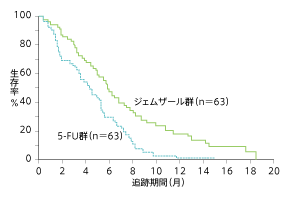
新しい放射線化学療法の試み
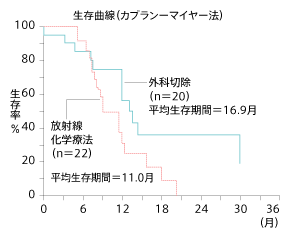
一般には、放射線を1.8グレイずつ28回(週に5日実施し、2日休み)、つまり5週間半照射します。そして、いろいろな方法はありますが5-FUは放射線と並行して24時間連続で、1日体表面積あたり200~250ミリグラムを点滴で投与することが多いそうです。その後、さらにジェムザールによる全身化学療法を追加することもあります。
ただし、古瀬さんによると「絶対的な標準治療はまだないのが現状で、転移が出てから抗がん剤を使ったほうがいいのかどうかも、はっきりとはわかっていないのです」。
放射線とジェムザールを同時並行で行う治療も試みられています。この場��、吐き気や白血球減少など副作用がかなり強く出るため、ジェムザールの量を減らさなければなりません。放射線治療も、1回の量を増やして回数すなわち治療期間を減らしたり、逆に1回の量を減らして回数や総線量を増やす試みも行われています。現在古瀬さんらは、新しい抗がん剤を用いた放射線化学療法など新たな試験に取り組んでいます。このように局所進行がんでは、今後新しい治療法が開発され、確立していくことが期待されているそうです。
膵臓がんの安全性を高める術式
膵臓がんは、膵臓の切断面から膵液が漏れてくることが、傷の治癒を遅らせ、重大な合併症を起こす引き金にもなっていました。
そのため、従来はできるだけ膵臓をしっかりと縫い合わせ、さらに膵液などの貯留を防ぐためにたくさんのドレーンを留置して、排出を促してきました。
しかし、全く発想を変えて木下さんらは手術の安全性を高めることに成功しています。従来のように、ガッチリと膵臓の断面を縫ったり、たくさんのドレーンを傷口に留置すると、かえって膵臓の血流が障害され、傷口の治癒を遅らせる結果になると考えたのです。そこで、「傷口の自然治癒を妨げない」ことを目的に、改良を施しました。膵臓の断面は寄せて4~5針縫うにとどめ、ドレーンの留置も最小限に止めました。
その結果、「東病院が開設された頃には、縫合不全から大出血を起こした例もありましたが、このようなシンプルな手術にしてからは1例も起こしたことがない」といいます。また、膵臓周囲の神経を処置する場合も半周のみ神経鞘をはぐようにし、大動脈周囲のリンパ節も転移の有無をみるサンプリング程度の切除にとどめているため、後遺症もほとんどなく、安全に手術が行えるようになっているそうです。
転移・再発の治療
ジェムザールが第1選択
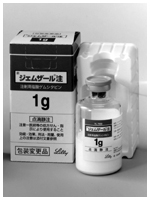
現状では、膵臓がんが発見された時点で遠隔転移が見つかる人が半数にのぼるため、全身化学療法が最も多く行われることになります。
この場合、現在では5-FUに変わってジェムザールが第1選択薬になっています。体表面積あたり1000ミリグラムを週に1回ずつ3週間投与しては1週間の休みを繰り返すのが標準的な使い方です。
ただし、ジェムザールは副作用が少なく、効果においても5-FUをしのぐとはいえ、その効果は十分とは言えません。そこで、現在ジェムザールと他の抗がん剤との併用、あるいはジェムザールの投与方法を工夫することで、治療効果を高める研究が進んでいます。
たとえば、通常ジェムザールは30分ほどで点滴投与されるのですが、アメリカではこれを150分かけて1.5倍量を入れる定速静注法も試みられています。
この方法では、1年生存率(約20パーセント)、半分の人が生存する生存期間中央値(7.3カ月)とも、1回に大量を投与するより効果が高いという結果が出ています。
奏効率が高い併用療法
一方、併用療法では、欧米ではファルモルビシン(一般名エピルビシン)やタキソテール(一般名ドセタキセル)、ランダ(もしくはブリプラチン、一般名シスプラチン)、エルブラット(一般名オキサリプラチン)などとの併用試験が行われています。いずれの場合もジェムザール単独より奏効率が高まることが報告されていますが、生存期間を改善する効果については明らかではありません。中でも、エルブラットが注目され、現在アメリカでジェムザール単独とエルブラットを併用した場合、さらにジェムザールの定速静注の3種類での比較試験が進行しているそうです。「その結果しだいでは、ジェムザールとエルブラットの併用療法が標準治療になる可能性もあります」と古瀬さんは指摘しています。
一方、日本では5-FUを改良した経口抗がん剤であるTS-1が注目されています。すでに臨床試験では期待できる治療成績が得られており、さらにジュムザールとの併用も期待されています。「ここ1~2年の間に、結果がでるでしょう」と古瀬さんは語っています。
この他、血管新生阻害剤のひとつであるアバスチンなどの新しい分子標的治療薬との併用療法も研究が進んでいます。膵臓がんの治療成績は、現状では決して高いものではありませんが、ジェムザールの登場を契機にさまざまな治療法が開発されつつあり、その進歩が期待できる時代に入ったといえます。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


