まずは実績のある医療機関へ。臨床試験への参加も1つの手 過酷な難治性がんとどう闘うか~難治性がん最新レポート
使える薬がない!
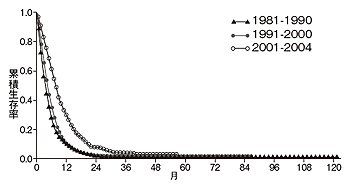
たとえば膵がんでいえば、基本的に病期分類の3期までは手術が適用される。しかし、それ以上にがんが進行している場合は、ジェムザール、TS-1、そして分子標的薬のタルセバ(*)の3剤による抗がん剤治療しか選択肢は残されていない(図5)。その後に残されている唯一の選択肢は緩和ケアだ。膵がんの妹を持つ篠田さんがうなだれるのもそうした過酷な事情によるものだ。
パンキャンジャパンには、膵がん患者からのさまざまな相談が持ち込まれるが、そこで多くを占めているのが、抗がん剤を行った後の治療についての質問だ。
「患者にすればもっと治療の選択肢がほしい。アメリカでは膵がんの治療に10種類近い薬剤が認められています。進行膵がんの患者でも多剤併用療法により平均寿命は日本の倍の2年ともいわれています。国際共同治験に参加できればスムーズに海外の新薬が使えるのですが、日本では臨床試験のハードルが高くそれも難しい。せめてドラッグ・ラグが解消されれば、もう少し希望が持てるようになるのですが……」と、眞島さんは声を落とす(図6、写真7)
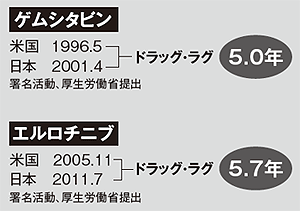
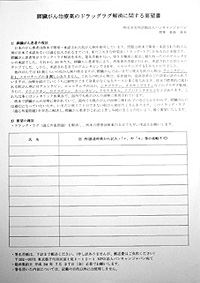
*タルセバ=一般名エルロチニブ
治療のすべが少ない現状
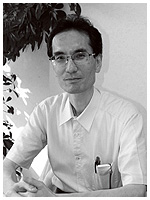
奥坂拓志さん
早期発見が難しく、予後も芳しくなく、しかも治療法も限られている──こうした難治性がんの厳しさ、難しさは臨床現場で患者と相対する医師たちの悩みでもある。
「私のところを訪れる患者さんは、他病院で手術できないと判断された患者さんが多くを占めています。ほとんどの患者さんに抗がん剤などの薬物治療を行いますが、その場合には、その先の緩和ケアまでを見通して患者さんにはお話しをするようにしています」と、いうのは国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科科長の奥坂拓志さんだ。
膵臓と同じく肝臓、胆道がんの治療も容易ではないと奥坂さんはいう。肝がんについてみてみると、切除手術の他にラジオ波による焼灼療法、カテーテルを用いて、がんを兵糧攻めにする塞栓術などの内科的治療があり、さらに最近では手術不能の患者を対象にネクサバール(*)という分子標的薬も用いられている。しかし肝硬変などで肝機能が低下している場合にはこれらの治療法も限定される。加えて日本ではウイルス性肝炎由来の肝がんがほとんどを占めており、そのために治療が成功しても再発・転移の危険は決して小さくはない。
また胆道がんについても現状は厳しい。治療の基本は手術だが、膵がんと同じように早期発見が難しく、大半の患者が抗がん剤治療に頼らざるを得ないのが実情だ。
さらにその場合に用いられる抗がん剤も、ファーストラインでジェムザールとシスプラチン(*)が、セカンドラインでTS-1が使われると、その後、患者には治療のすべが残されていない。当然、薬剤もずっと効いているというわけではなく、次第に効かなくなってくる。
「膵がんでは薬を始めてだいたい4~5カ月すると、効かなくなってきます。胆道がんの場合も抗がん剤を始めてからの平均余命は11~12カ月が目安となっています。いずれにしても、治療の現状は厳しいと言わざるを得ません」
*ネクサバール=一般名ソラフェニブ
*シスプラチン=商品名ランダ/ ブリプラチン
生活を高めるのも医師の役割
こうしたなかで奥坂さんは、膵がん・胆道がんのがん患者を対象に、毎週1度、栄養士やソーシャルワーカー、薬剤師などを講師に招き、院内で患者のための「膵がん・胆道がん教室」を開講している。そこでは、食事はどのようなものがいいか、またどんな医療サービスが受けられるか、他にも、緩和ケアではどんな薬剤を用いるのかなど、治療だけではなく、患者の生活を考えた指導が行われている。
「個々の患者さんに自分の病気や治療法を十分に理解して、QОL(生活の質)を高めてもらいたい。実際、副作用のことを理解するだけでも、患者さんの生活は変わります。医師の仕事は治療だけではありません。もっとも適切な治療を提供するのは当然のことですが、それとは別に患者さんの日々の暮らしをより充実させるために働きかけることも、私たちの大切な仕事ではないでしょうか」
世界規模で遺伝子解析が進む

中釜斉さん
このように現状では、難治性がん患者が置かれている状況は依然として厳しい。しかし、近い将来、それが一変する可能性もある。多くの患者たちの声に応えるように、難治性がんに照準を定めた研究プロジェクトが着実に進行を続けているのだ。
今年の6月、内閣府は日本医療の高度化を目指して「医療イノベーション5か年戦略」を打ち出している。そこでは官・産・学の連携をベースに、がんの新薬など革新的な医薬品の創造が第1目標に掲げられ、臨床試験システムなど、新たな枠組みづくりも提唱されている。
そうした潮流の中で個々の研究機関でも新たな取り組みが行われ始めた。たとえば国立がん研究センターでは、昨年10月に「難治がん研究分野」を発足、それまでは個別に進めていた難治性がんの研究を系統的に推進、製薬企業、医療機器メーカーなど企業との連携も活発化している。
また、それとは別に同センターは5年前からアメリカ、ヨーロッパ諸国など13カ国で構成する国際がんコンソーシアムというプロジェクトにも参画している。これは参加国が特定のがん症例を500例ずつ集め、それぞれのがんの成り立ち、治療法について遺伝子レベルで解析を進めようというものだ。ちなみに同センターは理化学研究所とともに日本人に特徴的なウイルス性肝がんの遺伝子解析を担当しており、予算は5年間で約20億円。すでに20数例の症例については、全ゲノムの解読が完了している。
国立がん研究センター研究所長の中釜斉さんはこうした研究を通して、新たな難治性がん治療の方向性も浮かび上がってきたと話す。
「肝がんや膵がんなど、難治性がんは遺伝子変化の複雑さや症例数の少なさが理由でがん発症のメカニズムについての研究が遅れていました。肺がんや乳がんで用いられているような分子標的薬が難治性がん治療でほとんど見当たらないのもそのためです。しかし、これからは大きく状況が変わっていくでしょう」
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


