まずは実績のある医療機関へ。臨床試験への参加も1つの手 過酷な難治性がんとどう闘うか~難治性がん最新レポート
「がんのアキレス腱」を探す
具体的に見てみよう。
たとえば同じ膵がんでも、腫瘍の中心部と周辺部では、がん細胞の性質が異なることがわかってきた。中心部で低酸素、低栄養の状態で生存しているがん細胞は、過酷な環境に耐えて進化しているためより強力で、この細胞を叩くことが効果的な治療につながることも考えられる。
また、その膵がんが肝臓に複数個転移した場合は、個々によって遺伝子変異が異なることも判明している。もっともその場合でも、転移がんに共通する遺伝子も存在する。それらの遺伝子は「がんのアキレス腱」と呼ばれており、中釜さんはそれがこれからの難治性がん研究のキーポイントになると睨んでいる。実際、先にあげた肝がんの遺伝子解析では、このがんのアキレス腱の候補も特定され、そこに照準を合わせた研究も進められているという。
「これからはがんのアキレス腱をターゲットにした治療薬が次々と開発され、それが抗がん剤治療の主たる薬剤になる可能性も十分にある。医療イノベーションの目標年次の5年後にはそうした研究が具体化しているかもしれません」
それは医療界の大目標である個別化治療につながっていくに違いない。
今後、早期発見のための腫瘍マーカーなどの新たなツールやがんワクチン、再生医療などの先端技術が重なり合い、治験システムなど研究開発の枠組みが見直されることで、がん医療全体がより高度化されながら個別化に向かっていくと中釜さんは期待を込める。
実績のある病院、医師へ
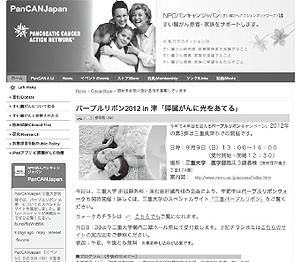
このように長いスパンで見ると、難治性がんの治療には大きな可能性が広がっている。しかし現在に視点を戻すと、患者には過酷としかいいようのない状況が浮かび上がる。そのなかで希望を見出すために、患者はどう行動すればいいのだろうか。パンキャンジャパンの眞島さんは、治療を受ける医療機関の選定に力を尽くすべきだという。
「難治性がんでは、専門医はそれほど多くない。だからこそ実績のある医師、医療機関を選びたい。ネットなどで情報を吟味して自らが患っているがんを数多く扱っているハイボリュームセンタ―を探してもらいたいですね。できれば医師も実績のある人を選びたいものです」
ちなみにパンキャンジャパンでは、膵がん治療に実績のある医療機関、医師をネット上で公表している(写真8)。同じことは進行がんを対象にした抗がん剤治療にもあてはまると眞島さんはいう。
「これまでは抗がん剤治療も外科医主導で行われることが多かった。しかし、現在では支持療法も含めて、薬物治療は複雑化しています。外科医では対応しきれない部分もあるでしょう。そのことを考えると、抗がん剤を専門に扱う腫瘍内科医を選ぶ必要があると思います」
臨床試験への参加も考える
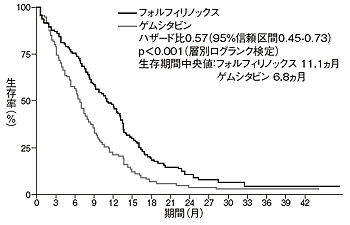
[写真10]

治療そのものについてはどうか。とくに進行性の難治性がんの場合は、治療選択がきわめて限られている。しかし方法がないわけではない。
「臨床試験への参加も1つの方策でしょう。タイミングが合えば、いい治療法にめぐり合える可能性もあります」
と、いうのは国立がん研究センターの奥坂さんだ。
たとえば進行膵がんに関しては現在、久留米大学病院、国立がん研究センター中央病院・東病院などで、がんペプチドワクチン(*)の臨床試験が継続中だ。また海外(フランス)で実施された、転移性膵がんを対象にしたジェムザールとの比較試験で、有効な治療効果を示したFOLFIRINOXという5-FU(*)、ロイコボリン(*)、イリノテカン(*)、エルプラット(*)による4剤併用療法も、現在日本で第2相試験が行われている(図9)。
他にも進行した胆道がんに対して、国立がん研究センターでは、今後ワクチンを用いた臨床試験を取り入れる予定としており、インターネットなどを通して、患者自身も最新情報をチェックしておく必要があるといえるだろう(写真10)。
*がんペプチドワクチンの臨床試験については、原稿作成時点の情報です。それ以降の臨床試験情報の変更につきましては、ご容赦ください
*5-FU =一般名フルオロウラシル
*ロイコボリン=一般名ホリナートカルシウム
*イリノテカン=商品名カンプト/ トポテシン
*エルプラット=一般名オキサリプラチン
検診で声をあげよう
そして、さらにもう1つ、一般の人たちにとっては、早期発見を心がけることも大切な点となる。そのことで難治性がん発症を食い止めることも不可能ではない。パンキャンジャパンの眞島さんは、実は今年の4月に、膵臓の全摘手術を受けている。
「私は50歳前の妹を膵がんで亡くしていますが、膵がんには家族性のもの(全体の5~10%)もあると言われていて、アメリカの学会が作成した家族性膵がんのガイドラインでは、親、兄弟、子供(第1度近親者)で膵がんになった人が2人以上、あるいは50歳前に発病した人がいる場合は家族性膵がんの疑いがあるため要注意と言われています。乳がんでもBRCA1、BRCA2の遺伝子変異による家族性乳がん、若年性乳がんの研究が進んでいますが、膵がんでもBRCA2、PALB2などの遺伝子異常と家族性膵がんの関連がわかってきました。また、大阪府立成人病センターによると、膵臓にのう胞という「袋」があり、主膵管の拡張もみられる人はハイリスクグループ(がんになる危険性の高い人)に分類され、要注意と言われています。私自身、家族歴もあり、のう胞があり、さらに主膵管の拡張がみられるというハイリスクグループの典型ですので、定期的に検診を受けていました。すると膵臓の上皮内にがんが早期で見つかったんです。それで、膵臓を全摘することにしました」
膵臓を全摘するかどうかは別にして、早期発見が難治性がん克服の切り札であることは事実だ。膵がんでいえば早期発見の広がりによって現在は20%にすぎない手術適用率が30%にも40%にも高められるだろう。そのためには1人ひとりの積極的な行動が必要と眞島さんはいう。
「現在日本では、家族性膵がんの登録制度がありません。また、疫学的なリスク因子をもとにしたハイリスクグループも特定されていません。だからこそ糖尿病患者さんなど不安のある人は検診の際に、『私の膵臓は大丈夫でしょうか』と問いかけたい。それだけでも状況は変わるはずです」
もちろん同じことは他の難治性がんにもあてはまる。少しでも不安があれば、そのままにせず医師や病院にぶつけたい。そうして早期発見によって命を保ち、新たな難治性がん治療の訪れに希望を紡ぎたい。
同じカテゴリーの最新記事
- 新規腫瘍マーカーでより診断精度向上への期待 膵がん早期発見「尾道方式」の大きな成果
- 化学・重粒子線治療でコンバージョン手術の可能性高まる 大きく変わった膵がん治療
- 低侵襲で繰り返し治療ができ、予後を延長 切除不能膵がんに対するHIFU(強力集束超音波)療法
- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜
- 膵臓は、実は〝沈黙の臓器〟ではない 膵がんの早期診断はここまで来た!
- 膵がん治療に朗報! 術前化学療法の確立をきっかけに飛躍へ
- 難治でも薬剤をうまく継いで長期生存を目指す 膵がん2次治療に6年ぶりに新薬「オニバイド」が登場
- 遺伝子情報をもとに効果の高い治療法を選択 膵がんにおける遺伝子変異に基づくゲノム医療とは
- 諦めないで、切除不能がんも積極的治療で手術可能に 膵がんの術前化学IMRT放射線療法で根治が望める


