1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
超寡分割照射と通常分割照射の効果を比較
1回線量を増やして照射回数を少なくする治療の臨床試験が世界的に行われているが、わずか7回の放射線照射(超寡分割照射)を行い、5年生存率、治療後時間が経ってから現れる晩期毒性が、通常分割照射(標準治療)と比べて劣らないとの報告がでた。
スウェーデンのウメオ大学のアンデシュ・ウィードマルク氏らによるHYPO-RT-PC試験で、『ランセット』オンライン版(2019年6月18日号)に掲載された。
超寡分割照射が、通常分割照射と比べて非劣性であることを検証する第Ⅲ相非盲検無作為化試験で、75歳以下の前立腺がん患者(中間リスク89%、高リスク11%)で、全身状態(PS)の比較的良い患者(0~2)を対象に、2005年7月~2015年11月に登録、1,200例が超寡分割照射群(589例)と通常分割照射群(602例)に割り付けられた。
通常分割照射群は2Gy×39回(78Gy;5日/週)照射、超寡分割照射群には6.1Gy×7回(42.7Gy;3日/週)照射された。追跡期間中央値は5年で、主要評価項目は治療成功生存率(FFS)とされた。
結果は5年時のFFSがどちらも84%で、超寡分割照射が通常分割照射に対して非劣性であることが確認された。また、5年無病生存率(DFS)は、超寡分割照射群94%、通常分割照射群96%で、有意な差が認められなかった。
一方、有害事象については、治療終了時に超寡分割照射群でグレード2以上の尿路毒性がわずかに増加した(28% vs. 23%)が、5年時のグレード2以上の尿路毒性と腸管毒性には差が見られず、治療後の晩期放射線障害にも違いがなかった(図3)。
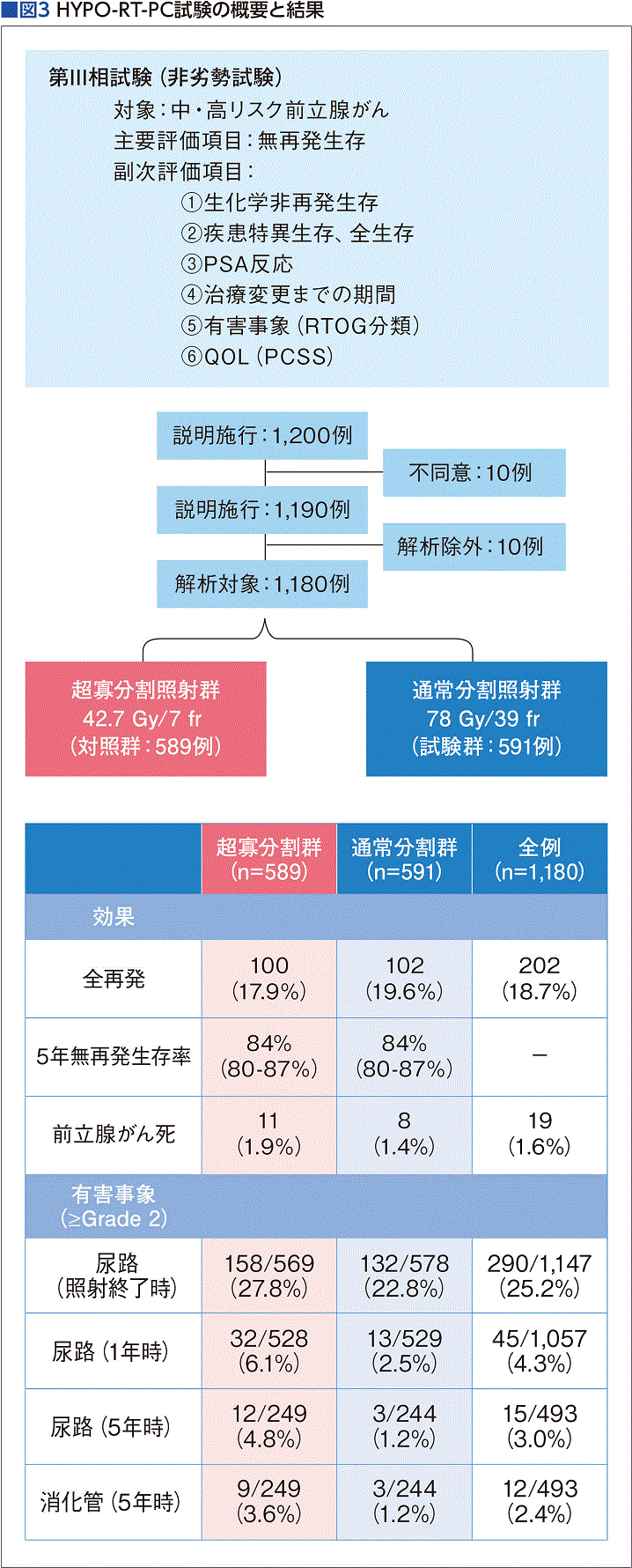
前立腺がんは1回の線量を増やすことで効果が見込める
1週間に5日、約8週間に渡り通院する通常分割照射は、日本における前立腺がんの標準治療だが、患者、とりわけ社会復帰した患者にはかなりの負担だ。
「この試験結果は、回数にして7回、2週間とちょっとの通院で通常分割照射と同じくらいの治療効果が得られ、同じくらいの副作用で済む可能性が高いわけですから、超寡分割照射は患者さんの治療中のQOLとしては確実に良いと言えるでしょう」と石川さんは語る。
ただし、この報告については、2つ注意が必要とのこと。1つは超寡分割照射が通常分割照射に比べて優れているのではなく、〝劣っていない(非劣性)〟報告である点。もう1つは欧米の患者を対象とした試験であり、日本人の患者で��ずしも同じ結果が得られるとは限らないという点だ。
「それでも、1回の線量を増やし、照射回数を減らす寡分割照射や超寡分割照射は、これから浸透する治療で、いずれは標準治療となるでしょう」と石川さん。
目的は患者のQOLだけではない。
「肝がんや肺がんでは、高線量を数回で終了する超寡分割照射は早くから行われてきました。肺や肝臓の一部は手術で切除できる、つまり、一部が失われても生きていける臓器だからです。前立腺がんは1回の線量を増やすことで得られる治療効果が非常に高いがんです。しかし、前立腺は臓器の内部に尿道がありますし、周囲にも直腸や膀胱など重要な臓器があり、そこに放射線が照射されてしまえば、重篤な放射線障害が起きてしまう。そのため、線量を高くしたほうが良いとわかっていてもできませんでしたが、高精度放射線治療の開発で、がんをピンポイントで狙い撃ちし、周囲の臓器に放射線が強く照射され図に高い線量を投与できるようになったことで、可能性が開けてきたのです」と石川さんは語る。
今後は寡分割/超寡分割照射に移行するのは確実だが課題も
では、日本では現在、寡分割照射はどのくらい行われているのだろうか。また、超寡分割照射に対する臨床試験は行われているのだろうか。
「1回の線量を増やし、回数を減らす動きは、海外では日本より10年くらい早く進められています。日本では、1回の線量を増やすのがようやく標準治療になってきたところです」
例えば、2014年に登録が終了し、20施設132例が登録した「前立腺がんに対するIMRT/IGRT併用寡分割照射の第Ⅱ相臨床試験」(厚労省科学研究費補助金がん臨床研究事業)では、1回2.5Gy×28回(70Gy)の照射によって日本人が有害事象を増加しないことを目的として行われた。これは2019年に経過観察が終了し、そろそろ結果が発表されるはずだが、実際には2.5Gy×28回は標準治療的に行われるようになり、今日では3Gy×20〜21回の照射を行う施設も増えているという。
「私たちの陽子線医学利用研究センターでも、陽子線を使った放射線治療を39回から28回に、そして現在は21回まで減らしていますが、もっと減らして行こうとしています。どちらも7~8年かけて臨床試験を行い、効果と安全性が確認できたためです」
石川さんに、陽子線治療での回数を何回まで減らすのを目標にしているか尋ねると、「はっきり言えませんが、10回前後かと思います。10回前後というと2週間くらいは要しますが、患者さんにとって1週間と2週間で負担の大きさは、そんなには違わないと思います」とのこと。
しかしながら、超寡分割照射については、日本人における治療効果と安全性についてのエビデンスがなく、まだほとんど行われていないのが現状という。
現在、国内では国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院(旧放射線医学総合研究所病院・千葉市)では、超寡分割照射による臨床試験を開始している。限局性前立腺がんの患者を対象に、重粒子線を4回照射する治療における安全性と効果を検証する臨床試験が行われている。しかし今後、日本で超寡分割照射の臨床試験が行われる可能性は今のところ高くないという。
前立腺がんへの寡分割照射を行う施設はまだ少数
「正直、今から臨床試験を行うのはなかなか難しいと思います。なぜなら今日、前立腺がんのさまざまな放射線治療については、ほぼ保険適用されていますから。海外で非劣性が証明されれば、治療の現場で使うこともできます。もちろん、導入には慎重さが必要ですが、臨床試験が行われなくても、寡分割/超寡分割照射が拡大していくことは間違いないと思います」
その一方、前立腺がんで寡分割/超寡分割照射がなかなか普及しないのは、実施している施設数が少ないためでもあるという。この治療は定位放射線治療のできる施設では実施可能であり、そうした施設は全国に100施設程度はあると考えられているが、前立腺がんに定位放射線治療を行っている施設となると、「10とか20といった少数」なのだそうだ。
日本では放射線治療を担当する放射線腫瘍医の数が不足しているが、線量の計算や治療計画を立てる医学物理士は、欧米諸国と比較して極端に少ない。これは、日本では医学物理士が国家資格ではなく、病院のポストも少ないためとのことだ。そのため、本来、医学物理士が行う業務を医師や放射線技師が行っていることが多いそうだ。
また、超寡分割照射がなかなか普及しないもう1つの理由は、患者が必ずしも新しい治療を希望しないことだという。
「前立腺がんの放射線治療に関していえば、少なくとも早期の治療については良い成績が出ていますから、安全が確認されている治療を普通に受けようという人は多いです。しかし、逆に言えば、良い成績が出ているからこそ、数回で治療を終わらせてもいいのではないか、というのが超寡分割照射の考え方です。一定レベルが確保されていて、マイナス要因が少なく、費用も少し安いですから」
寡分割/超寡分割照射は、今後、魅力的な治療オプションの1つになっていくと思われるが、患者の選択希望も見逃せない要素となるようだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


