この春保険適用になり、前立腺全摘除術でますます期待される手術法 尿失禁や性機能障害を抑える最新ロボット手術
症例の解析から見るロボット手術の治療成績
| 中央値(最小値-最大値) | |
| 手術時間 | 342分(264-526) |
| コンソール時間* | 270分(208-413) |
| 出血量(尿込み) | 200m(l 0-2350) |
| 輸血 | 1例(自己血) |
| 経口摂取開始日 | 1日(1-2日) |
| 歩行開始日 | 1日(1-2日) |
| ドレーン抜去日 | 3日(3-8日) |
| バルーン抜去日 | 8日(6-8日) |
田中さんらは2010年10月から2011年9月までに実施された40症例について治療成績を解析した(表7)。
開腹手術との比較で差が出たのは、出血量である。田中さんらの症例での出血量は200ml(中央値)。自己血輸血(*)が必要だったのは1例だ。
「出血の多さが開腹手術のデメリットなので、輸血が必要のない出血量で済むというのはロボット手術の大きな長所です」
では、回復の早さはどうなのか。手術後1日から2日目には口から食事をとることも歩行も可能だった。これは内視鏡手術よりもいいということではなく、同じ��ベルである。
田中さんは、「傷が小さいので回復が早いという印象はありますが、実際にそれを証明したデータは現時点ではありません」という。
「前立腺がんの手術では尿道カテーテルを1週間つけておきますが、ロボット手術の場合、もう少し早く抜けるのではと考えられています。ただ神戸大学医学部付属病院では開腹手術と同様、尿道カテーテルを6~8日留置しているため、退院時期は開腹手術とそれほど差がありません」
気になる合併症だが、皮下出血や一過性の尿閉などの軽いものが6例(40例中)あっただけで、深刻な合併症はなかった。
とはいえ、世界的にみると腸管損傷など重い合併症の報告もあるという。
「開腹手術でも起こる可能性のあることは、ロボット手術でも起こるかもしれません。ロボット手術ではリスクがまったくないということではなく、できるだけ少なくしていけるという点で安全性が高いといえるのだと思います」
*自己血輸血=あらかじめ貯めておいた自分の血液を戻す輸血方法
繊細な手術で尿漏れと性機能障害が減少
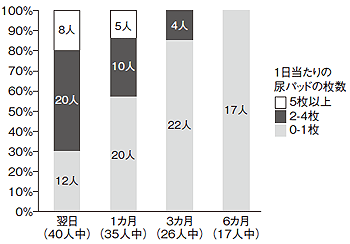
1日に使用したパッドの枚数から尿失禁の出現率をみると、翌日から0~1枚という人もいる。3カ月たてば5枚以上使う人はいなくなり、6カ月後には全員0~1枚となっている(図8)。
「手術件数の多い施設のデータを見てみると、尿パッドが0~1枚となる人は、6カ月後で70~90%とばらつきがあります。当院も症例が増えたら数字が変化すると考えられます」としながらも、「他の術式と比べて非常によくなる可能性がある」という。
性機能では、勃起の保持について見ると、術後3カ月で50%、半年で75%が回復という結果になっている。少例(6例)での解析のため、他の報告よりも好成績だが、開腹手術と比較すると良好だ。
田中さんは、がんが前立腺被膜を越えているかもしれないが性機能を残したいという患者さんを執刀した経験がある。術前のMRI検査で被膜にがん細胞の浸潤が疑われた一方の側はしっかり取り除き、もう片側は残した。病理検査の結果、切除断端は陰性だった。
がんはきれいに取れて神経を温存できたケースである。
「やはり繊細な手術ができるのだと実感しました。今後のことは未知数ですが、現在の症例での経過から見ると性機能の温存と維持に優れているといえます」
大切なのはがんを取りきれるかどうか
田中さんが大切だと強調するのはがんの根治性である。がんの取り残しがあるかないかは手術時に採取した「切除断端」の病理検査結果が目安になる。「切除断端陽性」だと取り残しの可能性があるというわけだ。
陽性だったのは40例中8例。これをリスク分類別にみると、ステージではT2(31例)で5例、T3(7例)で3例。グリソンスコアが6以下(3例)で1例、グリソンスコア 7(35例)で7例である。
「切除断端陽性率は20%で、初期40例としては欧米から出ている報告と遜色なく、だいたい予想通りといったところです」
切除断端については、陽性例と陰性例では陰性例のほうが再発しない確率は高いが、陽性だから再発するわけではなく、危険因子の1つと位置づけられていることを理解しておきたい。
4月から保険適用になり普及が期待される
最近の傾向として、性機能温存を希望する人が増えてきたと田中さんはいう。
「MRIなどの画像検査がさらに進歩すれば、がんの大きさや広がり具合をより正確に評価できるでしょう。その確実な診断に基づいて、患者さんが希望するならば機能温存にできる限り応えていきたいです」
ロボット手術は高額な費用がネックとなって普及が遅れているが、2012年4月、保険適用になったため、導入する施設が増えることが期待される。
保険適用以前は、同院の場合で、入院と手術の費用として138万円を患者さんが全額自己負担していた。保険適用により、公的健康保険を使った患者さんの負担額はその約1~3割となる。
田中さんは、「今後患者さんがロボット手術を受ける機 会は、増えていくでしょう。治療の選択肢が広がりますので、医師からしっかり説明を聞いてご自分の受けたい治療を選んでいただきたいです」とアドバイスする。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


