がんの確定は生検で、その前に重要なのがPSA検査 前立腺がん、どんな検査でどう診断するか?
悪性度などがんの素性を暴くのが生検
前述のとおり、PSA検査はあくまでも生検が必要か必要でないかをふるい分けるための検査であって、前立腺がんと確定するには生検が必要です。
生検とは、直接前立腺に針を刺して組織をとってきて、その組織を診断し、がんかどうか、またどのような性質のがんなのかを調べる検査です。
生検の方法は、超音波 で前立腺を観察しながら、お尻の穴、または陰嚢の裏側から針を刺し入れて行います。針の大きさは、長さが1㎝強、太さは1~2㎜で、点滴に使う針の太さと同じようなものと考えていいでしょう。針の数は従来では6本程度でしたが、現在では、がんができやすい前立腺の辺縁部を中心に、まんべんなく10~12本刺すのが一般的で、局所麻酔か全身麻酔、脊椎麻酔をしたうえで針を刺します。全身麻酔、脊椎麻酔の場合は最低1泊の入院が必要です。
「採取した組織を診断することにより、がんの確定診断だけでなく、がんの顔つきや悪性度など、がんの素性を知ることができます。そうしてそのがんに適した治療法を決定します」
生検は、体に針を刺す侵襲的な検査ですから、稀ではありますが出血や感染などを起こすことがあります。MRI(核磁気共鳴画像法)などの画像診断も進歩していますが、未だがんの確定には難しく、生検が必ず必要です。
治療効果の指標はPSA値でみる
治療開始後に、その効果や経過を観察する手段としてもPSA検査は有効です(図5)。
「前立腺の全摘手術を行うと、前立腺をすべてとってしまっているので理屈の上ではPSAは測定感度以下、つまり限りなくゼロに近くなります。しかし、手術後に3カ月に1回とか定期的に検査を行い、PSA値が上昇してきた場合には、前立腺以外の体のどこかにがんが再発していると考えざるをえません。施設によって違いがありますが、術後の検査で0.2を2回あるいは3回続けて超えると再発と判断する場合が多いです」
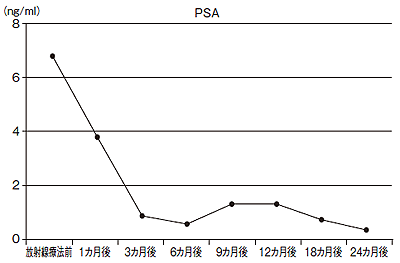
放射線治療も全摘手術と同じ根治治療ですが、全摘のように前立腺を摘出するわけではありません。しかし、全摘手術と同じように、治療後はほとんど測定できないくらい低くなります。この場合も、放射線治療後にPSAが上昇を続けているようなら再発と判断されます。
再発しているかどうか、がんが小さいうちは画像診断ではほとんどわからないので、PSAの値が重要、と武藤さんは指摘します。
なお、放射線治療後に、数値が一時的に上昇することがあります。しかし、経過を見ているうちに再び下がっていくので、心配はいりません(図6)。
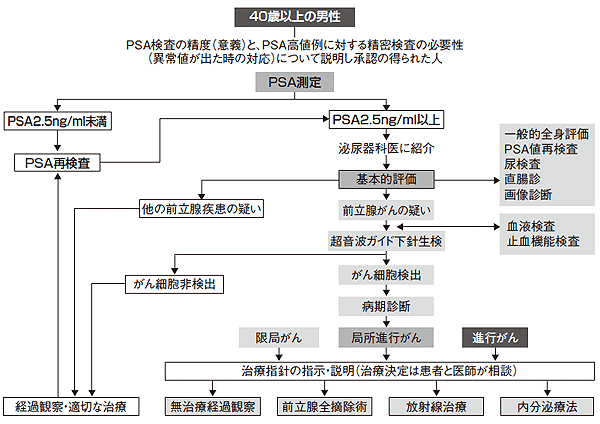
PSA値に振り回されない
「再発しているとわかればホルモン療法を追加しますが、ホルモン療法が効いているかどうかもPSAの値で検討します。ホルモン療法を行っているのに数値が上がるようなら、ホルモン療法が効いていないことになります」
ホルモン療法を始めた後に、PSAの値が上昇してがんが勢いを増してくることを「去勢抵抗性」といいます。
「ホルモン療法でPSAの値が上がるのは、ホルモン療法が効かないようながん細胞が増殖を始めて、がん細胞の性質が変わってくるからです。以前はそうなると、正直いってお手上げでしたが、今はタキソテール(*)という抗がん剤が登場して、効果を上げています」
このように、治療後のPSA検査は重要ではあるものの、あまりにPSAの値に一喜一憂して過剰な不安を抱くのは好ましくない、と武藤さんは次のように語っています。
「がんという診断がついて治療をしている方は、治療の内容によって適正なPSA値というのがあります。治療効果が十分にあると考えるPSAの数値はどのくらいなのか、これは主治医の先生とよく話し合いましょう。その上で適性と判断される範囲にある限り、PSA値の変動を過剰に心配する必要はありません」
*タキソテール=一般名ドセタキセル
治療法が決まるまでのさまざまな検査・診断
前立腺がんの検査の中心はPSA検査であるが、これは直接がんを捕えて検査するわけではないので、限界があることもまた事実。そのため、PSA 検査の弱点を補うさまざまな検査・診断が、用意されている。
PSA の値に異常があった場合、最初に行われるのが、排尿の状態などを調べる尿検査や直腸診である。
直腸診は、医師が直接肛門から直腸に指を入れ前立腺の背面を腸壁ごしに前立腺にふれる検査である。この方法は前立腺の大きさや弾力、しこりの有無を確認することができるため、PSA検査で発見できないタイプのがんも発見できる。ただし、客観的なデータが取れず、指で触れることのできない部分は確認できないので、見落としが発生してしまう。
これをフォローするのが、経直腸エコーなどの画像診断だ。超音波を発するプローブと呼ばれる器具を肛門から直腸内に入れ、前立腺の形や構造などを確認し、がんの有無を確認したり、がんの位置を調べたりできる。ただし、この検査はある程度、がんが大きくならなければ確認できないため、早期発見には不向きである。
一連の検査でがんの疑いがある場合は、確定診断である生検が行われる。生検は患者への負担が大きい検査ではあるが、がんの有無や悪性度など、今後の治療方針を決めるために大切な情報を得ることができる。とくに前立腺がんの場合、悪性度、いわゆるがんの顔つきを調べる指標として「グリソンスコア」が重要になってくる。生検で取り出した組織を顕微鏡で観察し、正常細胞に近いパターンから、最もがんの顔つきが悪いパターンまで分類し、悪性度を判定する。
生検でがんと確定診断された場合、最終的な治療方針を決定するために、CTやMRI、骨シンチグラフィなど、体全体の診断を行い、転移の有無などを確認する場合もある。とくに、前立腺がんの場合は、骨に転移が生じやすいため、早期の骨転移を発見するのに、骨シンチグラフィは有効な検査だ。
これらの検査・診断をきちんと行い、その時々の状況にあった最善の治療法を考えることが治療のポイントになる。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


