共に戦っていくための、今知っておくべき最新情報 前立腺がんでも、長く健やかに過ごせる!新しい治療法と情報が満載
講演2「前立腺がんに対する手術療法」
より体の負担が軽い、合併症の少ない手術を追求して
演者:座光寺秀典 山梨大学大学院医学工学総合研究部泌尿器科学助教
 | 体への負担が軽い手術について紹介する 座光寺秀典さん |
合併症を減らす配慮が必要
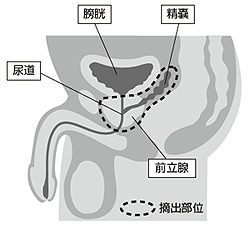
手術は前立腺がんを根治できる治療法です。しかし、根治を期待できるのはがんが前立腺内にとどまっている早期がん。がんが周囲の臓器に浸潤したり、転移したりしている場合、原則として手術の適応にはなりません。また、10年以上の余命が期待できる、全身状態が良好であるといった手術を受けるための基準もあります。
前立腺がんの手術では、基本的に「前立腺全摘除術」が行われます。これは前立腺やそれにつながる精嚢(精液を貯めておく器官)をまとめて摘出する手術。尿道の一部も切除するので、同時に膀胱と尿道をつなぎ合わせます。手術時間は通常2~3時間で、2~3週間の入院が必要です。
前立腺全摘除術は、勃起不全といった性機能低下に加え、術後の尿漏れといった合併症を起こしやすいことが難点といえるでしょう。こうした問題を避けるため、手術中は前立腺のまわりの神経や筋肉をなるべく傷つけないよう配慮します。最近ではがんが小さく、悪性度も低い場合、被膜(前立腺を覆う膜)近くを通る勃起神経を温存する方法も取り入れられるようになりました。
さまざまな術式がある
従来の開腹手術に加え、いくつかの新しい術式が普及しつつあります。
「腹腔鏡下前立腺全摘除術」は、腹部に数カ所の小さな穴を開け、そ��から内視鏡や手術器具を挿入して前立腺を摘出する手術法。出血量が少なく、傷の回復も早いといった利点があります。しかし、高い技術が要求され、実施できる医療機関は限られます。
「ミニマム創手術」は5センチ前後の手術創から内視鏡を挿入して、手術を行う方法です。体の負担が少なく、腹腔鏡手術ほど難易度が高くないので多くの施設で実施されています。また、最近では大学病院を中心に「ロボット支援手術」も導入されつつあります。これはロボットの体内3次元画像と精密な器具を利用して手術を行うシステムで、安全で確実な操作が簡単に行えるようになりました。
手術の合併症対策としては、勃起不全に対する治療薬、尿漏れを改善する骨盤底筋体操(排尿を調節する筋肉の強化体操)などがあります。こうした対策も術後のQOLを保つのに役立ちます。
講演3「前立腺がんの放射線治療」
前立腺がんでは体にやさしく、効果も大きい放射線治療が大活躍
演者:早川和重 北里大学大学院医療系研究科放射線科学教授
 | 「放射線治療は体にやさしい」と述べる 早川和重さん |
幅広く使われている放射線治療
前立腺がんでは放射線治療が幅広く行われています。早期だけでなく、病期3期、4期の進行がんでも活用されています。
その主な理由としては、体への負担が比較的少なく、治療を行いやすいことがあげられるでしょう。たとえば、手術も効果の大きい治療法ですが、体への負担が大きく、高齢の患者さんが多い前立腺がんでは、適応できない例が少なくありません。
ただし、前立腺がんの放射線治療にも副作用はあります。副作用としては、治療中、治療直後に尿道炎や直腸炎、皮膚炎といった一過性のものが生じますが、重篤な後遺症が生じることはほとんどありません。放射線には遺伝子を破壊してがん細胞の分裂・増殖を阻害する作用があり、それをがん治療に利用するのですが、放射線治療ではがんだけでなく、正常組織にも放射線が当たって障害を受けてしまうため、副作用が起こるのです。そこで近年、がんに放射線を集中して当てる治療法の改良が進められてきました。
放射線をがんに効率よく当てる
| 外照射療法 | |
| 前立腺部に線量を集めることが可能で、直腸への線量を低くすることができる ■3次元原体照射 ■強度変調放射線治療 | |
| 密封小線源治療(組織内照射) | |
| 低線量率線源を用いた永久刺入や高線量率線源を用いた一時刺入がある | |
| 重粒子線治療 | |
| ■陽子線・炭素線照射 | |
[放射線治療の効果](密封小線源療法・北里大学)
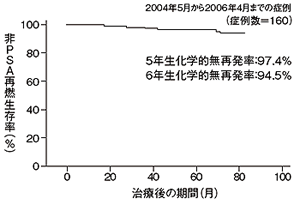
前立腺がんの放射線治療には主に、体外から放射線を当てる「外照射療法」と前立腺内に放射線源を直接挿入する「密封小線源療法」があります。
外照射療法では、臓器の形に合わせてさまざまな方向から放射線を当てる「3次元原体照射」、放射線の強さを調整しながら、多角的に放射線を当てる「強度変調放射線治療」などが登場しています。いずれも正常組織へのダメージが少なく、がんに効率よく放射線を当てられる治療法です。
密封小線源療法も、がんのまわりの正常組織にはあまり障害を与えません。放射線源の粒を前立腺内に埋め込む方法と、前立腺に差し込んだチューブ内に一時的に放射線源を入れる方法があります。また、正常組織には障害をほとんど与えず、がんに届く位置に合わせて大きなエネルギーを出す特殊な放射線を使った「重粒子線治療」も研究されています。
北里大学では低・中間リスクの前立腺がん患者さん160人に密封小線源療法を行い、経過を調べました。その結果、6年後の非PSA再燃生存率(PSAが正常値だった割合)は94.5パーセントに達しました。このように、前立腺がんの放射線治療は成績も優れています。
講演4「前立腺がんの内分泌療法・QOL」
がんを薬で抑えるホルモン療法。副作用対策で上手に付き合う
演者:丸茂 健 東京歯科大学市川総合病院泌尿器科教授
 | 「ホルモン療法との上手な付き合い方」を紹介する 丸茂健さん |
がんを薬で抑えるホルモン療法
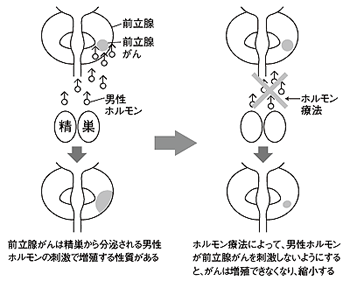
[ホルモン療法の主な種類]
| ・外科的去勢術(手術) ・抗アンドロゲン剤 ・LH-RHアゴニスト ・MAB療法 (抗アンドロゲン剤とLH-RHアゴニストを併用) ・その他(エストロゲン剤など) |
前立腺がんの特徴は内分泌療法(ホルモン療法)が効果を発揮することです。前立腺がんには、男性ホルモンの刺激によって増殖するという性質があります。そこで、男性ホルモンが前立腺がんを刺激しないようにすれば、がんの増殖を抑えられるというわけです。
ホルモン療法では、男性ホルモンを作る精巣を取り除く手術も、現在でもよく行われています。しかし、今では抗ホルモン剤を使う薬物療法がメインとなっています。抗ホルモン剤には、テストステロン(男性ホルモン)が前立腺に作用しないようにする抗アンドロゲン剤(経口薬)、脳に働いてテストステロンの分泌を阻害するLH-RHアゴニスト(注射薬)などがあります。抗アンドロゲン剤とLH-RHアゴニストを併用するMAB療法もあります。
薬物を使うホルモン療法は、体への負担が少なく、正常細胞に大きな障害を与えることもありません。そこで、さまざまな患者さんに適応できる利点があります。進行・転移したがんや、重い病気や高齢のために根治的治療ができないケースはもちろん、手術や放射線治療と併用されることもあります。
ホルモン療法特有の副作用
とはいえ、ホルモン療法にも、男性ホルモンの減少に伴う特有の副作用があることを知っておきましょう。まず、勃起障害、性欲低下といった性機能障害があげられます。男性ホルモンには骨の強度を高める働きがあるので、ホルモン療法によって骨粗鬆症のリスクも高まります。さらに、更年期障害のような「ホットフラッシュ」(のぼせ・ほてり・発汗など)という症状が現れることもよくあります。
勃起障害を改善するためには、PDE5阻害剤と呼ばれる治療薬や陰圧式勃起補助具といった医療器具が開発されています。骨量減少を抑えるには、ビスホスホネート製剤や活性型ビタミンD3といった治療薬もあります。ホットフラッシュには「桂枝茯苓丸」という漢方薬が有効という報告もあります。骨粗鬆症の予防には適度な運動、カルシウムやカリウム、ビタミンC・D・Kの摂取など、ホットフラッシュには冷やしたタオルの利用など、自分でできる対策もあります。ホルモン療法は長期にわたってがんの進行を抑えられる治療法なので、こうした副作用対策を取り入れて上手に付き合いましょう。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


