骨転移や疼痛が現れる前に治療を開始することで、より高い有効性が得られる ホルモン療法が効かなくなった前立腺がんに光を照らした新しい化学療法
タキソテールは外来で投与可能
副作用に苦しむのがイヤで、抗がん剤と聞いただけで拒絶反応を示す人もいるかもしれませんが、「この点でも画期的な薬がタキソテール。上手に使えばQOL(生活の質)を低下させずに生活できます」と堀江さん。
「がんに対する効果もさることながら、この薬のいいところは骨髄抑制(*)や吐き気といった副作用が比較的少ないので、高齢者でも安全に使うことができるし、短期間の入院、あるいは外来でこの治療を受けることができます」
あらわれやすい副作用としては、点滴中のアレルギー、また投与から数日間は発疹、吐き気・嘔吐、さらに数日から数週間は骨髄抑制、脱毛、筋肉・関節の痛み、好中球減少などがあらわれることがあります。
「好中球の減少などは一時的ですが、感染を起こしやすくなるので注意が必要です。それでも従来の抗がん剤に比べれば少ない頻度です。また、日本人に特有なものとして間質性肺炎(*)が起きることもありますが、これもまれです。もう少し頻度の高いものとしては手足のしびれがあり、その対策として漢方薬の牛車腎気丸が有効だという報告があり、当院でも効果を上げています」
副作用があらわれたり、体調がすぐれないときは、投与間隔を開けたり、薬剤の量を減らしたり、回復するまで治療を延期することもあるといいます。
ところで、タキソテールの治療をスタートしたときに注意すべきこととして、「当初、PSA値が上がることがある」と堀江さんは指摘します。
「治療を開始して2~3カ月は、治療しているにもかかわらずPSA値が上がる“フレア”という現象あります。しかしそれはあくまで一時的なことであり、そこで治療をやめずに継続していくと、やがてPSA値は低下していきます」
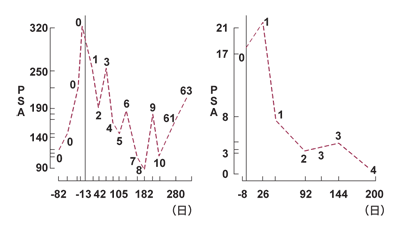
また、タキソテールを投与するときは、プレドニン(一般名プレドニゾロン)と併用するのが一般的です。
*骨髄抑制=がん治療で抗がん剤、放射線などにより、一定期間、骨髄の造血能が障害される状態
*間質性肺炎=肺炎が、肺胞や肺胞壁(間質)に起こる。非常に致命的であると同時に治療も難しい
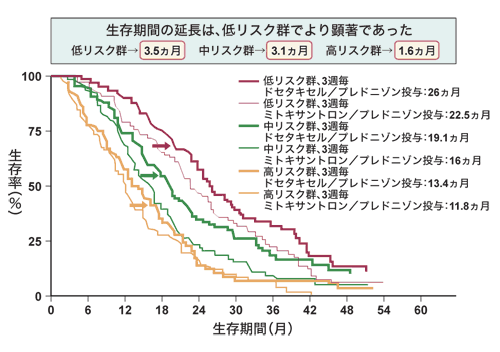
副作用は我慢しない
副作用があらわれたら、我慢しないで主治医に相談してほしい、と堀江さんはこう語ります。
「高齢者の場合、副作用が出ても我慢する人がいますが、我慢しないで早めに主治医に相談してほしい。早めに相談すれば早めに対処ができます。痛いのを我慢するというのは、本人にとってもよくないことだし、がんの治療にとってもよいことではありません。痛みを我慢するのではなく、痛みも積極的にとることによって治療効果がむしろ高まることもあるので、気になったことは何でもおっしゃっていただいたほうがいいですね」
投与法を工夫したら、効果もよくなって副作用も軽減されたという例もあります。たとえばタキソテール+プレドニンで効果が持続せず、プレドニンをエストラサイトへ変えたら再度、PSA値が下がった、という例もあります。
現在は、タキソテールの治療が効かなくなったときの新しい抗がん剤としてカバジタキセルとか、新しいホルモン治療薬としてアビラテロンなどの研究も進んでいます。ホルモン治療が効かなくなった後の治療は、より充実してくることが期待されています。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


