QOLを保ちながら、がんと付き合っていくことが大切 新たな抗がん剤の登場で変わるホルモン不応性前立腺がんの治療
前立腺がんの「再燃」と「ホルモン不応性」
- 血清テストステロンは去勢レベルを維持していること
- PSA値が2週間以上離れて3点連続上昇(2点でPSA値がnadir*より50%以上)
- AWS(アンドロゲン除去症候群)を少なくとも4週間観察
- 2次内分泌療法にも関わらずPSAが上昇する
- 骨病変あるいは軟部組織病変の進行ホルモン不応性の定義
- EAUガイドライン2007
再燃が起こる理由にはいろいろな機序が解明されているが、「前立腺がんが再燃する場合、多くは最初PSAの上昇だけが認められます。たとえば、ある程度の間隔をあけて3回連続して上昇した場合を再燃と定義することが多いようです」と賀本さんは言う。
ここで注意しなくてはならないのは、1度前立腺がんと診断された場合にはPSA値の「4」はとくに意味がなくなるという点だ。ホルモン治療をしていて、2週間以上の間隔をあけて3回連続でPSA値が上昇していたら、その値に関係なく再燃と定義されている。
昔のホルモン療法はアンドロゲンを下げるだけの方法しかなかったが、ここ10数年で抗アンドロゲン剤が開発され、再燃した場合でも効果を示す場合も多い。そのような再燃を繰り返しながら、いよいよホルモン療法がまったく効果がなくなった状態を「ホルモン不応性」と呼ばれている。
ホルモン不応性がわかり、タキソテールを使用している
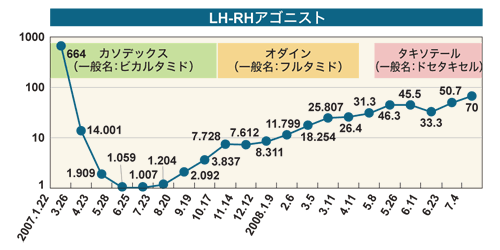
ホルモン不応性前立腺がんの治療法
タキソテールを投与しなければ、矢印のようにPSA値が上昇し、
がんが進行したと考えられる
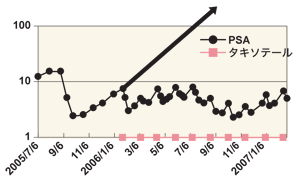
[ホルモン不応性前立腺がんにおける治療別生存率]
(京都大学付属病院)
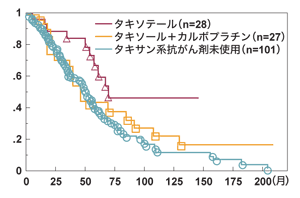
賀本さんは、「ホルモン不応性がんという状況になったら、予後は非常に厳しくなります。実際に、ほんの数年前までは、ホルモン不応性前立腺がんに効果のある抗がん剤はほとんどありませんでした。
しかし2004年にアメリカで承認されたタキソテール(一般名ドセタキセル)が、日本でも2008年8月から使えるようになったことから、以前のように、最初からあきらめたり、また緩和医療を施すだけという状況ではなくなりました」と言う。
日本でのタキソテールは、点滴静注を行う注射剤で承認されている。エビデンス(根拠)となっている使用量は、副腎皮質ステロイドとの併用で75ミリグラム/平方メートルを、3週間に1回投与となっている。
しかし賀本さんは、「臨床に携わる立場としては、この量は多いと感じています。副作用で苦しむことも少なくありません。
ですから当院では、患者さんのQOL(生活の質)維持のために、それぞれの病態に合わせて、量を60ミリグラム/平方メートルに減らすとか、間隔を4~8週間あけるとか、病気の勢いを抑えながら、患者さんの病態に合わせた治療を行うように心がけています」と言う。
ちなみに、タキソテールの副作用としては、骨髄抑制(感染症などにかかりやすくなる状態)、発疹などのアレルギー反応、嘔吐、吐き気、口内炎、下痢、味覚変化、筋肉や関節の痛み、脱毛、しびれ、むくみ、倦怠感などが挙げられているが、従来の化学療法剤に比べると比較的重篤な有害事象(副作用)の少ない印象があると言う。
その他の治療
(グレード3以上)
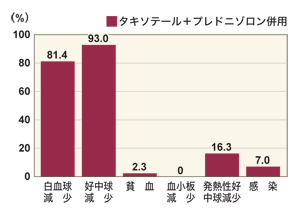
[国内フェーズ2試験における他の副作用発現率]
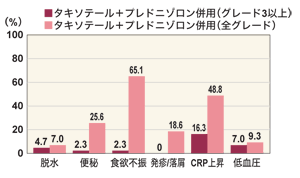
[前立腺がん骨転移に対する治療]
- 骨関連事象(骨痛、骨折など)に対して
―ゾレドロン酸(商品名ゾメタ)
―放射線治療 - 骨痛に対して
―ストロンチウム(商品名メタストロン)
―麻薬性鎮痛薬
がんの多くが骨転移をきたすが、中でも前立腺がんは骨転移の多いがんの1つである。進行がんでホルモン治療の効果がなくなったり、タキソテールが効かなくなったりした場合などは、最終的に、患者さんのQOLを保つための緩和治療を考えないといけない。賀本さんは、次のように話す。
「ホルモン不応性前立腺がんを完全に治すということはできません。しかし、タキソテールを使うことで延命効果を生みだし、上手くがんと付き合っていけるように考えることができます。
また、他のがんに比べても前立腺がんは骨に転移することが多いがんで、ホルモン不応性になると7~8割の人が骨に転移しています。激しい骨の痛みを抱えながら日々を過ごさなくてはならなくなる患者さんも少なくありません。そうした骨に関連する症状(骨関連事象と呼ばれます)を和らげることでQOLを維持し、できるだけ普通の生活ができるようにサポートすることが、何より大切だと私は考えています」
こうした骨の痛みを和らげるためには、放射線治療を行ったり、骨転移の治療に用いられるビスホスホネート系薬剤を使ったり、放射線治療薬のメタストロン(一般名ストロンチウム(Sr)-89)を使ったりする治療法が行われている。
賀本さんは、「前立腺がんの骨転移の痛みは、必ずしも転移部位すべてにおこすというわけではありません。したがって、もし痛みのあるところと転移部位が特定できる場合には、全身に影響を与えるモルヒネ治療よりも、放射線治療を積極的にお願いしています。
痛みの部位を特定できないような場合には、緩和医療チームにもお願いはしますが、ビスホスホネート系薬剤の投与や施設が限られますが、メタストロンも検討します。できるだけ、「骨の痛みを取る」ということを考える治療を行うべきだと思っています」と話す。
いずれにせよ、ホルモン不応性前立腺がんの治療は、タキソテールが登場したことで選択肢は広がった。また、他の臓器がんで用いられている分子標的薬を前立腺がんでも使えないかなど、新しい治療法の開発も進められている。
ただ、現時点でも骨転移に対する治療法もすすんでおり、これからはいかに骨転移をうまく制御していくかという点で、もっと研究を重ねていく必要がある。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


