前立腺がんと共存していくには、骨のケアが大切 前立腺がんが再発・転移しても長期のコントロールが可能に
破骨細胞の働きを止めるビスホスホネート
これで終わりではありません。まだまだカードはあります。たとえば、ビスホスホネートという薬剤などを使って、骨転移のある患者さんでも非常にいい状態を維持できます。
骨転移を起こすと骨関連事象(SRE)と呼ばれる、骨折などの患者さんに対して有害な事象が起きてしまうという認識が広まっています。それに対して、ビスホスホネートという薬剤が有効なのです。
前立腺がんは高率で骨に転移しやすいがんです。しかし、それはがん細胞自身が骨に作用して、骨を壊しているのではありません。骨には骨を壊す破骨細胞と、骨をつくる造骨細胞があります。がん細胞がさまざまな情報を出して、破骨細胞に働きかけますと、造骨細胞とのバランスを崩してしまい、骨に障害が出てくるわけです。ビスホスホネートという薬剤は、破骨細胞に取り込まれ、その骨を壊す働きを止める作用があります。
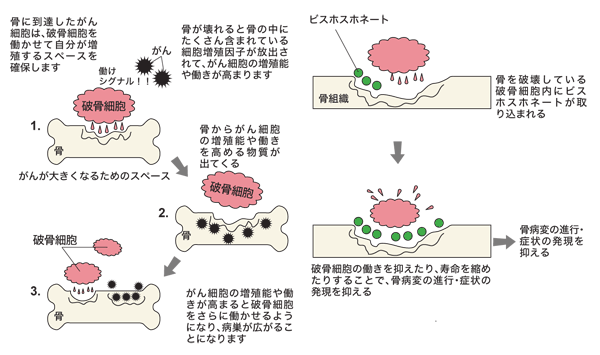
この薬剤は1980年代に開発されたあと、すでに第2世代、第3世代も開発され、現在、ゾメタ(一般名ゾレドロン酸)という薬が大きな注目を浴びています。ゾメタは第1世代の薬より1万倍効くことが、最近になってわかってきました。私たちも臨床で助けてもらっています。ゾメタは日本でも2006年から、固形がんの骨転移に保険適用になっています。ゾメタは、骨を原因とするさまざまな有害事象に対して、多くの患者さんがメリットを得られていることがわかっています。また、オランダの小さなコミュニティ・ホスピタルの試算ですが、先ほどの骨関連事象を起こした患者さん28名に、2年間でどれくらいの医療費がかかっているかを調べたところ、1人平均約1万3000ユーロでした。そのうち骨関連事象に対するものが約半分の6973ユーロです。いかに骨関連事象に治療費がかかっているかがわかります。したがって、早くからゾメタなどのビスホスホネートを使っていけば、骨関連事象への治療費は軽減され、医療費も圧縮できるという可能性が示唆されています。
ビスホスホネートの長所は、何といっても破骨細胞そのものをダイレクトに攻撃して、抑制してしまう点です。また、特殊な薬剤ではないために、一般のクリニックでも投与できるメリットもあります。さらに反復投与が可能である点も長所です。
短所は、投与直後にまれに発熱があること、投与が長期化すると低カルシウム血症になることがある点です。また、まれですが、腎臓の機能に影響を及ぼしたり、顎の骨が壊死することがあることが、海外で報告されています。
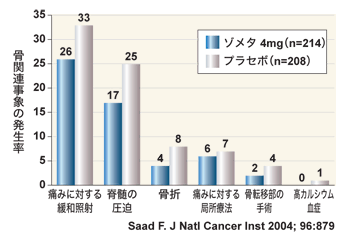
弱った骨を積極的に支える新たな骨セメント療法
まだカードはあります。次は緩和照射、放射線治療です。これはがんを根治するという目的ではなく、転移した部分に放射線を当てることによって、痛みを抑えたり局所での、がんの進行を抑えようというのが目的です。脊椎に当てる場合、背中から1門(1方向)だけ、骨だけに当てますから、副作用はほとんどありませんし、転移部の骨の痛みを抑えるだけでなく、その部位の骨折などを予防できる可能性が知られています。
まだ方法はあります。最近、骨セメント療法という治療法が開発されました。これは特殊なセメントを、転移部の骨の中に注入することによって、弱ってしまった骨を積極的に支えていく治療法です。これによって加重が掛かると痛みが生じるような脊椎などの転移部分も、骨セメントを注入することによって、もう1度加重に対して耐えられるような骨に戻るわけです。
骨セメントのメリットは、部位を選択的に治療できることと、支持骨という大きな骨にも有効な点です。デメリットとしては効果が確実ではなく、針を刺すために痛みが出ることがある点が挙げられます。
まだあります。放射線核種治療です。ある種の放射線物質を体内に注射で投与することによって、それが骨の部分でβ線(放射線の一種)を出し、骨の痛みを取る治療法です。理論的には骨シンチと同じです。この治療法は2007年に保険適用になっています。
国内ではストロンチウム-89という薬剤が使われていますが、がんを治すのではなく、あくまでも骨転移に伴う痛みを取る薬です。長所は痛み止めの麻薬を減らせる点、最期の段階で患者さんのQOL(生活の質)が改善される点です。短所はまだ施設限定で、全国どの病院でもできるわけではないという点です。また、ストロンチウム-89の供給を、海外の原子炉に依存している点も短所です。
前立腺がんが骨転移したからといって、今すぐに危ないということはありません。骨転移治療のポイントは、骨をうまく管理しながら、いかにしてQOLを維持するかということです。
前立腺がんとの共生にはボーン・ヘルスが不可欠
この記事で、是非知っておいていただきたいメッセージが2つあります。1つは前立腺がんの自然史です。一般的に、前立腺がんのPSA再発から転移までの中央値は、実に8年です。さらに、転移からがん死までの中央値は、さらに5年です。ですから、まだまだ時間があります。しかも、その間に新しい治療法が開発される可能性もあります。前立腺がんが再発した、転移したとしても、すぐに悲観することはありません。
もう1つは、PSA値ばかりを気にするのではなく、骨のケアが大切だということです。アメリカの調査では、骨折のない前立腺がんの患者さんの生存率と、骨折を併発した前立腺がんの患者さんの生存率には、大きな差が出ています。骨を大切にしていけば、進行・再発がんであっても、長期のコントロールは可能です。前立腺がんと長期に共存していくためには、ボーン・ヘルス(骨の健康)が不可欠なのです。
(構成/江口敏)
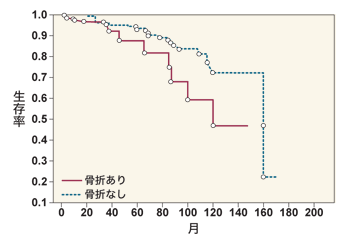
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


