ホルモン療法は前立腺がんの中心的な治療法 MAB療法は治療効果が高く、前立腺がんの進行を遅らせる
分泌を抑える方法と作用を抑える方法
ホルモン療法には、大きく分けて2つの方法があります。1つは、男性ホルモンの分泌を抑える方法。もう1つは、男性ホルモンが前立腺の細胞に作用するのを防ぐ方法です。
男性ホルモンの分泌を抑える方法には、精巣を取る手術(除睾術)があります。かつてはホルモン療法の中心でしたが、最近はあまり行われていません。
その代わりに、脳に働きかけて、精巣から男性ホルモンが分泌されないようにする方法が中心。LH-RHアゴニストという薬を注射する治療法です。精巣を取るのと同程度の効果があることがわかっています。 LH-RHアゴニストは、下垂体に働きかけて、下垂体のLH分泌能力を低下させます。脳の視床下部で分泌されるLH-RHは、ときどき分泌されて下垂体を刺激します。LH-RHアゴニストは、恒常的に下垂体を刺激することで、LHを分泌する能力を失わせてしまうのです。
LHは精巣に働きかけてテストステロンを分泌させるので、LHの分泌が抑えられると、テストステロンの分泌も抑えられます。効果が4週間持続するタイプと3カ月持続するタイプがあります。
女性ホルモン薬を使って男性ホルモンの分泌を抑える方法もあります。ただし、現在ではほとんど行われていません。
男性ホルモンの前立腺に対する作用を抑える方法としては、抗アンドロゲン薬(抗男性ホルモン薬)が使われています。こちらは内服薬で、カソデックス(一般名ビカルタミド)、オダイン(一般名フルタミド)、プロスタール(酢酸クロルマジノン)といった薬があります。男性ホルモンが前立腺に働きかけるのをブロックする薬です。
現在のホルモン療法はMAB療法が中心
ホルモン療法としてよく行われているのは、LH-RHアゴニストと抗アンドロゲン薬による治療を併用するMAB療法です。MABとは、Maximum(最大)Androgen(男性ホルモン)Blockade(遮断)の略で、前立腺がんに、最大限、男性ホルモンの影響が及ばないようにする治療法という意味。現在では、前立腺がんのホルモン療法は、MAB療法が中心になっています。
図3は、日本において、前立腺がんに対してどのようなホルモン療法が行われているかを示しています。MAB療法を受けている人が最も多く、ホルモン療法を受けている人全体の6割に達しています。
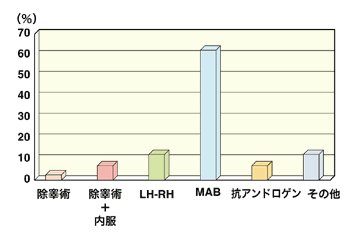
MAB療法を受けている人が多いのは、それだけ治療効果が高いからです。図4は、MAB療法とLH-RHアゴニスト単独治療の効果を比較したグラフ(ビカルタミドは抗アンドロゲン薬)。治療を開始したときは、腫瘍マーカーPSAの値はさまざまな異常値を示しています。それが改善し、正常値(4以下)になった患者の割合を示しています。MAB療法のほうが、早い段階で正常値になる人が多く、治療効果が高いことがわかります。
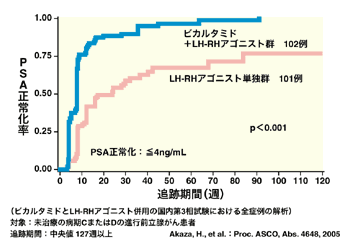
図5は、病気の進行の具合を比較しています。ホルモン療法を続けていると、効果が低下し、病勢が増してくることがあります。これを病勢進行と呼んでいます。MAB療法とLH-RHアゴニスト単独療法を比べると、MAB療法のほうが、病勢進行が現れるのが遅いことがわかります。治療開始から2年後の段階で、LH-RHアゴニスト単独だと、7割くらいの人に病勢進行が起きていますが、MAB療法ではそれが3~4割程度です。
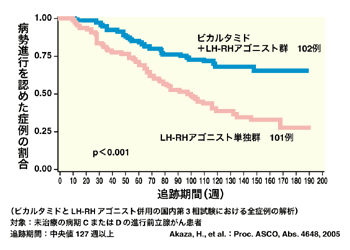
日本人にとくによく効く可能性
ホルモン療法は、日本人にはとくによく効くのかもしれない、と考えられています。それを示唆しているのが図6の研究。ハワイにおいて単独のホルモン療法を受けた白人と日系人の生存率を比較しています。
全生存率で比較すると、日系人の生存率が白人より高いことがわかります。全生存率は、すべての原因で死亡した人数を差し引き、生存率を求めた値です。
疾患特異的生存率は、前立腺がんで死亡した人数だけを差し引いて求めた生存率。つまり、どれだけの人が前立腺がんで死亡しなかったかを示しています。こちらでも、白人より日系人の生存率が高くなっています。
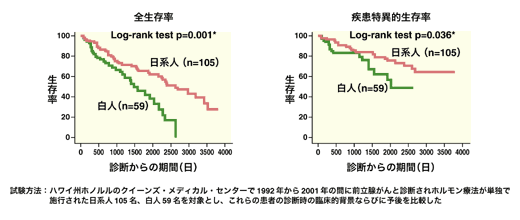
ハワイの日系人と白人なので、生活環境は共通していて、遺伝的要素の異なる集団を比較したことになります。この結果から、ホルモン療法は日本人にとくに効きやすいのかもしれない、と考えられるわけです。日本では、欧米よりホルモン療法がよく行われていますが、よく効くからなのかもしれません。
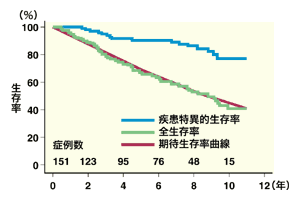
ホルモン療法は、安全な治療でもあります。それを示しているのが図7です。このグラフは、前立腺がんでホルモン療法を受けた人の疾患特異的生存率と全生存率、それに期待生存率を重ねてあります。期待生存率とは、ある年齢の人が、どのくらいの余命を期待できるかを示したものです。
注目すべきは、全生存率と期待生存率がきれいに重なっていること。つまり、前立腺がんと診断されてホルモン療法を受けた人の余命は、同年齢の人の平均と変わらないことを意味しています。
なおかつ、疾患特異的生存率が高いことから、前立腺がんで死亡する人は多くないことがわかります。つまり、前立腺がんと診断されても、他の重大な病気がなければ、平均より長生きできるとも考えられるのです。
ただし、安全な治療法とはいえ、ホルモン療法には副作用もあります。ホットフラッシュと呼ばれるほてりや急な発汗、乳房が大きくなったり乳首が痛んだりする女性化乳房、体重の増加、などがよく見られます。
気分が少し変化し、イライラ、不安などに悩まされる人もいます。頻尿の人も増えます。血液検査をすると、貧血、肝機能、血糖値などに異常が出やすくなります。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


