「前立腺がんと骨転移――上手にコントロールするためには?――」 骨転移はホルモン剤、ビスフォスフォネート剤を上手く使って治療しよう
非常に期待されるストロンチウムによる治療
ビスフォスフォネートをどういう場合に行うかについては、明確なデータが出ているわけではありませんが、ホルモン療法が効かなくなってきて、化学療法に移るかどうかというときに、ビスフォスフォネートを一緒に使うと、骨の痛みを改善することができることがわかっています。ただし、最初に骨転移を見つけたときに、ホルモン療法と同時にビスフォスフォネートを一緒にやったほうが良いかどうかについては、まだ十分な結果は出ていません。今、世界中でこの薬をどの時点で使うのがベストか、研究されているところです。
ホルモン療法を行うと、男性ホルモンが低下し、骨に対する影響が出て、骨粗鬆症のような症状が出てきます。ゾレドロン酸を投与するとその症状を抑えることができますから、前立腺がん治療による骨折の危険をある程度下げることができます。また、前立腺がんと骨の転移が一緒になったような症例の場合、転移の病巣にも作用して、骨折を抑制することができます。したがって、ゾレドロン酸をいかに上手に使うかが、今考えられています。
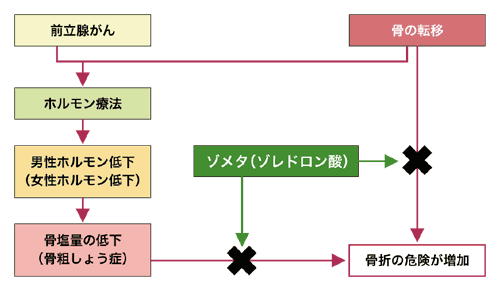
放射線治療は照射する部位が限局していたほうが効果的です。例えば、脊椎の3番目に転移があるが、他にはないというような場合、そこに放射線を当てると非常に有効です。ただ、他に転移がある場合には、全体に放射線を当てることができる場合と、できない場合があります。
最近、ストロンチウムによる治療も保険診療でできるようになりました。残念ながら、できる施設が限られていますが、早晩、大学病院ならどこでもできるようになると思います。ストロンチウムは骨にくっつきやすいという性格があり、その性格を利用して、前立腺がんの病巣にストロンチウムを打ちますと、そこで放射線を発揮して、その部位のがん細胞を死滅させます。
この薬の場合、がん細胞があちこちに転移していても、その部分に取り込まれて作用を発揮しますから、放射線を直接当てる場合より、もう少し範囲が広くても効果を発揮します。ストロンチウムによる治療は、非常に期待されている治療法で、今後普及してくるはずです。
痛みを上手に取れば治療効果は上がる
先ほども触れましたが、骨転移によるしびれ・麻痺など神経症状がある場合は、すぐに放射線か手術か、治療しなければなりません。それと同時にステロイドの投与が非常に重要です。いずれにしても、時間が経過するにしたがって、しびれ・麻痺が回復しなくなることがわかっており、早急の措置が不可欠です。そういう意味では、骨転移による神経症状には注意しておく必要があります。
治療法の最後に、鎮痛薬の話をしておきたいと思います。基本的に、鎮痛薬は上手に使う必要があります。骨に痛みがあるが、まだ、ホルモン療法は行っていないという場合に、鎮痛薬を使うケースがあります。しかし、最初からホルモン剤を使用すれば、非常に効果があり、鎮痛薬を使用する必要はないということを、日常茶飯事に経験していますから、初期の段階で鎮痛薬を使う必要はないと思います。
しかし、ホルモン療法を続けているにもかかわらず、痛みが少し出てきた場合には、最近はどんどん鎮痛薬を使っています。世界保健機関(WHO)による「がん疼痛治療法」(3段階除痛ラダー)に沿って、まず第1段階では非ステロイド系消炎鎮痛薬を使用します。それでも痛みが取れない場合は、非ステロイド系消炎鎮痛薬に弱い麻薬、弱オピオイドを上乗せすします。それでもダメなときには、非ステロイド系に強い麻薬、強オピオイドを上乗せすると、痛みはかなり取れます。
従来、麻薬を使うと早く悪くなるのではないかと言われていましたが、それはまったくのウソです。むしろ、痛みを上手に取ってあげたほうが治療効果が上がることが明らかにされています。
したがって、少なくとも経験のある医師は、痛みを取ることに関して非常に積極的で、早期の段階から鎮痛薬を使う方向に向かっているのが、最近の傾向です。
もちろん初期の段階では、ホルモン療法で大きな除痛効果が出ますから、鎮痛薬を使用することはありませんが、残念ながらホルモン療法の効果が薄れ、痛みが出てきた場合には、早めに非ステロイド系消炎鎮痛薬、弱オピオイド、強オピオイドといった鎮痛薬を使用したほうが、最終的に治療効果が出ることは間違いないところです。
鎮痛薬を使う場合の5つの原則
鎮痛薬を使用する場合、いくつかの原則があります。
第1は、できるだけ経口的に使用することです。そのほうが患者さんも飲みやすく便利です。第2は、投与時間を決めて規則正しく使用することです。間隔を短くしたり、不規則に使用するのは良くありません。また、時間を空けすぎると痛みが大きくなり、結果的に鎮痛薬を通常よりたくさん飲まなくてはならなくなります。第3は、除痛ラダーに沿って段階的に使用することです。
第4は、個々の患者さんに合った適切な量を使用することです。鎮痛薬によってどういう副作用が出るかは、よくわかっていますが、出てくる程度、状況には大きな個人差があります。したがって、患者さんの状況に応じた適量を使用する必要があり、その量がわかるまでに多少試行錯誤を繰り返す必要もあります。要するに、鎮痛薬の処方にはさじ加減が必要で、そのさじ加減には結構苦労することを知っておいていただきたいと思います。
さらに第5は、それだけでは対応できないケースもあり、ケース・バイ・ケースでさらにきめ細かな配慮が必要です。
いずれにしても、鎮痛薬の投与に関しては、昔よりかなり早い段階から行われており、がん治療において痛みを取ることが重視されるようになっています。ですから、痛みがある場合は、医師に遠慮なく、「早く痛みを取ってほしい」と訴えるほうがいいと思います。痛みが取れれば取れるだけ、治療効果は上がるわけですから。
- できる限り経口的に
- 投与時間を決めて規則正しく
- 疼痛ラダーに沿って段階的に
- 個々の患者さんに適切な量で
- その上でさらに細かい配慮を
(構成/本誌編集部)
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


