「前立腺がん市民フォーラム」 パネルディスカッション「進行がんでも、希望に生きる」再録 進行・再発しても、10年、20年の長期生存を目指して生きよう
ホルモン療法
PSAの変化に一喜一憂しない
赤座 三谷さんの例からもわかるように、ホルモン療法には高い効果がありますね。じっさい手術や放射線などの根治治療の後にこの治療を継続して、症状が安定しているという人が少なくありません。
患者さんからの質問にもホルモン療法に関するものが多いのですが、そのなかでももっとも多数を占めていたのが、この治療はいつまで続ければいいのか、あるいはいつまで継続できるのかというものです。
残念ながらがんがホルモン療法に抵抗性を獲得し、そのために治療の効き目がなくなることがあるのも事実です。そのため患者さんの中には、医師から、この治療は数年しか効果が持続しないといわれ、不安を感じている人もいるでしょう。その点について堀江先生にお聞きしたいと思います。
堀江 おっしゃるようにホルモン療法は非常に優れた治療法ですね。ただ、ひとことで前立腺がんといっても、人によってがんの大きさも違えば性質も違っています。そのことによってホルモン療法の効果にも個人差があり、この治療をどれだけ続ければいいのか、どれだけ続けられるのか一概にはいい切れません。そういうことから将来的には、ホルモン療法が効果を持たないときが訪れるかもしれない、ということをあらかじめ医師は患者さんにお伝えします。
しかし現在、この治療で症状が安定しているのであれば、あまり細かなPSAの変化などにとらわれず、おおらかに治療を続けていかれればと思います。あとにお話が出ると思いますが、内分泌療法の効果がなくなった後でも有効な薬剤が開発されています。
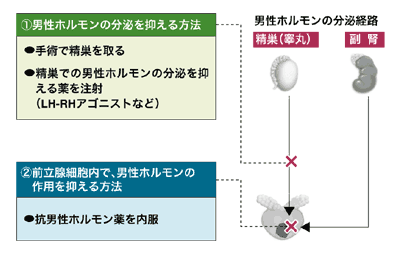
見直しが必要なホルモン療法限界説

ソフトな語り口で聴衆を魅了した赤座さん
赤座 ホルモン療法の限界についてはある種の思い込みがあるように思います。PSAが発見されたのは1940年代で、それまでは前立腺がんの80~90パーセントが進行がんでした。それで、その時代にホルモン療法について非常に有効な治療法だが、効果は2、3年しか持続しないという研究論文が海外で発表され、その研究者がノーベル賞を獲得したんですね。それでホルモン療法は数年が限界という考えが世界中に広がり、現在も同じように考えられているんです。
でも、その論文が発表されたときは、患者さんのほとんどが症状が重篤な進行がん患者さんですからね。発見時の前立腺がんの8割が早期がんで占められる現在とは、まったく状況は違っているんです。
じっさい転移はないけれどがんが前立腺をはみ出してしまっているステージ3の患者さんたちを対象にした私たちの臨床試験では、PSAが0.1にまで下がった場合、その後の7年間で患者さんのほとんどは、制がんされていて、前立腺がんで亡くなってもいないんです。
前立腺がんに対するホルモン療法の有効率は90パーセント以上といわれています。つまりステージ3というやや進行した状態であっても、ホルモン療法は、ほとんどの患者さんに対して有効に作用し続けているわけです。
さらに、これはまだ明確なエビデンス(科学的根拠)はありませんが、三谷さんのように間欠療法を用いるホルモン療法の効果の持続期間が、1.5倍、あるいは2倍にも延長できるというデータも出始めています。そうしたことを考えるとホルモン療法の限界についても見直す必要があるのではないでしょうか。ホルモン療法は一般にいわれているよりもずっと長く、継続することができるように思います。
男性ホルモンの低下から起こる副作用
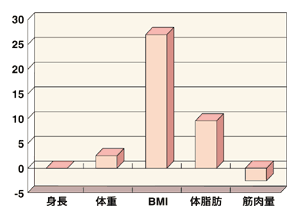
[ホルモン療法の副作用(うつや不安)]
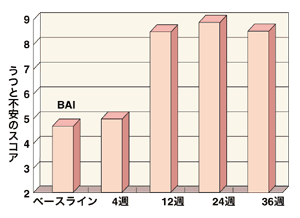
赤座 さて、こうしたホルモン療法についての質問で同じように多かったのが、副作用に関する疑問でした。
副作用がなければホルモン療法は、もっともっと素晴らしい治療法として進化を遂げられます。そこで製薬会社や私たち医療者は副作用をなくすために、どういう薬の可能性があるのか、治療戦略が考えられるのか精力的に研究を続けています。もっとも現時点では副作用を避けて通れないのも事実です。そこで塚本先生、この問題についてまず概略を整理していただけませんか。
塚本 当たり前のことですが、ホルモン療法とは男性ホルモンのレベルを急激に低下させるもので、そのことによってさまざまな副作用が現われます。
まず第1にあげられるのは、女性の更年期と同じ諸症状ですね。具体的にはほてりや動悸など。これらの症状には個人差があって、ごく軽微な人もいれば、残念ながら治療の中断を余儀なくされるケースもあります。
第2には短期的な副作用として勃起障害があげられます。これはどんな人にでも100パーセント現われます。
そして第3には長期的に及ぶ副作用として骨密度の低下によって生じる骨粗鬆症があります。これはホルモン療法の実施期間の長さに比例して、発症例も増加します。そこで骨への影響が懸念される場合は、骨粗鬆症治療薬のビスフォスフォネートを併用することになります。
また副作用については、最近になってそれらに加えて、ホルモン療法を行うことで心血管系の合併症も増えるのではないかという論文も出ています。この点についてもこれからは注意が必要ですね。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


