「前立腺がん市民フォーラム」 パネルディスカッション「進行がんでも、希望に生きる」再録 進行・再発しても、10年、20年の長期生存を目指して生きよう
抗アンドロゲン剤の中断、変更
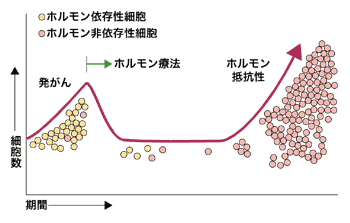
[間欠的アンドロゲン除去療法の考え方]
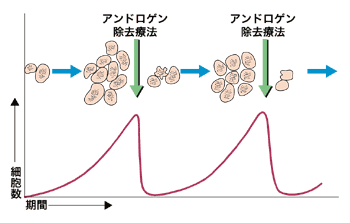
赤座 また話はホルモン療法に戻りますが、この治療を続けていると、とくに転移を有する進行がんでは多くの場合(すべてではない)、いつかは薬が効かなくなるときが訪れます。ホルモン抵抗性の発現、あるいは前立腺がんの再燃といわれる状況ですが、こうした場合の治療法についておたずねしたいと思います。繰り返しになるかもしれませんが、まず前立腺がんの再燃を判断するタイミングということからお話ください。
堀江 ホルモン療法を受けておられる患者さんは定期的にPSAの検査を受けておられますね。その数値が3回連続して上昇した場合、初めて上昇した時期に遡って、男性ホルモンの遮断療法に対して抵抗性が生じていると判断します。
では、そのときにどんな治療があるのか。まず考えられるのが、注射の薬はそのまま継続して、飲み薬の抗アンドロゲン剤を中断する、あるいは別の薬に変えるという手法です。時には抗アンドロゲン剤をやめるだけでも治療効果が現われることもあります。さらにPSAが上昇する場合には、ステロイド剤を用いることもあるし、また、より強力な抗がん剤を用いることも考えられます。
それ以外では、これからは塚本先生が話されていた抗がん剤に期待が持てるでしょうね。この薬は高齢の人たちが使いやすいことも大きな利点のひとつです。
塚本 おっしゃるとおりですね。付け加えれば骨転移がある場合には、赤座先生が話されていたビスフォスフォネートを利用すればいいでしょう。この薬には前立腺がんそのものの進行を遅らせるという報告もあります。ひとつ難しいのはステロイドホルモンの使い方ですね。これには微妙なさじ加減が必要でしょうね。
ホルモン療法単独の治療効果は?
赤座 手術や放射線治療など根治治療とホルモン療法を併用されている患者さんも少なくありません。この場合には、ホルモン療法にはどんな意味があるのでしょうか。
塚本 以前はあらかじめ3~6カ月程度、ホルモン療法を行ってから手術を行うことがよくありました。ホルモン療法でがんの勢いを弱めてから手術をしようということですが、残念ながら予想していたほどの効果はあがりませんでした。
最近ではPSAの再上昇を遅らせるために手術後に放射線照射が行われることもありますね。こちらは効果があったとする報告もありますが、まだまだデータは不十分です。ホルモン療法も含めて、術後の補助療法をどうするかということもこれからの検討課題ですね。
赤座 ホルモン療法単独で治療が行われていることも多いですね。質問を寄せてくれた76歳のK・Tさんのケースもそうで、01年6月に前立腺がんが見つかって以来、ホルモン療法単独の治療を受けておられ、PSAは測定限界以下の水準が続いています。それでいつまでこの治療を受けなければならないのか、ということをたずねておられます。いってみれば「嬉しい悩み」かもしれませんが、このことについてはどうお考えになりますか。
堀江 私のところでも、前立腺がんでがんが小さい場合、ホルモン療法でPSAがごく微小なレベルに抑えられているケースが少なくありませんし、そのなかには治療をやめても長期間、再発が起こっていないケースもあります。
比較的小さいがんであればホルモン療法だけでも前立腺がんを直すことは可能といえるでしょう。ただその場合には、定期的に検査を受けて、状態をチェックする必要があるでしょうね。
赤座 前立腺がんの患者さん向けのガイドラインを作成するときにも、このことはQ&Aで必ず記載します。それくらい患者さんにとっては気になる事柄で、われわれ治療者には重要だけれど判断が難しい問題ですね。
ただ、最近では海外の文献で、注射と経口タイプのホルモン剤の併用治療を6年以上続けた後、治療をやめても再発しないという報告も行われています。このあたりがひとつの目安になるのかもしれません。そうして治療を中断した後、PSAが上昇した場合に、三谷さんのようにまた治療を再開するという考え方もあるでしょうね。
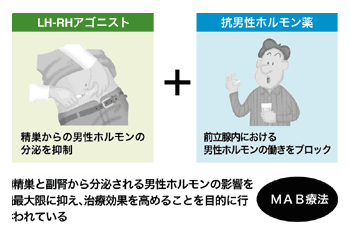
再燃がんの治療
これまでの抗がん剤になかった手応え
赤座 もっともじっさいには、もっとやっかいなのがホルモン療法が効果をもたらさなくなった場合、つまりがんが抵抗性を獲得して再燃してしまったケースですね。この場合でもがんの勢いを抑えるために治療の前提として、男性ホルモンを遮断する必要があるというのが現在の常識ですね。
ごく一部の人たちは意図的にがん細胞を活性化させて叩くという手法を主張していますが、現段階ではエビデンス(科学的根拠)がともなっていないし、やはりリスクが大きすぎると思います。そこで注目されているのが塚本先生が話されていたように近く承認が予定されているドセタキセルという抗がん剤の可能性ですが、この薬の使用によってじっさいにどの程度の効果が見込めるのでしょう。この抗がん剤についてもう少し詳しく話していただけますか。
塚本 海外では、ホルモン療法が効かなくなった重症患者を対象にして、この抗がん剤の臨床試験が行われていますが、重篤な患者さんばかりが対象になっていることもあってか、効果の持続期間はそう長くない。
しかし現実の臨床では、いろんな段階の患者さんが対象になりますから、それよりも効果は上がると考えられます。じっさいこの薬を用いた患者さんの70パーセントが1度は、PSAが低下しているという報告も行われているんです。当然、それだけ生命予後(余命)も延長される。この薬剤を使うことでがんが治るわけではありませんが、これまでの抗がん剤にはなかった手ごたえが感じられるのも事実です。
堀江 もちろんPSAが低下することが大事ですが、治療を受けることで、PSA値が上昇しないのであれば大きなメリットがありますね。副作用が比較的少ないこともこの薬のメリットだと思います。抗がん剤ですが、外来で投与を受けることができる薬ですね。
もっと迅速に薬の審査が行えるシステムを
赤座 この薬はすでに日本でも他のがん種では治療薬として承認されており、保険適用が認められていますね。もっとも前立腺がんに対しては、世界で効果が確認されているのにまだ承認されていない。
厚生労働省では患者さんや医療者の要望に応えて、優先審査を行っていますが、やはり遅すぎるように思います。先生方は研究目的でこの薬を使われているのでしょうが、一般の医療者から見ると、せっかくいい薬があるのに利用できないことにジレンマを感じざるを得ません。保険診療に関する制度的な問題もあるのでしょうが、その点についてはどうお考えですか。
塚本 保険診療と混合診療の問題ですね。現在は混合診療は認められておらず、未承認の抗がん剤は使えない。赤座先生が感じておられるジレンマも十分に理解できます。
ただ厚生労働省のいい分に一理あるのも事実でしょうね。混合診療を認めてしまうと、民間療法で用いられている実態のよくわからない薬も使われるようになり、医療現場が混乱をきたすことも考えられますからね。私個人としては現在のシステムと混合診療を認めるシステムとの中間点に落としどころがあるように思っていますが……。堀江先生はどうお考えですか。
堀江 そうですね。ただ今はインターネットの時代で、海外の臨床試験の実績なども簡単に調べられるようになっている。そんなことを考えるともっと迅速に審査が行えるシステムがあってもいいようにも思いますね。
赤座 いずれにせよ、この薬は原則的には未承認薬だから医療現場では使えません。もっともホルモン療法が効かなくなった場合は、患者さんのほうから「こんな薬があると聞いているのですが」と、医師に提案してみることも大切かもしれませんね。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


