傷が小さく、痛みと合併症のリスクが少ない手術 技術格差の大きな腹腔鏡下手術は熟達医を選べ
入院の期間が短縮、費用負担は少なく
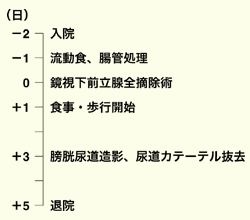
さらに腹腔鏡手術の大きなメリットは、出血量を最小限に抑えることができることと、腹腔内を膨らませる圧で出血を減らせることである。
また、内視鏡のカメラを前立腺のすぐ前まで挿入し、細部を拡大してモニター画面で見ながら作業できるので正確な操作ができる。
従来、前立腺がん手術では、術中に出血したときに輸血できるよう、あらかじめ患者本人の血液を採取して蓄えておく自己血貯血を行われていたが、最近はその必要がなくなりつつある。
「開腹手術を行っているときは、10~50パーセントで自己血輸血が行われていました。しかし、私自身の経験について言えば、今まで輸血が必要だったのは2例だけでした。自己血貯血は不必要なので行っていません。手術直前に貯血すれば貧血になることがあり、造血剤を使わなければならなくなります。そうなると血液の粘度が上がり深部静脈血栓症のリスクを高めてしまいます。
また、手術が終わった後、尿道にカテーテルを留置しますが、それを抜去するまでの期間が開腹手術は1週間くらい必要なのに対して腹腔鏡手術はだいたい3日です。入院期間も前者が約2週間なのに、後者はわずか5日くらいですみます。
診療報酬は開腹手術に比べ高いのですが、入院費が少なくてすむので、腹腔鏡手術のほうが医療費の総額が低くなってしまいます」
短期の比較で開腹術と同等以上の成績
従来、前立腺がんの腹腔鏡手術は、開腹手術よりも時間がかかり、これが患者に負担になるとされてきた。ところが、最近はこの点に関しても大きく事情が変わってきたようだ。
「最初は、手術は8~9時間といわれていたものが、現在ではどの病院でも3~4時間で終わっているでしょう。私の経験でいちばん速かった患者さんでは1時間40分くらいですが、平均では2~3時間以内で、当初の3分の1くらいの時間でできるようになっています。
たとえば、あまり手術に熟達していない若い医師が隣で開腹手術をするとしたら、まず私の腹腔鏡手術のほうが早く終わるでしょう」
腹腔鏡下前立腺摘除術は、1998年にフランスで始まった術式だ。したがって、世界でこの手術に対する15年、20年という長期経過での治療成績はまだ示されていない。ただ、手術の適応とされる前立腺内にがんが留まっている例に関しては、断端陽性率(切除した前立腺の切れ端にがんが残っている割合)やPSA(前立腺特異抗原)の再発率などで短期の成績を比較できる。それによると、世界的には開腹手術と腹腔鏡手術の差はないという。
「私たちの教室で最初の200例ぐらいまでのデータを集計したところ、開腹手術と腹腔鏡手術に有意差はないものの、腹腔鏡手術の成績のほうがいいことがわかりました。がんが皮膜まで到達しておらず、きちんと中に収まっていれば腹腔鏡手術で97パーセントの人が根治しています。
また、皮膜外のところまで細胞レベルでがんが浸潤している場合においても85パーセントが根治しています。腹腔鏡手術を始めた2000年から現在に至るまで、この治療を受けて手術で亡くなった方は1人もおりません。
PSA再発という観点に絞っても91.5パーセントが無再発です」
小線源療法と外照射療法などの選択肢も提供
前立腺がんの進行度は、大きくステージA・B・C・Dの4段階に分けられていて、手術の適応は早期がんといわれるA・Bに限られる。慶應病院ではこの病期の前立腺がんに対する治療法として、放射線の小線源療法(内側から前立腺を照射する療法)や外照射療法などの選択肢を提供している。
「マスコミでは、たくさんある前立腺がんの治療法に対して、患者さんがどれでも選べるかのように伝えていますが、やはりがんの状態によって最適な治療があります。ステージA・Bの患者さんで根治だけを考えた場合、慶應病院で言えば腹腔鏡手術がいちばんお勧めできる治療法です」
慶應病院では小線源療法の効果が期待できる適応の基準を設けている。がんの悪性度の目安となるグリソンスコアが6以下のものであること、がんが片側だけに寄っているもの、PSA値が10以下のものなどだ。
「ただし、60代以下の若い患者さんについては、やはり長期の成績を考え、どちらかというと手術をお勧めしています。放射線治療では長期間経過後、膀胱がんや直腸がんなどの2次がんが発生するリスクをも考えなければなりません。しかし、70代以降の患者さんで小線源療法の適応に入ればこちらがお勧めです」
希望を最大限かなえられる治療選択を
前立腺摘除術は、尿失禁や男性機能障害(性欲低下や勃起障害)などの合併症を招くことがある。小線源療法などの放射線治療との比較では、この点も検討材料となるだろう。
「私の経験では前立腺摘除術により1日尿パットを2枚以上使わなければならないような本格的尿失禁の発生は2.3パーセントです。手術直後に尿失禁があっても、長くて1年も経てば尿漏れはありません。
一方、小線源療法では、最初はむしろ排尿しにくくなり、逆に何年か続けていれば尿漏れが出てくることがあります。
また、小線源療法では、初めは男性機能は維持されますが、長い時間経過すると加齢の問題もあって障害が出ることが少なくありません。さらに多中心性発がんといって、生検では見つからなかった悪性のがんがあった場合に問題が起きるかもしれません。
医療者やマスコミは生存率やED(Erectile Dysfunction勃起障害)発生率でものを言いますが、患者さんにとっては、がんが治るかどうか、EDになるかどうかは、確率云々の問題ではないのです。すべて良いという治療法は残念ながらありません。ぜひ自分の希望を最大限にかなえられる治療を選択してください」
腹腔鏡下前立腺摘除術は、高度な手技が求められるので、術者や施設の数がきわめて限られている。そのため、慶應病院でも、この手術を受けるためには平均で1.5カ月から2カ月の予約待ちをしなければならないのが現状である。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


