進行別 がん標準治療 放射線治療、ホルモン療法の治療選択を考えよう
骨に転移しやすいがん
しかし、生検は前立腺に針を刺して数カ所から組織を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる検査です。通常は入院の上、麻酔をして行う検査で、できれば避けたいというのも人情です。グレーゾーンの人全員を検査すると、8割の人は無駄に生検を受けることになってしまいます。そこで、触診や経直腸式超音波検査の結果から総合的に判断したり、さらにPSAのタイプや前立腺の大きさとの比率など詳細な検討によって、対象をしぼり、生検を行うように工夫されています。
最近ではパワードプラーといって、血流をみる超音波検査によってがんの病巣に血流が流れ込んでいるような兆候があるかどうかをみて、生検の必要性を判断することも行われています。
こうした検査の結果、最終的には生検によってがんと確定した場合、次には治療方針を決定するため、がんのステージ(病期)を把握する検査が行われます。ここでは、CT、MRI、骨シンチグラフィなどが中心になります。
高橋さんによると「前立腺がんは、やがて前立腺の被膜を破って外に出て、周囲のリンパ節に転移していきます。また、骨に転移する率が極めて高いのが特徴」といいます。
CTやMRIは、このうち被膜の外にがんが出ているかどうか、近くのリンパ節に転移があるかどうかを見るのに有効です。骨シンチグラフィは、*放射性同位元素を投与して骨転移の有無をみる検査です。転移があるとその部分に放射性同位元素が集まり黒く写し出されます。さらに、レントゲンによる確認の検査も行われます。
また、PSA値によっても、およその進行度がわかります。「PSAは、腫瘍の体積に比例して高くなる」のだそうです。20を超えるとがんは前立腺をくるむ被膜を越えて外に出始めます。50になるとリンパ節転移、100近くになると骨に転移があってもおかしくない。1000を超えると確実に転移があるそうです。
*放射性同位元素=放射能をもつ物質で、原子量が異なるもの
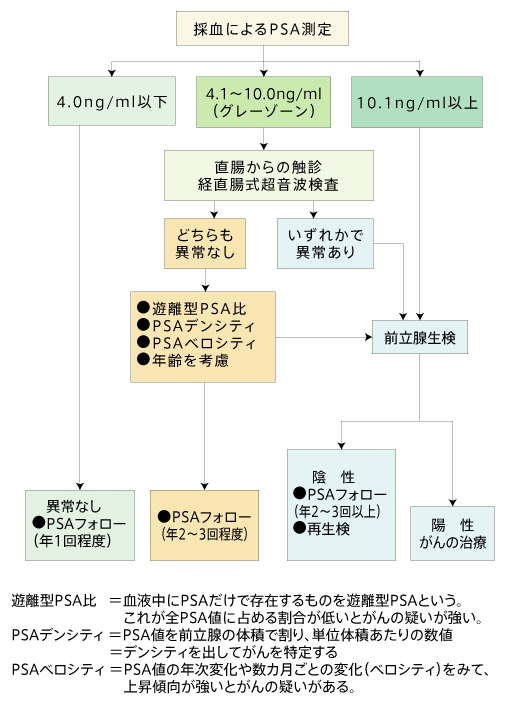
早期がんの治療・T1~T2
治療の対象になるのはT1bから
以上の検査によって、ステージ分類をしたのが下の表です。実際に治療の対象になるのは、このうちT1bからです。
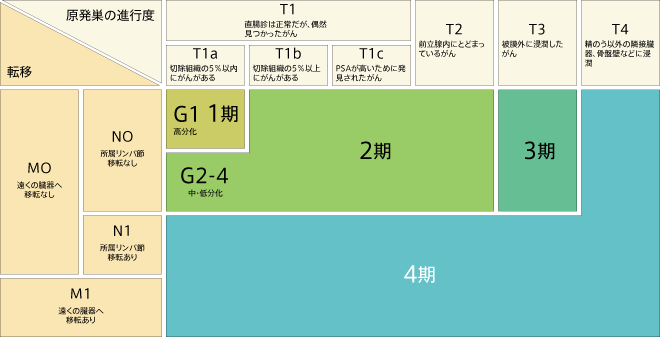
●T1
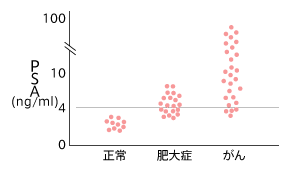
一般的に4ng/ml以下が正常値。4~10ng/mlはグレーゾーン。
10ng/ml以上だと約40%の人にがんが発見される。
T1aは、前立腺肥大の切除などで偶然みつかったがんで、CTや超音波検査でもがんは見えないけれど、切除した標本を顕微鏡で調べるとそのうち5パーセント以内にがんが見つかったという状態です。「この場合、基本的には無治療です。前立腺肥大の手術をしたときにがんはすでに取りきれてしまったと考えられるからです」と高橋さんは説明しています。
PSAで経過を観察し、この値が上昇すれば改めて治療を考えます。
がん細胞が5パーセントを超えていれば(T1b)「生検を受ければ見つかるはずのがん」なので、前立腺内にとどまるがんであることを確認した上で、T2に準じた治療になります。
PSA値が高くて生検でがんが発見された場合(T1c)は、必ずしも早期とは限らないので、あらためてステージ分類を行った上で治療方針が決められます。この中で「PSAが少し高くても高齢で生検でもわずかにがんが確認できる程度、しかも高分化型であれば、まれですが経過観察ということもある」そうです。
●T2
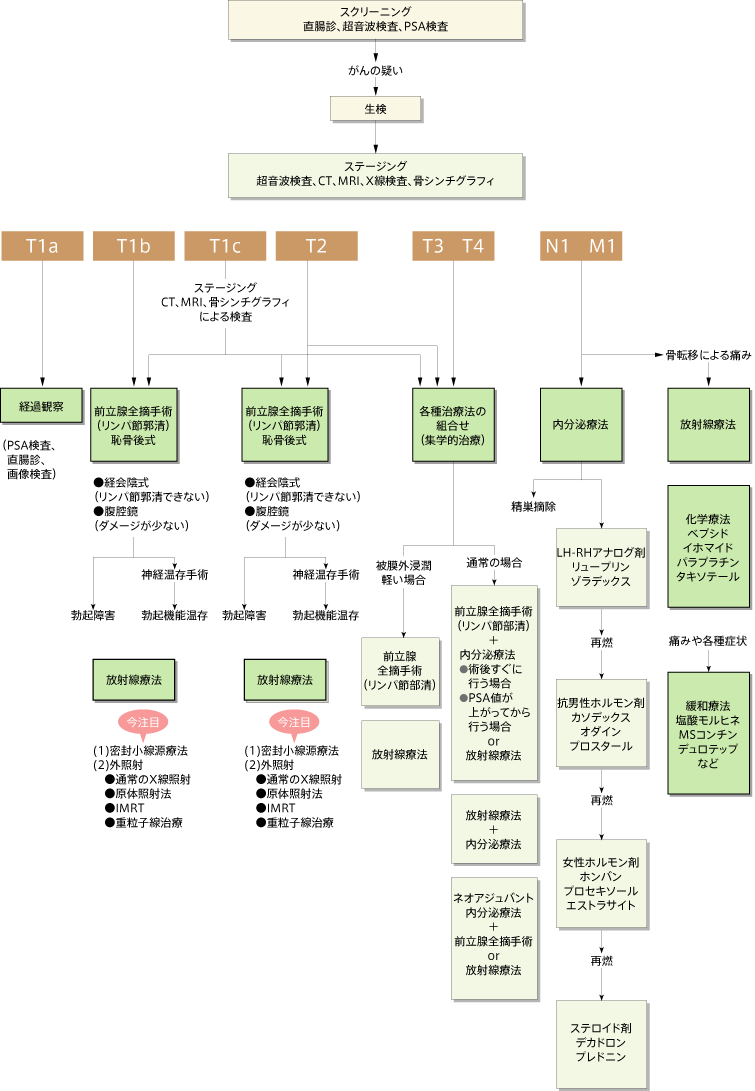
さて、早期がんは前立腺内にがんがとどまる段階です。T2までがこれに相当します。全摘手術によるT2の10年生存率は90パーセント以上。治る可能性が極めて高い段階です。この段階では、基本的には手術、あるいは放射線治療が選択肢になります。
「根治性の高さがすでに立証されているという点で、従来は前立腺全摘手術が中心でした。これに対して放射線治療は勃起障害、尿失禁などの合併症が少なくて、根治が期待できるのが長所。
アメリカでは、手術と密封小線源療法という放射線治療がほぼ半々の割合で行われています。去年、日本でも密封小線源療法が認可されたので、今年からは大きな選択肢となるはずです」と高橋さんは語っています。
体への負担が少ない腹腔鏡手術
●手術
これにもいろいろな手法がありますが、標準的に行われているのは、オヘソの下を縦に12~13センチ切開して前立腺を切除し、膀胱と切断した尿道をつなぐ方法です。このとき、同時に周囲のリンパ節も郭清します。この場合のリンパ節郭清は、治療より検査、つまりリンパ節転移の有無を調べる意味合いが大きいそうです。入院期間は2~3週間です。
この他、会陰部から前立腺を摘出する方法などもありますが、高橋さんによると、むしろ現在注目されているのは、腹腔鏡下手術だといいます。これは、腹部に5カ所ほど小さな切開を入れ、ここから腹腔鏡や手術器具を挿入して、前立腺を切除する方法です。
「開腹手術に比べて、体への負担が少ないのが大きな長所です。傷も小さく、痛みも少ないので入院期間も7日ほど。手術翌日には歩くことも水を飲むこともでき、その翌日には食事もできます」と高橋さん。
開腹手術の場合、縫合した尿道が治癒するまで2週間ほど尿道にカテーテル(細い管)が留置されますが、腹腔鏡下手術の場合はこれも4日ほどですむそうです。「腹腔鏡下手術の場合、5倍くらいに術野を拡大した視野で縫合するので、細かく縫うことが可能」だからです。したがって、後述する尿失禁が起こる率も非常に少ないそうです。
ただ、腹腔鏡下手術は手術を行う人の技術力の差が大きいのが現在の問題点です。つまり、うまい人とそうでない人の差が大きいのです。しかし、「万が一の場合、すみやかに開腹手術に移行すれば、命を失うようなことはありません」と高橋さんは語っています。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


