進行別 がん標準治療 放射線治療、ホルモン療法の治療選択を考えよう
LH-RHアナログ剤は精巣摘出と同等
そこで、現在よく行われているのが、LH-RHアナログという薬によって、精巣からの男性ホルモンの分泌をブロックする方法です。高橋さんによると「効果は両側精巣の摘出と同等」だそうです。
ステージT3~T4の場合は、リュープリン(一般名リュープロレリン)、あるいはゾラデックス(一般名ゴセレリン)というLH-RHアナログ剤を3カ月に1回の割合でずっと使い続けるのが基本です。前立腺がんは成長速度が遅いので、治療の効果は10年生存率、あるいは15年生存率で評価されています。補助療法としての長期的なデータがまだ十分ではないので、ずっと続けるのが基本になっているそうです。
T3で全摘手術に内分泌療法を併用する場合は、通常手術の直後から始めますが、最近放射線治療でもPSAが高くなってから内分泌療法を始めるより、直後から始めたほうが効果が高いことがわかってきたそうです。
高橋さんによると「リンパ節転移がなく、PSAもそれほど高くない場合は、手術に加えて放射線を併用する方法が効果をあげています。おそらく、被膜の外にパラパラと残ったがん細胞を放射線が叩いてくれるからでしょう。しかし、放射線治療は局所を狙い撃ちする治療法なので骨やリンパ節に微小な転移があった場合は、効果は期待できません。その場合は、全身的な効果を期待できる内分泌療法を併用するべき」と語っています。
こうした各種の治療法を組み合わせることで、T3(~T4)の段階であっても、「いいところでは、70パーセント以上の10年生存率が得られている」そうです。
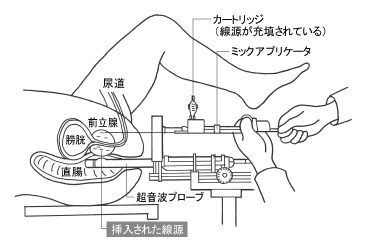
転移・再燃
内分泌療法が効果を発揮する
すでに、周囲のリンパ節や骨などに転移がある状態です。局所療法である手術や放射線治療では治療ができないので、この段階では内分泌療法が選択されます。「抗がん剤は、症状の緩和などに効果があ���ことはありますが、前立腺がんの場合延命効果は認められない」からです。
しかし、内分泌療法によってかなり長期間日常生活をふつうに送ることができます。
前述のように、男性ホルモンの働きをブロックする内分泌療法は、骨転移があるような人にも効果があり、腰痛や尿が出ないといった症状に苦しんでいた人でも、驚くほど元気になると言います。
ただし、内分泌療法によって、いったんは低下したPSA値も、2~3年で再び上昇してくることが多いのです。がんの再燃です。これは、がん細胞の中にも内分泌療法が効かないものがあり、これが増殖してくるという説、またがん細胞が男性ホルモンが不足した状態でも増殖できる能力を持つという二つの説があるそうです。しかし、再燃してもまだ手は残されています。
「内分泌療法の場合、第一選択薬はLH-RHアナログですが、これが効かなくなってもまだ副腎由来の男性ホルモンの分泌を阻止するものなど他の抗男性ホルモン剤があります。これを併用するとまた、PSAが下がって元気になります。これも効かなくなった場合は、エストロゲンという女性ホルモンでまたPSAを下げることができる」といいます。これで、半年から1年は元気な時間を伸ばすことができます。

前立腺がんは理由は不明だが骨に転移しやすい。
特に骨盤や腰椎に転移しやすいが、遠くの頸椎や肋骨にも転移する
PSAが上昇したらステロイド剤を
「それでもPSAが上昇したときには、ステロイド剤を是非試してください」と高橋さん。骨転移を起こして末期状態にあるような人でも、食事が食べられるようになる、モルヒネを使わないでも痛みをコントロールできるようになるなど、ムーンフェイス(満月様顔ぼう)というステロイド剤の副作用はあっても劇的に体調が良くなることがあるそうです。効果は、半年ぐらいですが、それでも大きな効果です。
このように、内分泌療法はがんが再燃してもいろいろな薬に切り換えていくことでリンパ節や他の臓器へ転移した状態でも3~5年間、元気に延命することができるのです。また、80歳以上の高齢者や他の病気で10年以上の余命を期待できないケースでは、体への負担が少ないという意味で内分泌療法が大きな選択肢になります。
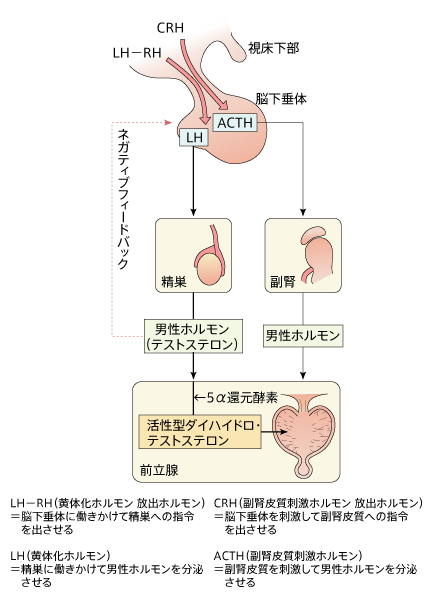
●副作用
内分泌療法は、男性ホルモンの働きを阻止するものです。したがって、通常全例に勃起障害が起こります。性欲も低下し、乳房が女性のように膨らむこともあります。
そして、急激に男性ホルモンの量が低下するので、女性の更年期障害と同じように、のぼせやほてり、発汗、不眠、うつ傾向などの症状が一時的に起こる人もいます。閉経後の女性同様、高脂血症や骨密度の低下などが起こることもあるので、注意が必要です。
うつが続くときには、選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRI)などの、副作用の少ない抗うつ剤で、またイライラや不眠で悩まされる場合は、抗不安剤や睡眠薬で症状が改善されるそうです。
生検
組織や臓器の一部を採取して、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる検査です。がんであるかどうかは、最終的に生検によって判断されます。
前立腺がんの場合は、直腸に探子を挿入して、前立腺の様子を超音波でモニターしながら、前立腺の組織を採取します。実際には、ピストルのような道具で細い針を前立腺に刺して、組織を採取します。針は長さ15~20ミリ、太さ1ミリほどのものです。問題は、どこから採取すれば、がんを見落とすことがないかです。
基本的には、6カ所生検といって前立腺の左右に各3本ずつ、計6カ所から組織を採取するのが標準的です。しかし、最近ではさらに精度を向上させるため、8~12本の針をがんが発生しやすい部分に刺すことが多くなっているそうです。生検は、腰椎麻酔か軽い全身麻酔で行われることが多く、15~20分ほどで終わるそうです。
期待余命と治療法の選択
前立腺がんの場合、非常に進行がゆっくりしていることが多いので、年齢によっても治療の選択肢が変わってきます。前立腺全摘手術によって根治を目指すのは、一般的に*期待余命が10年を超える場合です。つまり、10年以上寿命があると予測される場合は、手術によるリスクよりも得るところのほうが大きいと考えられるわけです。日本人男性の平均余命から考えると、75歳前後がその境目になります。この年齢で重い糖尿病や心筋梗塞などがある場合は、リスクのほうが大きくなると考え、通常全摘手術は勧められません。
全摘手術を行わない場合、内分泌療法が大きな手段になりますが、密封小線源療法などは治療による負担が少ないので、高齢の人でも行うことができます。
*期待余命=あと何年生きられるかという年数
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


