渡辺亨チームが医療サポートする:前立腺がん編
たくさんある前立腺がん治療法の中から、納得して選択する
赤倉功一郎さんのお話
*1 前立腺がんの治療法の選択

超音波を駆使してがんを焼く治療光景
前立腺がんの治療は、従来、70歳以下でがんが前立腺内にとどまる場合は、手術(前立腺全摘除術)が第一選択となっていましたが、最近は、1期、2期の早期の患者さんの治療は、本人の希望により、体外放射線治療、ホルモン療法、組織内小線源療法、高密度焦点式超音波療法といった選択肢などが出てきました。また、前立腺がんは一般に進行が遅く、早期から進行がんになって命が危ない状態になるまでに10年かかると言われるので、70歳以上で小さくておとなしいがんの場合は、無治療での経過観察も選択肢となっています。
2004年、ニューヨーク前立腺研究所の研究により、早期前立腺がんの予後(生存率)は前立腺全摘除術、体外放射線治療、小線源療法のいずれにおいても、統計学的に差がないことがわかりました。
前立腺がんの3期で転移がない場合は、ホルモン療法に放射線を組み合わせる治療を行い、それより進行した症例にはホルモン療法が採用されます。
| 治療法 | 内容 | 費用 | 保険の適用 |
|---|---|---|---|
| 開腹手術療法 (前立腺全摘除術) | 2期まで適応。勃起障害(ED)は性機能温存手術をして30%、しないと80~90%。尿漏れは5~10%、入院2~4週間。5年後のがん消失率は80%程度。 | 31万6000円 | 保険診療 |
| 腹腔鏡下手術療法 | ED、尿漏れとも開腹手術よりやや劣る。入院1~2週間。 | 80~100万円 | 高度先進医療 (手術のみ自費。 あとは保険適用) |
| 体外放射線治療 | 1~2期と、3期まで適応になることがある。ED30%程度。尿漏れは少ない。膀胱炎や直腸出血が起きることもある。入院不要だが毎日連続で約1月半の治療が必要。5年後のがん消失率は80%程度。 | 200~250万円 | 保険診療も可 |
| IMRT (強度変調放射線治療) | コンピュータの計算により前立腺に集中して体外から放射線照射ができる。結果的に周辺の臓器への線量を軽減でき、合併症を少なくできる。 | 200~250万円 | 保険診療 |
| 組織内小線源療法 | 2期まで適応。放射性物質のイリジウムを密封した小さな針を前立腺の中に埋め込む手法。EDは10%程度。尿漏れはほとんどない。 | 250万円 | 保険診療 |
| 重粒子線治療 | 2期まで適応。従来の放射線治療より強いエネルギーでがんを集中的にたたけるので、効果を強くでき、一方で副作用を弱くできる。重粒子線照射の治療は、独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院などで受けることができる。 | 314万円 | 高度先進医療 |
| 高密度焦点式 超音波療法 | 2期まで適応。直腸に挿入したプローブから、前立腺に強力な超音波が焦点を結ぶように照射して、80~98℃に加熱、がんを凝固、壊死させる。東海大学付属八王子病院など、全国10数カ所の施設で実施。EDは30%程度。尿漏れはほとんどない。無出血。入院は2~4日。 | 80~100万円 | 自由診療 |
| ホルモン療法 | 前立腺がんは男性ホルモンの影響を受けて増殖するので、男性ホルモンがつくられる過程を抑えたり、前立腺に作用しないようにするもの。以前は男性ホルモンが多くつくられる精巣自体を手術で摘除する方法がよく行われていたが、男性ホルモンを作る刺激をもたらすホルモン(LH-RH)を抑えるLH-RHアゴニストという薬や、男性ホルモンを抑える作用がある女性ホルモンや抗男性ホルモン剤が登場した。最近ではLH-RHアゴニスト単独あるいは抗アンドロゲン剤との併用が主流。この治療法は当初有効でも、年単位で時間がたつと治療に抵抗して増殖するがん細胞が発生してくる。EDは90~100%出る。尿漏れはない。 | 月6~10万円 前後 | 保険診療 |
*2 前立腺全摘除術の適応
前立腺がんの患者さんに行われる外科手術を、前立腺全摘除術といい、最も根治性が高い治療法と考えられています。2期までの早期のがんに適用され、3期のがんについて手術適応かどうかは議論されているところです。
この手術では前立腺、精嚢を切除し、膀胱と尿道をつなぎます。さらに前立腺肥大症などの良性腫瘍と異なり、所属リンパ節の郭清を行わなければなりません。そのため、出血も多く、付近の神経組織の温存も図らねばならないので、高度な技術も要求されます。この手術の合併症としては、尿失禁と性機能障害(ED)が主なものです。そのため全身状態や年齢(70~75歳が上限とされる)を考慮して手術の適応が決められます。
尿失禁は、以前の手術ではよくみられましたが、最近では日常生活に支障をきたすようなものは稀になっています。性機能障害、勃起不全はほぼ必発といえますが、早期に限っては性機能に関係する神経を傷つけずに摘出する方法もあります。
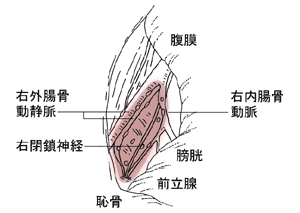
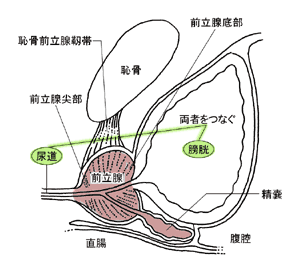
*3 術前ホルモン療法の意味
手術や放射線治療の前にホルモン療法を行うことをネオアジュバンド療法といいます。このうち、放射線治療のネオアジュバンド療法については、臨床試験で予後を改善する効果があることがわかっていて、これを採用することがほぼ常識となっています。一方、手術に伴うネオアジュバンド療法は予後を改善するのかどうかについてはまだわかっていません。ただ85パーセント以上の例で腫瘍を小さくする効果はあるので、この効果をねらって行う施設もあるようです。さらに、手術前の病期診断では、がんの広がりを正確に把握することができず、手術したら意外に病巣が広がっているということがわかる場合もあるので、「念のためにがんを叩く処置をしておこう」という考え方もあります。生検から手術までは時間を置くことも多く、この間がんが進行しないようにしようという考え方もあります。
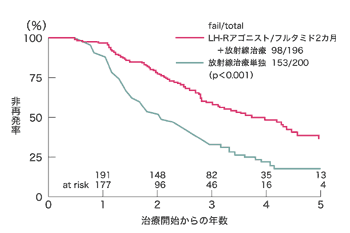
*4 ホルモン療法の副作用
ホルモン剤の副作用として、ED(勃起障害)などの男性機能障害はほぼ必発です。さらに更年期障害と同じように発汗、ほてり、関節痛などが現れがちです。また、プロスタール(一般名酢酸クロルマジノン)は女性化やむくみなど、カソデックス(一般名ビカルタミド)は乳房に痛みを覚えたり腫れたりし、オダイン(一般名フルタミド)は肝機能障害や下痢というふうに、薬剤によって、それぞれ異なった障害が現れることがあります。
*5 自己血貯血法
前立腺の前面 には多数の静脈があって、手術では1000ミリリットル以上の出血する場合があるので、輸血の準備が必要です。ところが、輸血ではウイルス感染や免疫反応などの危険性が多少あります。そこでそれを避ける方法として、あらかじめ自分の血液を採血・貯蔵しておき、手術の際に体に戻す自己血貯血法という方法を行うことがあります。
普通は手術の2~4週間前くらいに一度400ミリリットルを採血し、手術時の1週間前くらいにもう一度採血し、2回分を貯血します。
*6 性機能温存法
前立腺がんの手術による後遺症で最も多いのが、性機能の障害です。前立腺のすぐ近くに勃起を支配する神経があり、以前の手術ではこの神経を傷つけてしまっていたため、90パーセント以上がEDになっていました。これに対して、80年代に神経を温存し、性機能を保つ手術法が開発されており、日本の開腹手術でも腹腔鏡手術でもだんだんこの手術法を採用するようになっています。これにより半分が勃起機能を保てるようになってきました。また、神経を切除しなければならない場合、性機能の温存のために足から神経を取って移植する「神経再建手術」が取り入れられる場合もあります。
ただし、温存手術をしても、どうしても数割の人は性機能が戻りません。
また、温存術は出血が多くなりがちで、がん細胞が遺残するリスクも高くなってしまいます。もちろんどうしても術者の力量によって、成績は左右されます。
同じカテゴリーの最新記事
- 放射性医薬品を使って診断と治療を行う最新医学 前立腺がん・神経内分泌腫瘍のセラノスティクス
- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん
- 日本発〝触覚〟のある手術支援ロボットが登場 前立腺がんで初の手術、広がる可能性
- 大規模追跡調査で10年生存率90%の好成績 前立腺がんの小線源療法の現在
- ADT+タキソテール+ザイティガ併用療法が有効! ホルモン感受性前立腺がんの生存期間を延ばした新しい薬物療法
- ホルモン療法が効かなくなった前立腺がん 転移のない去勢抵抗性前立腺がんに副作用の軽い新薬ニュベクオ
- 1回の照射線量を増やし、回数を減らす治療は今後標準治療に 前立腺がんへの超寡分割照射治療の可能性
- 低栄養が独立した予後因子に-ホルモン未治療転移性前立腺がん 積極的治療を考慮する上で有用となる
- 未治療転移性前立腺がんの治療の現状を検証 去勢抵抗性後の治療方針で全生存期間に有意差認めず


