失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
骨転移でもキャンサーボードは必要ですか?
私自身は、骨転移の治療においては、とても重要だと思っています。キャンサーボードはもともと手術、放射線療法、薬物療法などに関わる専門医や医療スタッフが集まり、1人のがん患者さんの症状や状態、治療方針などについて議論し、情報共有するカンファレンス(会議)のことです。
しかし、骨転移はより多くの専門的医療者が関わる必要があるので、骨転移においてキャンサーボードの必要性はより高いことがわかると思います。
ガイドラインにも、「キャンサーボードや院内骨転移登録は骨転移診療に有用か?」というクエスチョンが記載されています。この推奨度は「弱い」ですが、それはこのテーマで臨床試験などが行われていないためです。
しかし、キャンサーボードに関して5つの論文が検討され、緩和ケアの患者さんが整形外科を受診した割合をキャンサーボードの設置前後で比較し、前の55%に対し、後は100%だった例などが紹介されています。この研究では整形外科の受診によってがん性疼痛とがん以外の疼痛が識別され、不必要な麻薬投与による副作用が軽減されたこと、骨転移の手術が2倍以上に増え、骨折や麻痺に対する早期介入事例が増えたこと、歩行能力が維持され、自宅療養可能な患者さんが増えたことなども報告されています。
そして、骨転移のあるがん患者さんがQOLを維持して、治療を継続するためにもキャンサーボードや院内骨転移登録は有用であり、現時点でエビデンスレベルは低いものの推奨できる取り組みと思われる、と結論づけています。
ネックは病院に骨転移診療に必要なすべてのスタッフが揃っているとは限らないことです。しかし、コロナ禍で、リモートによるキャンサーボードも現実的になりました。議論の結果、手術が必要な患者さんを外科専門医がいる病院に一時的に転院させ、治療が終わったらまた地元病院に戻る、といったことも今後行われていくのではないかと思います。そうした仕組み作りに向けても私たちも検討を始めています。実際に、改訂2版もコロナ禍のため、リモート会議を駆使して作成しました。
リモート診療は国も推奨しているので、将来的にはそこに組み込まれ、「ガイドラインには書かれているけれど、うちはスタッフが少ないから骨転移治療は無理」という事態は減ってくるのではないかと期待しています。慢性期は地元で治療できるのです。
患者さんがガイドラインを上手に活かすた��には?
ガイドラインを発刊したのは、現状では十分知られていない骨転移診療について、医療者に情報共有してほしかったためですが、患者さんにも情報を共有し、利用していただきたいという思いがありました。
ガイドラインは現時点で、エビデンスのある標準治療をまとめたものです。「これだけは最低限やらないとだめでしょう」ということが書かれています。患者さんは、それを知ることで、自分は標準治療を受けているのか理解できると思います。
患者さんの側から「この治療を受けることはできませんか?」と医療者に投げかけることで、標準的な骨転移の医療を受けることにつながります。患者さんから言ってもらうと医療者は動きやすいですから。
たとえば、あなたの大腿骨には骨転移があり、手術を受けて動けるようになりたいと思っているのに、「骨折の危険性があるから安静にしてください」といわれたとします。ガイドラインには「病的骨折や切迫骨折のリスクのある四肢長管骨(大腿骨や上腕骨など手足の長い骨)の骨転移に手術は有効か?」という問いが載っており、推奨度は「強い」になっています。もちろん、手術にはリスクもあり、整形外科医が不可と判断することはあるでしょうが、ガイドラインに載っている治療ということで、他科の医師ではなく、整形外科医に検討してもらうとよいでしょう。
ただ、ガイドラインは医療者向けで、専門用語も多く、患者さんには読みにくいと思いますが、骨転移の治療を理解するためには読んでほしいと思います。そこで、私たちも読みやすいガイドを提供したいと、現在、患者さん向けのガイド作成を計画しています。これは現在、当院で配布している「かんたん、わかりやすい骨転移診療ガイド」という小冊子ですが、これを元に考えています。
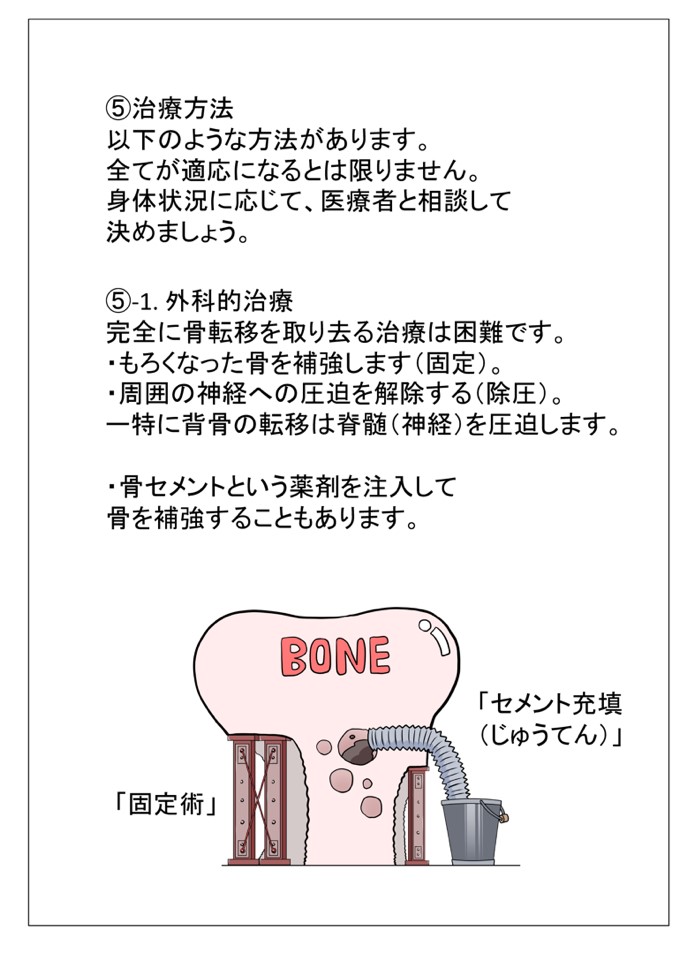
骨転移の患者さんは全国で20万人とも言われていますが、実際の骨転移患者数は正確にわかっていません。対象患者数がわからないと、ガイドラインを出した後に、それによって、どれだけ治療成績がよくなったか評価できません。そのためには「がん登録」が重要ですが、現在はどこに転移があるかまでは登録を行なっていないため、転移部位のがん登録なども進めていく必要があると思います。
はじめにお話ししたように、他臓器に遠隔転移があれば、骨に潜在的に転移していている可能性があり、疼痛などの症状があると、かなり進行している場合もあります。骨転移は早期発見、早期治療により予後が変わると思われますので、まだ症状の出ていない潜在的骨転移をどう見分けて治療するかは今後の課題です。
骨転移の治療は、使えるリソースを最大限活用することが重要です。そうした治療によって運動機能の維持が得られ、患者さんが医療の恩恵を十分享受できるように、医療者は常に学習し、多職種と連携して治療を行うために、ガイドラインを使ってほしいと思います。
そして、進行がんで骨転移があって、日常生活が極端に制限されていても、医療者の英知と技術を結集して、運動機能を維持・回復させて、日常生活を取り戻したり、社会復帰が可能になってほしいと願っています。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


