転移・再発とは、体の中で何が起こっているのかを知るために これだけは知っておこう!再発・転移の基礎知識と考え方
局所・領域再発は完治可能
がんが目に見える形で転移・再発巣として現れた場合、治療の考え方は最初の治療とは大きく異なると、吉田さんは語っています。
「基本的に、初回のがん治療は完治を目指した治療です。しかし、再発の仕方やがんの種類にもよりますが、一般的には遠隔臓器に再発したがんは、延命と緩和が治療目標になります」。
再発と一口にいっても、局所再発、領域再発、遠隔再発(全身再発)という3つの形があり、それによって治療の方針も違ってきます。
局所再発
原発巣のがんを治療した部位に、またがんが発生することです。これは、初回治療で残存していたがん細胞が大きくなって再発したものです。たとえば、乳がんに乳房温存手術を行った後に、温存した乳房内に再発すれば局所再発です。局所再発ならば、乳房切除術をするなど、再度手術をして完治することも可能です。
領域再発
原発巣近くのリンパ節に転移再発したがんです。これも局所再発の1つに数えられることもあります。乳がんならば、同じ側の脇の下のリンパ節に再発したがんは領域再発で、再度手術で完治できる場合もあります。
遠隔再発(全身再発)
がんがリンパや血液の流れに乗って、原発巣と離れた臓器に再発するのが、遠隔再発です。この段階になると、完治を目指した治療は難しくなります。
このように、局所再発ならば根治を目指すことも場合によっては可能です。「再度、手術ができるがんは、乳がんなど基本的にゆっくり成長するがん」だといいます。
しかし、遠隔再発となると、全身にがんが広がっていると考えられるので、摘出してもまた別の部位に再発が起こります。吉田さんによると「大腸がんの肝転移や肺転移のように、例外的ながんもありますが、基本的には遠隔臓器への転移再発がんに対して、根治を目指した手術が行われることは稀です」。
大腸がんが肝臓に転移した場合、再発したがんが3個以下など一定の条件にあえば、がんの摘出手術で、30~40パーセントの5年生存率を期待できるそうです。といっても、この大腸がんの肝転移が例外的なケース。卵巣がんの場合は、手術でがんの量をできるだけ減らしてから、抗がん剤による化学療法を行ったほうが延命効果が期待できますが、このような「減量手術」の適応も限られています。
つらい副作用に耐えないで
このように、遠隔再発が起きた場合には、根治を目指した治療ができることは少なく、基本的に抗がん剤など全身療法を行って、延命を目指すことになります。
「副作用が許容範囲で、QOL(生活の質)を保ちながら、がんと共存することが目標です。死がちらついて苦しいことはよくわかりますが、治療のゴールをはっきりと見据えることがまずは大切。それによって、安らかな生を得ることもできるのです」と吉田さんは語っています。
副作用は我慢しないで、薬を減らしたり、変えることが必要です。また、副作用のでにくい薬もあるといいます。
「治療の現場では、死を直視することができないために、大した効果もないのに、つらい副作用に耐えて抗がん剤が使われているケースが決して少なくありません」と吉田さんは嘆いています。
ここ数10年の間に、新しい抗がん剤や分子レベルでがんを攻撃する分子標的治療薬が登場し、再発後のがん治療は著しい進歩をとげています。
たとえば、大腸がんの場合、ベストサポーティブケア(抗がん剤を使わず、緩和治療のみ)では、生存期間の中央値は半年から1年です。しかし、FOLFOXやFOLFIRIという抗ガン剤の組み合わせに、分子標的治療薬のアバスチンやアービタックスを上乗せすると、最大で30カ月近くまで生存期間が伸びると報告されているそうです。
乳がんでも、抗がん剤とホルモン療法、ハーセプチンという分子標的治療薬を組み合わせることで、再発しても5年、10年と生存する人がどんどん増えています。
延命治療と緩和医療の両立を
ただ、治療法を考えるときには「薬が“効く”ということの意味に注意してほしい」と吉田さんは指摘します。患者さんや家族は、医師が「効く」といえば、がんが治るか、少なくとも延命効果があると思いがちです。しかし、実際にはがんが消えたり、縮小するという意味で、これは必ずしも治癒や延命を意味するとはいえないのです。
「抗がん剤治療を受けるときには、ベストサポーティブケアと比べてどうなのか、新たな薬剤の場合は、従来の再発治療に使われてきた薬と比べてどうなのか、その意味とデータを理解して選択してほしい」と吉田さんは勧めています。
そして、延命のためにも重要なのが痛みの緩和です。痛みがあると寿命も短くなるといいます。そして、痛みの95パーセント以上は治療で抑えられるというのです。
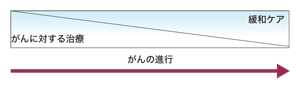
「日本では、延命効果が期待できなくなったら、緩和医療に入るという考え方が主流ですが、これは間違いです。最後まで抗がん剤による延命を図りながら、心のケアを含めて、がんによって生じた心身の苦痛を緩和するのが、現代的な考え方です」と吉田さんは強調します。
延命治療と緩和医療は両立して行われるべきもので、そうあってこそ、生活の質を保ちながら1日でも長く生きることができるのです。
再発治療に標準治療はないといいます。「どんな治療を選ぶかは、患者さんの人生観しだい。刻々と変わる状況を把握し、情報を収拾しながら主治医と相談して、自分が納得する治療を受けてください。一方で、人生の時間は有限であることを再認識することにより“より善く生きること”を実践してほしい」と吉田さんは語っています。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


