ビスホスホネート投与による顎骨骨髄炎・骨壊死は、早期発見・早期治療で治療できる可能性 骨転移治療中に口に異常を感じたら早めに主治医に相談を
ビスホスホネートが骨転移の標準治療
渡邉さんが話すビスホスホネートは、現在骨転移に対する標準治療として用いられるようになっている。この薬は骨の中に入り、がん細胞から骨を溶かすように指令を出された破骨細胞がこの薬を食べると死滅してしまい、骨に穴を作ることができない。つまり、がん細胞は骨の中に入り込めなくなるのだ。こうしたメカニズムにより、溶かされた骨が自然に再生して骨折の危険や痛みが解消する。
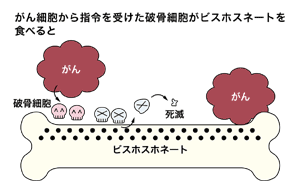
ビスホスホネートには、経口薬と注射薬がある。骨転移の治療薬としては注射薬であるアレディア(一般名パミドロン酸二ナトリウム)とゾメタ(一般名ゾレドロン酸水和物)が用いられている。乳がんの骨転移にのみ適応のあるアレディアに比べ、ゾメタは固形がんの骨転移、骨髄腫の骨病変への使用が認められており、100倍から1000倍も骨が溶けるのを抑制する力が強く、効果も強力であるとされ、骨転移治療の標準治療薬となりつつある。
ところが、海外でこれらビスホスホネートにより顎骨壊死という対応に苦慮する副作用が起こるという報告が、03年頃から目立つようになった。大田洋二郎さんは早くからこの情報に目を向けていたわけである。


抗生物質の服用で顎骨壊死は治療できる
静岡がんセンターで発見された顎骨壊死の1症例目の患者さんに対しては、炎症部分を取り除く処置が行われるとともに、抗生物質の投与が行われた。手術から10カ月を経過し、ニキビ様のできものも見られない。この間ゾメタの治療は中断せず続けてきた。大田さんによれば、ほかの5つの症例も含めて、「顎骨骨髄炎から骨壊死の進行���抑えきれている状況」という。
「顎骨骨髄炎は治りにくい病態と考えられがちですが、我々は『早期に対応すれば拡大を防ぐことができる』という実感を得ています。すでに日本ではビスホスホネートは相当使われるようになっていますが、がん専門医にはぜひ早期のうちに骨髄炎症状を見つけて治療に導いてほしいですね」
静岡がんセンターの口腔外科では各科に、ビスホスホネートの治療を受けている患者さんに対して「3カ月に1回は、口の中の状態を聞いて」とチェックを依頼している。そして、「異常が見つかったら口腔外科を紹介するように」と呼びかけている。
「顎骨骨髄炎・骨壊死のような症状に対してこれまでは、『炎症の症状、痛み、腫れが強い状態になったら治療する』という場合が多かったと思います。慢性化していると痛み、腫れは強くなく、症状は膿が少しずつと出るといった状態が長期間続くので、積極的に抗生物質を使わなかったのです。これに対して当院では、感染症科のドクターが『骨髄炎は治しにくい病態』という認識から早期かつ適切な期間の抗生物質投与を呼びかけています」
顎骨壊死の治療に特別な抗生物質を用いるわけではない。ペニシリン系のサワシリン(一般名アモキシシリン水和物)、オーグメンチン(一般名アモキシリン・クラブラン酸)やリンコマイシン系といわれるダラシン(一般名クリンダマイシン)を静岡がんセンターでは投与している。症例によって有効な薬の種類が異なるので、反応を見ながら使い分けている。
「アメリカの歯科医師会が作ったガイドラインでは、顎骨壊死に対する抗生物質の投与期間を『14日投与』というふうに書いてあります。
当院は抗生物質を6~8週間しっかり投与して腐骨をあわせて除去していく治療方針です。もちろんこれが1番よい治療法だとわかっているわけではありませんが、現在の6例というわずかな経験に関してはこれで良好な経過を得ています」
| 内服処方例 | 薬剤名(商品名) | 投与量(1回) | 投与間隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | アモキシシリン(サワシリン) | 500mg(2カプセル) | 1日3回 |
| 2 | アモキシシリン・クラブラン酸 (オーグメンチン) | 500mg(2錠) | 1日3回 |
| 嘔気が強い場合にはアモキシシリン250mg(1カプセル)+アモキシシリン・クラブラン酸250mg(1錠)を1日3回とすれば、嘔気がおさまる場合あり | |||
| 3 | クリンダマイシン(ダラシン) | 150mg(1カプセル) | 1日4回(6時間毎) |
大曲 貴夫(『がん患者の感染症診察マニュアル』南山堂)より 改変引用
口の中に異常を感じたら、早めに専門医に相談を
「アメリカでは歯槽骨が露出し始めた時点で顎骨壊死と診断することになっています。私たちはその前に歯茎に膿が溜まる状態を骨髄炎が始まる状態と考えています。
口の中に痛みがあったり、ニキビ様のできものができたり、へんな味が出たという訴えに気をつけるように医師にお願いしています。また、患者さんもそうした自覚症状があったらぜひ早く主治医に申告してください。内科の先生は口の中や歯茎をしっかり診ることにあまり慣れていないので、歯科医、口腔外科の先生と連携することが大切です」(大田さん)
なぜビスホスホネートの投与で顎骨壊死が起こるか、またなぜ顎の骨だけが壊死するのかははっきりとわかっていない。だから、予防法もわからない。ただ、これまでに公表されたきちんとした臨床研究から、いちばんの誘発因子はビスホスホネート投与中に抜歯などの歯科的治療を受けることであることがわかっている。そのため、ビスホスホネートの治療を始める場合は、事前に歯の治療をしておくことが必要と考えられる。
「顎骨壊死に関しては、まだ十分なデータがないので、わからないことだらけで不安が多いのが実情です。まず私たちの取り組みの中から顎骨壊死の予防・治療の糸口を見いだすことができれば、と考えています」
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


