再発・胃がん/大腸がんの治療 最初に正しい治療を受けることが再発予防になる
再発がんでも打つ手はある
がんが再発した場合、完全に治すことはなかなかできません。しかし、だからといって、打つ手がないということではないのです。たとえ完全に治すことができなくても、延命のための治療もあれば、症状を取り除いたり、QOL(生活の質)を上げたりするための治療もあります。結果的に患者さんががんで死亡したとしても、生存期間が延びたり、症状を取り除いて質の高い生活が送れたりすれば、それは治療する意味があるからです。
完全に治すことができない場合には、生存期間を延ばすために、抗がん剤治療や放射線治療がよく行われます。進行胃がんの場合であれば、数カ月という単位での延命効果が期待できます。
合併症を取り除くことも重要です。がんから出血して大変な場合や、消化管に狭窄が起きているような場合には、それを抑える治療が行われます。がんを治すことにはつながらなくても、症状を取り除くことには意味があります。痛みを抑えることも同様です。
食事を口から食べられなくなった人には、チューブ栄養が行われます。それによって、外出することも可能になります。
痛みがなく、栄養がしっかりとれていて、動くことができれば、人間は生きていくことができます。そのような意志がある限り、きちんとケアするべきなのです。
精神的なケアは、日本ではまだ遅れています。ただ、腫瘍精神科という分野ができ、精神的ケアも行われるようになってきました。
再発がんの完治は不可能とは言いきれない
再発がんを完全に治すことは困難ですが、まったく不可能なのかというと、そうでもありません。たとえば、私自身は、30数年にわたってがんの治療を行ってきましたが、絶望的な再発がんが完全に治ったと思える人が、これまでに3人いました。確率としては、再発がんは治らないということになりますが、例外があるのも現実なのです。
肝転移や肺転移を簡単にあきらめることはありません。たとえば、大腸がんの肝転移は、取り除いていくことで、かなりよい成績が得られることがあります。
-大腸がん肝転移例の5年生存率-
| グレード | 肝転移を切除 | 非切除例 |
|---|---|---|
| A | 52.9% | 14.3% |
| B | 29.6% | 7.7% |
| C | 10.4% | 0% |
表2は、大腸がん肝転移の患者さんに対して、肝転移を切除した場合と、切除しなかった場合の5年生存率を比較したものです。グレードは転移の個数によって分けています。
転移の数が多くないグレードAの場合、切除すれば5年生存率は52.9パーセントです。半数以上が生存していることになります。それに対して、切除しなかった場合には、14.3パーセントになってしまいます。
転移の数が多いグレードCの場合には、切除しなければ5年生存率は0パーセント。切除すれば、10.4パーセントになります。
胃がんの場合、大腸がんほどの成績は上がりませんが、1個だけの転移であれば、それを取り除くことで50パーセント程度の5年生存を得ることができます。
脳転移に関しては、できている部位によっては手術できますし、ガンマナイフという特殊な放射線治療で小さくすることもできます。こうした治療によって、いい状態で生きることは可能です。
リンパ節転移はあちこちに現れるので、治療は一般的に難しいとされています。ただし、手術のときにあまり進んでいなかった場合や、転移している個数が1個か2個の場合には、まれに治るケースもあります。
転移再発の治療にはチーム医療が望ましい
がんの転移再発は、治療が非常に難しいので、1人の医師が担当するのではなく、チームで進めるのが理想的です。
癌研有明病院では、消化器がんの患者さんは、消化器センター全体で患者さんを引き受ける形にしています。そのシステムをまとめたのが図6です。
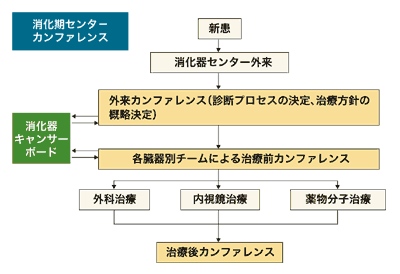
たとえば、転移再発の患者さんが受診したとき、まず外科の医師が話をし、次に内科の医師が話をし、その次に放射線科の医師が話をして、患者さんだけに治療方針を決めてもらう、というようなことはしません。医師同士でよく話し合う必要があるので、患者さんを中心としたカンファレンスを開き、診断プロセスや治療方針の概略について、決定を下すようにしているのです。
治療を行っていても、たとえば、まだ放射線治療を続けたほうがいいのか、それとも緩和医療にしたほうがいいのか、というようなことで患者さんはもちろん担当医でも迷うことはあります。そのような場合、担当医は1人で悩むのではなく、キャンサーボードという集まりに相談することができます。そこでは、たとえば大腸がんの肺転移なら、呼吸器科の医師にも出席してもらい、コメントをもらうこともあります。そのようにして結論を出すのです。
転移再発の治療は、チームで進めなければなかなかうまくいきません。いろいろな科に回すのがいいように思われていますが、それは無責任なだけだと考えています。チーム医療が広く行われるようになることを期待しています。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


