がんの転移はここまで解明されている がん転移のメカニズムとは、打開策はあるのか
血管だけでなくリンパ管も作られる
体の中には、血管以外に、リンパ管というチューブ状構造が存在する。リンパ管の主な役割は2つある。1つは血管からにじみ出た液体を回収して血管に戻すこと、もう1つは体の免疫系を形成することだ。
リンパ管を流れているのがリンパ液で、がん細胞はリンパ液によって運ばれ、転移することもある。血行性転移が、新たに血管が作られることで起こるように、リンパ行性転移も、新たなリンパ管ができることで起こるようになる。
「リンパ管を作るのにも、VEGFが利用されています。ただ、血管を作る因子とは違っていて、VEGFファミリーの中でも、VEGF-CやVEGF-Dが、リンパ管新生を起こすための基本的なたんぱく質とされています」
がん細胞がこれらの因子を出すようになると、がんの周囲にリンパ管が増えてくる。そこにがん細胞がもぐり込んで、リンパ行性転移が起こりやすくなるのだ。
「ただ、リンパ行性転移が、この機構だけで起きているのかといえば、そうではありません。はっきりしたことはわかっていませんが、たぶん20種類も30種類ものいろいろなメカニズムが関係して、リンパ行性転移が起きているのでしょう」
もし、リンパ行性転移がVEGF-CやVEGF-Dだけで起きているのなら、このたんぱく質の働きを抑えるだけで、リンパ行性転移を防ぐことが可能なはずだ。しかし、現実には、そう簡単にはいかないだろう。なかなか一筋縄ではいかないのだ。
転移するがん細胞ははがれて移動する
血管やリンパ管ができたとしても、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗るためには、がんのかたまりからはがれ、血管やリンパ管のところまで動いて行く必要がある。かたまりを作っているがん細胞が、そこからはがれ落ち、移動するというのだから不思議だ。
どのようにしてはがれるのかを理解するためには、がん細胞同士がどのようにくっついているのかを理解する必要がある。
「がん細胞がくっついているのにも、いくつかのたんぱく質が関係しています。カドヘリンやカテニンなどの細胞接着分子がそれで、細胞と細胞が手をつなぐようにして接着し合っています。チャックが締まった状態と考えてもいいでしょう」
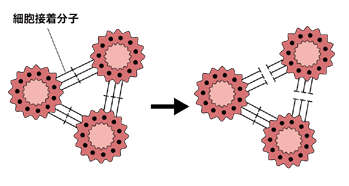
がん細胞間では接着分子が手の働きをしている。
これが離れるとがん細胞は移動できる
このように細胞がくっつき合ってかたまりを作っているのだが、このままでは転移できない。転移するためには、かたまりからはがれることが前提となるわけだ。
「がん細胞は、細胞接着分子の発現を、適当に上げたり下げたりすることができます。はがれるときには、これらのたんぱく質の発現を低下させます。すると、しっかり締まっていたチャックが緩んで、細胞がはがれやすくなるのです」
もっとも、がん細胞がかたまりからはがれるメカニズムも、これだけということではない。もっと変わったはがれ方をするがん細胞があることも知られている。
「たとえば、大腸がんは上皮細胞からできますが、この細胞は、自らの顔を変えることで、がんのかたまりから切り離されるという方法をとります。上皮らしさを持っていると、上皮細胞と引き付け合い、はがれることができません。ところが、一時的に上皮らしさを消してしまい、他の細胞のような顔に変わると、上皮細胞との間のチャックが切れてしまいます。がん細胞が仮面をつけて別の細胞に変装し、仲間との間の接着を切られるように仕向けるわけです」
かたまりからはがれた後、がん細胞が転移するためには、血管やリンパ管にたどり着く必要がある。がん細胞は、どうやってそこまで移動するのだろうか。
「細胞が動くための装置が細胞の中にあります。アクチンファイバーという繊維状の物質ですが、これを壊したり、再構築したりして動きます。
わかりやすく説明すると、後ろのほうのアクチンファイバーを壊して、前のほうに持ってきて再構築するわけです。これを繰り返すことで、少しずつ進んでいきます」
がん細胞はむやみに動くわけではない。アンテナとして働く受容体を細胞から出し、それで増殖因子の濃度の高い方向に移動したりするのだ。
浸潤しやすいがんは転移しやすい
がん細胞が移動するためには、正常な細胞の間を通り抜けて行かなければならない。正常な組織では、細胞間には間質という網の目状のたんぱく質があり、普通ならそこを細胞が通過するのは難しい。しかし、がん細胞はMMP(マトリックス・メタロ・プロテアーゼ)などのたんぱく質分解酵素を分泌し、自らの進むべき進路を開いて行くのだという。
「このたんぱく質分解酵素は、正常細胞も低いレベルで持っています。がん細胞はそれを高いレベルで使用し、進路に穴を開けたり、かたまりが大きくなっていくとき、周囲にスペースを空けるために使ったりしています」
こうして、かたまりからはがれたがん細胞は、自ら動いて血管やリンパ管にたどり着く。そして、血管やリンパ管に入り込み、転移の旅のスタートを切ることになるのだ。
ここで浸潤についても説明しておく必要があるだろう。浸潤とは、がんのかたまりからはがれたがん細胞が、単独で、あるいは仲間を引き連れて、じりじりとかたまりの外側に広がっていく現象のことをいう。かたまりにつながりつつ、周辺の組織にしみ込むように広がっていく。
したがって、転移と浸潤はまったく異なる現象ではない。まず浸潤が起こり、浸潤した先に血管やリンパ管があれば、がん細胞が血管やリンパ管に入って転移が起きる可能性が高くなる。
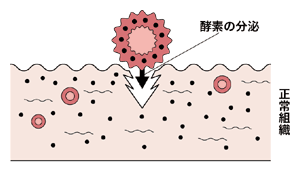
たんぱく質分解酵素を分泌し、
正常組織に穴をあけて進路を開いて進んで行く
「良性腫瘍は浸潤を起こしません。だから転移もしません。逆に、悪性腫瘍は浸潤するので、転移も起こるわけです。つまり、浸潤も転移と並んで悪性の重要なファクターといえます」
当然のことだが、浸潤しやすいがんは、転移しやすい傾向にある。膵臓がんは非常に早い時期から転移が起こるが、浸潤する性質もかなり強く、かたまりが大きくなくても、周囲の組織にばらばらと広がっていく。
「浸潤するがんは治療も困難です。たとえば、脳腫瘍の中でもとくに悪性度が高いといわれる神経膠芽腫は、病気の末期には周囲の脳にどんどん浸潤してしまいます。手術する場合、浸潤した細胞が少しでも残れば再発しますが、だからといって、脳を大きく切除することもできません。それでお手上げになってしまうわけです」
脳腫瘍でも、良性の脳腫瘍ならば、浸潤しないし、転移も起こさない。手術するとしても、周囲の脳を傷つけないように腫瘍を取り除けば完治する。怖いのは、浸潤したり、転移したりする性質を持っていることなのだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


