がんの転移はここまで解明されている がん転移のメカニズムとは、打開策はあるのか
転移しやすい臓器はほぼ決まっている
血液もリンパ液も全身を循環している。がん細胞が血液やリンパ液によって運ばれるなら、全身のどこに転移が起きてもおかしくないはずだ。ところが、転移が起きやすい部位はほぼ決まっている。
リンパ行性転移の場合、一般に、がんの近くのリンパ節に転移しやすい。これは、リンパ液がリンパ節に集められるからで、どのがん種でも同じだ。
血行性転移の場合には、転移が起きやすい部位は、肝臓、肺、脳、骨など、ある程度決まっている。肝臓へは胃がんや大腸がんからの転移が多く、脳へは肺がんからの転移が多く、肺へは乳がん、脳腫瘍などからの転移が多い。
このように、転移しやすい部位が決まっているのには、いくつかの理由が考えられる。
「1つには、血流のルートの問題があります。たとえば、大腸がんが肝臓に転移しやすいのは、大腸から肝臓に向かう門脈という血管のルートがあるからです。消化管で吸収した栄養を肝臓に運ぶ血管ですが、大腸がんのがん細胞も、この血流に乗って肝臓まで運ばれているわけです」
また、肝臓には細い血管が網の目のように広がっていくので、がん細胞がひっかかりやすいこともある。肺への転移が多いのも、やはり毛細血管が多いことがあげられる。
| 1. 肺には毛細血管が多い |
| 2. 肺がん細胞からのシグナル (サイトカインなどの情報伝達物質) を受け取る 肺自身が、がん転移をしやすい環境をつくる |
さらに、肺への転移では、がん細胞からの信号を受け取った肺が、自ら転移しやすい環境を作ってしまうことも、動物を使った実験で明らかになっている。マウスの皮下にがんを移植したところ、転移が起こる前から、肺の細胞がMMPという消化酵素を出し、間質の消化が始まることがわかったのだ。がんが大きくなると、がん細胞からサイトカインなどの情報伝達物質が放出され、それを肺の細胞が受け取ることで、こうした準備が始まるらしい。
「肺の間質が消化されることで、がんの出店を出しやすい環境が整うことになります。肺への転移が起こりやすい理由の1つとして、このようなメカニズムも関係しています」
骨に転移するがん細胞は、骨にある破骨細胞を利用しているという。骨には、カルシウムを沈着させる造骨細胞と、カルシウムを溶け出させる破骨細胞があり、両方が常に働いている。破骨細胞を活性化させる力を持ったがん細胞は、破骨細胞の働きで骨に穴を作り、そこに転移するのだ。
転移を防ぐ薬の開発が現在も進められている
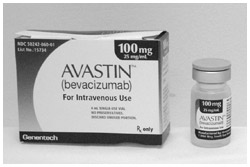
血管新生阻害剤の第1号として発売されているアバスチン
がんがどのように転移するのかがわかってくると、転移を防ぐ方法もわかってくる。実際、そのようにして新しい薬の開発が進められてきた。
まず治療薬の標的となったのは、血管新生を介して増殖や転移を促進させる血管新生因子とその受容体である。血管新生が起こらないようにすれば、増殖も抑えられるし、血行性転移も抑えられるはず、と考えられたわけだ。
血管新生因子はいくつかあるが、選ばれたのはVEGF-Aだった。血管を作るための最も重要な因子ということで、これに対する中和抗体の研究が進められたのだ。こうして作られたのが、現在、アバスチンの商品名で知られている抗ヒトVEGF-A中和抗体である。
アバスチンは、2003年に大腸がんの患者を対象にした第3相臨床試験が行われている。それによって、従来の標準化学療法では15.6カ月だった生存期間が、標準化学療法とアバスチンの併用では、20.3カ月に延びることが明らかになったのだ。
アメリカでは04年2月にアバスチンを新しいタイプの抗がん剤として承認。日本でも07年4月に承認され、大腸がんの治療薬として使用できるようになっている。臨床試験では、乳がんや肺がん(腺がん)に対しても、治療効果を発揮することが明らかになっているという。
もう1つはVEGFなどの受容体を標的とした治療薬である。
「VEGFの受容体のほうを抑えても、理論的には同様の効果が出るはずです。そこで、受容体を標的とした治療薬の研究も進められてきました。こうして、VEGF受容体のシグナルであるチロシンキナーゼの働きを止める薬が開発されたのです。さらに、チロシンキナーゼ以外のいくつかのシグナルの働きも抑えるので、この薬はマルチ阻害薬と呼ばれています。FDA(米国食品医薬品局)はマルチ阻害薬を腎臓がんの治療薬として承認しています」
現在のところ、転移のメカニズムに関連する因子を標的とした治療薬で、がんの治療薬として実用化されているのは、この2種類の薬だけだ(日本で承認されているのは大腸がんに対するアバスチンのみ)。しかし、他にも研究は進められている。
たとえば、リンパ管新生に関わっているVEGF-Cとその受容体のシステムを抑えることができれば、リンパ行性転移がある程度抑えられるのではないかと考えられ、研究が進められているそうだ。
「動物実験でははっきりした効果が現れていますが、最終的には、実際に患者さんに使ってみて、生存期間をどれだけ延ばせるのかを調べなければなりません。その臨床試験では、アバスチンほどうまくいかない可能性があります。リンパ管新生を防ぐ薬ですから、すでに転移している進行がんの患者さんに使った場合、アバスチンほどの効果が現れない可能性はありますからね」
困難な点はいろいろあるのだろうが、この分野での研究が急速に進められていることは間違いない。転移のメカニズムは、ようやく一部が明らかになっただけで、まだわかっていないこともたくさん残されている。今後も、新しい標的に対する治療薬が開発されることになるのだろう。
「がんの転移を完全に抑えるということは無理かもしれません。しかし、転移を抑える方法は、これからも開発されてくるはずです。ゴールを10としたら、現在はまだやっと3に到達した程度。まだまだやることは残されています」
この分野で最先端の研究を進める渋谷さんは、こう語っている。今後の進歩に期待したいところだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


