「より多く」から「より適量」へ発想の転換をして、延命をはかった療法の最新成果 がん休眠療法10年の軌跡
がんが消えても、治療の手を緩めてはいけない
金沢大学医学部付属病院腫瘍外科の外来でこの休眠療法に則った治療を受けた2つのケースを紹介しよう。
Aさん(58歳)は、乳がんと診断され、がん専門病院で手術を受けた。手術の前後に数多くの種類の抗がん剤治療を受け、さらに、放射線治療も受けた。しかし、残念ながら2002年に肝臓と骨に転移が発見された。同外来を受診した際は、ほとんどの抗がん剤は使いきり、残ったのはタキソール(一般名パクリタキセル)のみという状況だった。
そこで、高橋さんは、タキソールの毎週投与をAさんの適量(個別化最大継続可能量)を求めながら行うことにした。通常、タキソールの毎週投与では体表面積(体重と身長から決定)当たり80ミリグラムである。しかし、安全な40ミリグラムからスタートした。
毎週外来で、Aさんの血液検査の内容や自覚症状、下痢などの状態をチェックして、次の投与量を決めた。副作用がなければ10ミリグラム増加し、グレード1ならそのままの量を投与し、グレード2以上なら10ミリグラム減少という投与を繰り返した。5週でAさんの適量(副作用のグレードが1となる量)は60ミリグラムであることがわかり、その後は60ミリグラムを継続して投与した。副作用はグレード0と1を繰り返し、2となることはなかった。副作用が軽微な状態で、タキソールによる治療を続けたところ、5センチの大きさの肝転移はゆっくりと2センチまで縮小し、安定した。
しかし、治療をスタートしてから1年が経過した頃から再びがんの増殖がみられた。ちょうどその頃、新薬のゼローダ(一般名カペシタビン)が使えるようになったため、薬剤をゼローダに変更した。その結果、再びがんの増殖が止まり、肝転移はさらに縮小し、ついに画像上消滅した。現在、この状態が1年以上続いている。
ただし、術前から高かった腫瘍マーカーが正常値に戻っていないこともあり、油断はできない。ゼローダは経口剤のため、1カ月に1回、外来通院するだけで治療が続けられる。Aさんの外来通院の負担は軽くなり、日常生活でも時間的な余裕が持てるようになったという。
「画像上で完全消滅していても、がんという病気は手ごわいです。CTでは5ミリまでの腫瘍しか指摘できません。5ミリでもがん細胞は1億個以上あります。Aさんが現在の状態を少しでも長く維持していくためには、治療の手を緩めず、今後も続けていく必要があります。また、ゼローダのような経口剤は『ゆっくりと長く』という休眠療法のコンセプトには最適です。胃がんや大腸がんで使用されている経口剤のTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシル)も休眠療法に最適です。ほかの抗がん剤でも経口剤の開発が進んでいます。その実現が待たれます」と高橋さんは語る。
余命半年の患者が抗がん剤の副作用もなく2年延命
Bさん(64歳)は2002年初めに、肺転移を伴う膵臓がんと診断された。休眠療法を紹介したNHK番組「ためしてガッテン」を見て、神奈川県の茅ヶ崎市から金沢市の同外来まで訪れた。自宅まで遠いとのことから、当初は入院してジェムザール(一般名ゲムシタビン)の毎週投与の治療を受けた。Aさんと同様の方法で、Bさんの適量を求めた。
通常、ジェムザールの毎週投与では体表面積当たり1000ミリグラムだが、500ミリからスタートした。副作用がなければ100ミリグラム増加し、グレード1ならそのままの量を投与し、グレード2以上なら100ミリグラム減少という調整を5週間繰り返した。その結果、Bさんの適量は500ミリグラムとわかった。この量での副作用はまったくないため、外来治療に切り替えた。
Aさんは茅ヶ崎市の自宅から同外来まで2週間に1回、通院を続けた。1人で飛行機に乗って来ることが多く、兼六園近くのホテルに宿泊していた。ときには奥さんと自家用車に乗って来ることもあった。治療後、夫婦2人で能登半島一周旅行も楽しまれた。治療を始めて1年経過後、残念ながらジェムザールは効かなくなってきた。そこで、次の抗がん剤を同様な方法で投与を始めたところ、さらに1年以上生存期間が延長できた。
「Bさんは、余命半年という状態でした。2つの抗がん剤を適量に用いて、2年延命できました。休眠療法は糖尿病や高血圧の治療と同じように薬を使い続けますが、抗がん剤の場合、薬が効かなくなってくることがほとんどです。これを薬剤耐性と呼びます。このことを考えると、Bさんの場合、有効な抗がん剤が5つあれば5年の延命が得られた可能性があります。
しかし、現在の抗がん剤治療では最初の抗がん剤をたくさん投与するため、副作用が残り、次の抗がん剤に変更するまでにかなり時間(休薬期間)がかかります。あるデータによると、胃がんでは次の抗がん剤に変更できたのはわずか30パーセントです。最初から適量の抗がん剤治療を行えば、次の抗がん剤にチェンジすることが容易に可能です。テーラード・ドーズ化学療法にはそうした利点もあります」(高橋さん)
Aさん、Bさんとも通常の量(最大耐用量)の半分からスタートしたように、テーラード・ドーズ化学療法では通常の半分(または3分の2)から始めて、グレードを指標に増量・減量を繰り返し、適量を調整していく。使用する抗がん剤の種類はがんの臓器別に決まっている標準的治療法をもとに行う。適量は、血中濃度、遺伝子、代謝酵素などが関係していると予測される。これらの相関関係については、現在、研究と検討が行われ、本法のより科学的な確立が目指されている。
副作用は低く生存期間が長いことが証明された
グレードを指標に適量を調整するテーラード・ドーズ化学療法について、高橋さんは次にように述べる。
「この療法は、落ちこぼれが少ないという特徴があります。教育現場で言えば、習熟度別授業のようなものです。個人の習熟度に合わせた授業を行って、クラス全体の生徒1人ひとりがそれなりに成績を上げて、結果的にクラスの平均点を上げます」(高橋さん)
今年2月、高橋さんは、米国膵臓学会雑誌「PANCREAS」に転移性膵臓がんに対するテーラード・ドーズ化学療法の治療成績を発表した。転移性膵臓がん患者18名を対象に治療を行った結果、奏効率(完全寛解=CRと部分寛解=PR以上)は3例で16.7パーセント、100人治療したらその51番目の人が死亡した時期(生存期間中央値。MST)は9.5カ月、6カ月生存率83.3パーセント、1年生存率27.8パーセント、2年生存率16.7パーセントだった。
この治療成績を世界の報告例(最大耐用量による従来の抗がん剤治療)と比較したのが図1である。テーラード・ドーズ化学療法は、有効率、生存期間中央値、1年生存率ともに世界の報告を上回っている。
「私の治療法のほうが副作用はずっと低いにもかかわらず、生存期間の延長が認められます。その理由はもちろん長く継続しているためです」と高橋さん。
| 報告書 | 患者数 | 奏効率(%) | 生存期間 中央値(月) | 1年生存率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Casper et al | 44 | 9.0 | 5.6 | 23 |
| Carmichael et al | 34 | 6.3 | 報告なし | 報告なし |
| Rothenberg et al | 63 | 10.5 | 3.8 | 4 |
| Crino et al | 24 | 15.0 | 報告なし | 報告なし |
| Burris et al | 63 | 5.4 | 5.6 | 18 |
| Stornolo et al | 3023 | 12.0 | 4.8 | 15 |
| Rosemurgy et al | 103 | 報告なし | 5.5 | 報告なし |
| Moore et al | 139 | 報告なし | 6.4 | 5 |
| Humblet et al | 214 | 7.0 | 4.0 | 14 |
| 高橋ら | 18 | 16.7 | 9.5 | 27.8 |
| 患者個々の適量 | 1年生存率 | CA19-9が50% 以下になった割合 |
|---|---|---|
| 300~500 mg/m2 | 3/10(30.0%) | 7/9(77.8%) |
| 600~700 mg/m2 | 2/8(25.0%) | 5/7(71.4%) |
[テーラード・ドーズ化学療法での投与量の求め方]
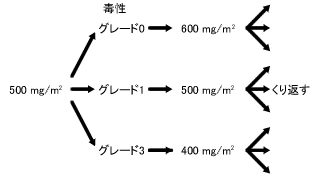
例えば500mg/m2を投与した患者の副作用がグレード0の場合は次回は抗がん剤を増量し、グレード1ならば量は変えず、グレード2なら減量、というように投与量を変更しこれを繰り返していく
もう1つ、個々の抗がん剤の適量が多くても少なくてもその効果に差がないことも明らかになった。1年生存率は300~500ミリグラムが30パーセント、600~700ミリグラムが25パーセントでほとんど変わらない。腫瘍マーカーが50パーセント以下になった症例数も前者は77.8パーセント、後者は71.4パーセントでほぼ同じ(図2参照)。
「これは、今回の量が個々で適量であることを示す、非常に重要なデータです」と高橋さんは言う。
高橋さんががん休眠療法を発表してから10年目。現在、国内では進行再発胃がんに対する世界初のテーラード・ドーズ化学療法が実施されている。
抗がん剤としてトポテシンまたはカンプト(一般名塩酸イリノテカン)とTS-1の併用した療法と、TS-1単独療法の効果を比較する無作為化比較試験である。予定参加患者数は合計90例。がん集学的治療研究財団が統括して全国48施設が参加。
また、転移性膵臓がんや切除不能再発大腸がん、転移性乳がんに対しても臨床試験が行われている。さらに、再発子宮がん、再発卵巣がん、転移性前立腺がんに対しても、臨床試験を計画・準備中だ。
欧米では「抗がん剤の低用量を頻回に投与することで血管新生の抑制効果がある」という研究発表によって、抗がん剤の量に関する臨床研究も始められたという。高橋さんが発表した「がん休眠療法」はテーラード・ドーズ化学療法という新しい治療法を備えて、第2ステージを迎えた。高橋さんは「休眠療法に基づいたテーラード・ドーズ化学療法をエビデンス(科学的根拠)にすることが私の使命です」と語る。
同じカテゴリーの最新記事
- 失われた機能とQOLを取り戻すため骨転移は積極的に治療を! 『骨転移診療ガイドライン』改訂版は多職種の参加で作成
- 脇腹の痛みが続いたら要注意! 増えている骨転移
- がんによる急変には、患者は何を心得ておくべきなのか オンコロジック・エマージェンシー対策
- 高齢者機能評価ツールを用いて判断できる可能性 進行再発がんの薬物治療〝進め方と止めどき〟
- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた
- 「骨を守る」対策も並行して行う乳がん骨転移治療 日常活動動作や生活の質を維持するために
- 再発・転移特集/再発・転移の基礎知識
- いかに手術に持ち込めるかがカギ 大腸がんの肝転移治療戦略 肝切除においては肝臓の機能、容積の確保が重要
- 分子標的薬、サイバーナイフなど肺がん脳転移しても治療法はある 分子標的薬や放射線療法の進化で治療が大きく進歩


