ハーセプチンによって、QOLを保ったまま過ごせる人も 個別化治療の幕開け!胃がんにも分子標的薬が登場
がんの大きさが変わらぬまま1~2年過ごせる人も
検査結果で、HER2陽性となった場合には、前述のゼローダ、シスプラチン、ハーセプチンの3剤併用療法を、3週間1コースとして6コース行います(図4)。
治療は、我が国の場合、最初の7~10日程度は入院治療を行い、その後、外来での治療を続けます。
治療の流れとしては、患者さんはまず1日目にハーセプチンとシスプラチンの点滴投与を受け、それと同時にゼローダを2週間、毎日飲み続けます。その後1週間治療を休みます。
これを6コース繰り返し、6コース終了後は、病状を見ながら3週間ごとにハーセプチン単独、あるいはゼローダを併用して、治療を続けます。
「治療がうまくいけば、6コースの治療のあとハーセプチンを投与するだけで、がんの大きさが変わらずに、副作用もなくQOL(生活の質)を保ちながら過ごすこともできた患者さんが、ToGA試験中にもいらっしゃいました。なかには、1~2年、がんが小さいまま過ごすことができている人もいるので、患者さんにとっては大きな意味を持つと思います」
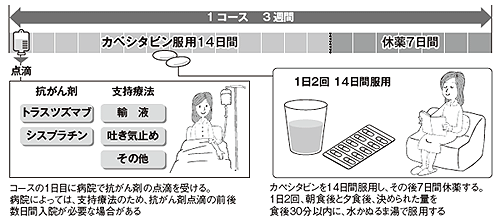
QOLを維持しながら治療を続けるために
ハーセプチンを用いた3剤併用療法の場合、どのような副作用に気をつければいいのでしょうか。
「副作用としては、ゼローダによる赤血球や白血球、血小板減少といった血液毒性がみられます。またゼローダという薬は、大腸がんにも使われますが、大腸がんで問題になっている、手や足がヒリヒリ・チクチクする、赤くはれるといった手足症候群はあまり見られません。大腸がんで使う量よりも、少ないためだと考えられます」
他にもシスプラチンによる悪心、嘔吐なども注意が必要ですが、最近では複数の制吐剤などにより、副作用対策はしっかりできており、薬の投与量を減らすようなことはあまりないようです。また、ハーセプチンに関しても、吐き気などはあまり起こらず、患者さんは、あまり無理せず治療を受けることができるそうです。
進行・再発胃がんの場合、病気が治る、いわゆる” 治癒”することは難しく、治療の目標は、いかにQOLを保ったまま長く過ごせるかになっていきます。そのためにも、副作用対策をしっかり行いながら、治療を続けることが今後重要となってくるといえそうです。
ハーセプチンが効かなくなった場合
ハーセプチン治療が有効でなかった場合には、2次治療としてイリノテカン(*)(一般名)もしくはタキソール(*)のどちらかを投与します。3次治療では、2次治療で使わなかったほうの薬剤を投与します。2次、3次治療において、どの順番で投与するべきかについては、2012年6月ごろに臨床試験の結果が出る予定です。
また、乳がんの場合、ハーセプチンによる治療がうまくいかなかった場合に2次治療としてタイケルブ(*)が使われていますが、HER2陽性胃がんの場合にもタイケルブが有効ではないかと臨床試験が行われ、現在試験の結果が解析中です。
他にも、ペルツズマブ、TDM1(一般名未定)といって、HER2陽性乳がんの治療薬として開発中の薬剤も、胃がん治療薬として開発が進められる予定で、今後新たな分子標的薬の登場が期待されています。
*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン
*タキソール=一般名パクリタキセル
*タイケブル=一般名ラパチニブ
HER2以外を標的とした分子標的薬の開発も
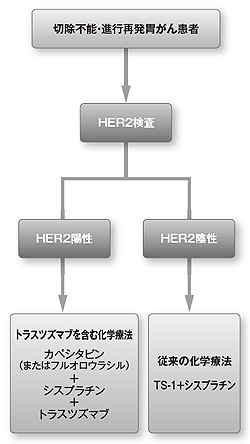
一方、HER2が陰性だった場合の治療は、従来どおり、TS-1とシスプラチンの2剤併用療法を行うことが多いです。
効果がなかった場合には、HER2陽性の場合と同様、イリノテカンかタキソールのどちらかの薬剤を2次治療、3次治療として選択します。
さらに、HER2陰性の場合でも、HER2以外のシグナルを標的にした分子標的薬の開発も進んでいるそうです。
このように、HER2陽性か陰性かが選別されたことをきっかけに、進行・再発胃がんの治療に対する薬物は多様化し、細分化、個別化する方向へ進み始めたと土井さんは説明します(図5)。
「まさに”カギが1つはずれた”という印象です。胃がんは分子の差異が多様なので、標的となる分子を1つひとつ解明していかなくてはなりませんが、それぞれを少しずつひも解いていくことで、今後治療体系がわかってくると考えています」
土井さんは期待をにじませました。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


