胃がんの診断と治療が大きく変わる 分子標的薬の登場で、胃がん治療は新たな時代へ
ハーセプチン承認で進行・再発胃がん治療に光
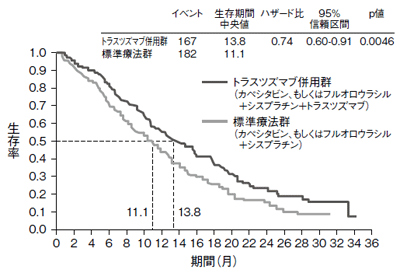
ここ最近で、進行・再発胃がんの化学療法にとっての最も明るい話題は、がん細胞が持っている特定の分子をターゲットにする分子標的薬であるハーセプチン(*)と、5-FU系のゼローダの承認です。
大津さんらも参加した国際共同臨床試験(ToGA試験)でその有効性が証明されました。約3,800人のうちHER2陽性の患者さん594人が参加したこの試験では、ゼローダ(または5-FU)+シスプラチンを3週間ごと投与する群と、ゼローダ(または5-FU)+シスプラチン+ハーセプチンを3週間ごと投与する群に分けられた比較試験において、全生存期間中央値でハーセプチン併用群が13.8カ月、標準療法のみ群が11.1カ月。一方、無増悪生存期間も、ハーセプチン併用群が6.7カ月だったのに対し、標準療法のみ群は5.5カ月と、ハーセプチンを追加投与したほうが、成績が良好という結果が出たのです。
「ハーセプチンの出現で、乳がんの治療は、明らかにHER2陽性とそれ以外というように、診断、治療が変わりました。胃がんについても同じだと思います。単に薬が1つ増えたということ以上に、胃がんの診断、治療の方向性を大きく変えることになるでしょう」(大津さん)
HER2陽性の患者は、胃がん全体の15~20パーセント弱ですが、該当者は初回治療でハーセプチンを含む前述の3剤併用治療を受けられます。
今後はTS-1とシスプラチンとハーセプチンの3剤併用を評価する試験も始まる予定です。
*ハーセプチン=一般名トラスツズマブ
進行・再発胃がんに対する新薬開発が続々と進む
進行・再発胃がんの治療においては、同じくHER2を標的とする分子標的薬タイケルブ(*)も臨床試験が進み、その有効性が期待されています。タイケルブは乳がんの治療で、ハーセプチンが効かなくなった人に対する2次治療として投与されている薬です。
他にもHER2を標的にする分子標的薬が3~4種類ほど開発されそうだということです。
腎細胞がんに有効なアフィニトール(*)という薬は、臨床試験において、1つ以上の前治療がうまくいかなかった進行胃がんへの有効性が認められ、現在、日本が中心となって、承認される前の最終段階の臨床試験である第3相試験を欧米を含��国際共同で実施中です。今年中には最終解析がなされるようです。
大腸がんの治療において有効性の高い血管新生阻害剤であるアバスチン(*)は、無増悪生存率や奏効率では有効性が認められたものの、残念ながら全体の生存率については有意な延長効果をもたらすまでには至りませんでした。
しかし、同じく血管新生阻害剤であるラムシルマブ(一般名)については、タキソールと併用の比較試験を日本とヨーロッパで開始しています。
「胃がんにおける新薬の開発は世界的に日本と韓国がリードしています。臨床試験が次々と行われていますが、そのほとんどが分子標的薬です。がん治療の究極は、治療の個別化ですが、分子標的治療の開発は間違いなくその道に先鞭をつけています」(大津さん)
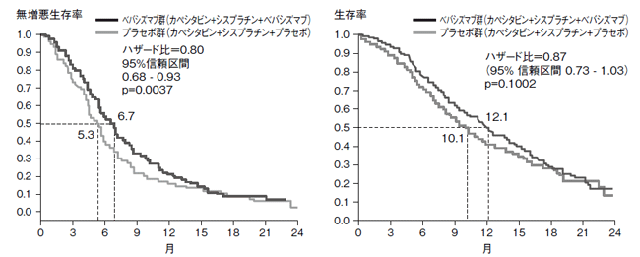
*タイケルブ=一般名ラパチニブ
*アフィニトール=一般名エベロリムス
*アバスチン=一般名ベバシズマブ
究極の個別化治療がん幹細胞へのアプローチも
さらに、今後期待できるのが、「がん幹細胞」へのアプローチです。がん幹細胞とは、がんを生じさせたり、進行させる能力を持っているとされる、大もとの細胞です。同じ細胞を作る自己複製能や、いろいろな細胞に分化できる多分化能を持っています。このがん幹細胞ががんの発生に関わっているとの仮説のもとに、それをターゲットにした薬の開発が模索されています。いくつかのがんではがん幹細胞が特定されており、胃がんについても特定されつつあるようです。
「分子標的薬がターゲットにする、がん細胞の増殖に関わる分子や、血管新生に関わる分子をたたくだけではなく、大もとの細胞をたたくことができれば究極のがん治療となります。早期がんでも採血するとがん細胞が身体中回っているといわれますが、がんが再発するかというと、手術だけで根治するケースがほとんどです。これらのがん幹細胞を標的とした有効な薬剤ができれば、将来的に補助化学療法がかなり効果的に行える可能性があります」(大津さん)
さらに進歩し続ける胃がんの化学療法
新薬、とくに分子標的薬については、患者にとって、医療費が高額になるという問題点もありますが、胃がんの化学療法のフィールドは確実に進歩していることは確かです。
「現在、ステージ2であれば、手術とTS-1で85~90パーセントぐらい治ります。ステージ3は手術のみだと30~40パーセントですが、化学療法の併用で50パーセントぐらいに引き上がってきました。ステージ4は半年前後だった生存期間が14~15カ月に延びています。今後はさらに根治率と延命期間を伸ばしていくことが課題です」
そのためには、既存の薬剤のレジメンの工夫と新薬開発の両輪が揃うことが重要だと大津さんは話します。
「現在、ハーセプチンを含めれば5種類の薬で治療のレジメンを考えられます。もちろんそれを試行錯誤して、現在のTS-1(あるいはゼローダ)とシスプラチンが標準治療となったわけですが、既存の薬をどう組み合せていけばいいかを考えることは大切です。そしてさらに治療効果を上げていくためには、そこに新薬を加えることです。今後は免疫的なアプローチによっても、治療の個別化を目指していくことになるでしょう。そのためにさまざまなアプローチで新しい治療を開発していくことが我々の使命です」
大津さんはそう結びました。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


