ピロリ菌を除菌することのメリット・デメリットは? ここまでわかった「胃がんの原因は本当にピロリ菌?」
ピロリ菌感染を高精度に調べる尿素呼気試験
ピロリ菌を除菌するためには、まずピロリ菌に感染しているかどうかを調べる必要があります。現在、その方法として普及しているのが、抗体検査です。血液や尿にピロリ菌抗体が含まれているかどうかを調べるのです。
ただし、この抗体検査の精度は決して高くはなく、感染していても抗体を検出できずに陰性だと判断されることもあるようです。
そこで、より高精度の検査が必要となります。それが尿素呼気試験です。尿素呼気試験とは、ピロリ菌が持つ尿素分解作用を利用して、ピロリ菌の有無を調べる検査です(下図)。
尿素呼気試験では、まず被験者に尿素(検査薬)を服用してもらいます。ピロリ菌にはその尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する作用がありますので、胃がピロリ菌に感染していれば尿素が分解されるため、呼気に13Cを含んだ二酸化炭素が多く検出されます。一方、ピロリ菌に感染していなければ、尿素が分解されないため、呼気に13Cを含む二酸化炭素が検出されることはありません。
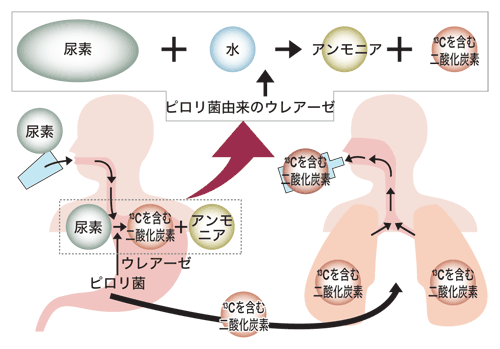
胃がピロリ菌に感染していれば尿素が分解されるため、呼気に13Cを含んだ二酸化炭素が多く検出される
「内視鏡で胃粘膜を採集し、ピロリ菌がいるかどうかを調べるのが確実なようですが、たまたま採取した粘膜にピロリ菌がいなかったら、『感染していない』と判断されてしまいます。その点、尿素呼気試験なら、ピロリ菌が感染している場所が限られていても、強力に尿素が分解されるので、より高精度にピロリ菌の感染を捉えることができるのです」
また、便の中からピロリ菌の残骸(抗原)を検出する便抗原検査も、同様に検査精度は高いと考えられています。
抗生物質の耐性菌に要注意
さて、除菌ですが、決して特殊な治療をするわけではありません。基本は、抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬剤の服用です。
現在、ピロリ菌の除菌で利用されている抗生物質には、アモキシシリン(一般名同)とクラリス錠(一般名クラリスロマイシン)の2剤が広く用いられています。また、強酸性の胃液の中では抗生物質の効き目が弱まってしまうため、胃酸を抑える薬のプロトンポンプ阻害剤〔オメプラール錠(一般名オメプラゾール)、タケプロンカプセル(一般名ランソプラゾール)など〕も同時に服用します。
ただし、この3剤併用療法による除菌の成功率は徐々に下がっているようです。
「クラリス錠は肺炎などにも多用されているために、耐性をもったピロリ菌が出現しており、除菌成功率は70~80パーセント程度と言われています。これで除菌ができなかった場合、クラリスロマイシンを、腟トリコモナス症などに用いれらる抗生物質のフラジール内服錠(一般名メトロニダゾール)に代えて、2次除菌を試みます」
それでも数パーセントの確率(1次除菌と2次除菌を合わせて)で除菌に失敗することがあるようで、日本ヘリコバクター学会では、3次除菌に用いる抗生物質に何を用いればよいかが検討されていますが、今のところ明確な方針が決まっていません。
プロバイオティクスを生活に取り入れて発がんリスクを抑える
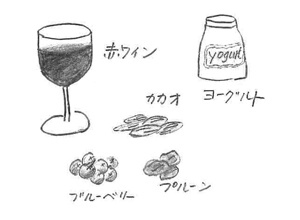
では、2次除菌に失敗したら、ピロリ菌による発がんのリスクを抱えたまま生活し続けなければならないのでしょうか。除菌できなかった場合の対処について、神谷さんはこう説明してくれました。
「ピロリ菌を完全に除菌することは望めませんが、日常生活にプロバイオティクスを取り入れることで、発がんリスクを抑えることが期待できます」
プロバイオティクスとは、主に腸管内の細菌に作用して、そのバランスを改善することで利益をもたらす生きた微生物と定義されています。
近年、腸内細菌のバランスを整える効果を謳って、乳酸菌などの生きた微生物を含むヨーグルトが販売されていますが、胃内の細菌バランスを整えるのにも有効とされる商品もあり、こうした商品を取り入れることでピロリ菌を少しでも減らすことができるというのです。
また、ポリフェノールがピロリ菌を減らすことが明らかになっているため、ポリフェノールを多く含む食品(赤ワイン、カカオ、プルーン、ブルーベリーなど)を摂ることも、ピロリ菌を抑えるのに有効です。
食道がんになる危険性は?
ピロリ菌の除菌には、強い抗生物質が用いられるため、その薬効はピロリ菌に留まらず、胃や腸にいる正常な細菌にも及ぶことになります。こうした細菌の中には消化を助けるなどのメリットをもたらすものもいるため、除菌治療が行われると下痢などの副作用があらわれることもあります。
そのため、除菌に際して、医師から下痢の薬の服用やプロバイオティクス薬剤・食品の服薬や摂取を勧められることがあります。
「プロバイオティクスに含まれる細菌には抗生物質に対する耐性があるものが多く、抗生物質と一緒に使用しても有効と考えられており、除菌に伴う下痢の対処は十分可能です。
しかし、除菌に対して慎重な医師からは、除菌によって食道がんが増えるのではないかとの指摘があります」
ピロリ菌は胃の粘膜の細胞に障害を与えるため、感染が長期に渡ると萎縮性胃炎が進行する場合があります。
こうなると胃酸の分泌が弱まり、胃液の酸性度が弱まることがあるのですが、除菌が成功すると、胃酸の分泌が活発になり、胃液が食道に逆流すると指摘されているのです。
胃では胃酸を中和する粘液が活発に分泌されているため、胃粘膜は胃酸から守られていますが、胃酸を中和する粘液のない食道に胃液が達すると、粘膜が傷つけられます。
放置すれば食道がんになることもあり、これを問題視する医師もいるのですが、神谷さんは除菌の慎重論にこう反論します。
「除菌によって食道がんになる危険性があることは否めません。しかし、その確率は非常に低いといっていいでしょう。除菌により胃酸の分泌が活発になって、食道に逆流した胃酸によって食道がんになるのは、ごくまれです。これに対して、除菌をしなければ、より多くの方が胃がんになるため、確率の違いを考慮すると、除菌をすることが推奨されます」
しかし、ピロリ菌の除菌が保険の適応になっているのは、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃がんに対する内視鏡的治療を受けた方(後者3疾患への適応は2010年6月から認められました)の場合に限られます。慢性胃炎が確認されている程度では保険が適応されず、全額自己負担となります。検査方法の違いから、除菌費用は医療機関によって異なり、2万円から2万5千円程度です(内視鏡検査をしないで尿素呼気試験を行った場合)。
一部にピロリ菌の除菌に慎重な医師もいるようですが、日本ヘリコバクター学会では、2009年から「ピロリ菌感染症認定医」制度を創設。現在、200人程度の認定医が全国で、ピロリ菌感染症の診断、そして、除菌に当たっています。日本ヘリコバクター学会のウェブサイトで、ピロリ菌感染症認定医を公開していますので(*)、ピロリ菌の除菌を希望するなら、このサイトを参考に認定医を受診するといいでしょう。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


