TS-1+シスプラチン併用療法が進行・再発胃がんの標準治療になる!? 胃がんガイドラインの書き換えを迫る日本発・抗がん剤のパワー
再発胃がんの標準治療に道
もう1つは、TS-1単独では優位性がはっきりしないのなら、TS-1とシスプラチンを併用すれば生存期間がもっとよくなるのではないか、と多施設共同研究で行われた「SPIRITS」と呼ばれる試験。
手術不能進行・再発胃がんを対象に、初回治療としてTS-1単独治療とTS-1+シスプラチン併用治療を比較したところ、無増悪生存期間はTS-1単独が4カ月だったのに対して、TS-1+シスプラチン併用が6カ月で有意に延長した。全生存期間(中央値)は、TS-1単独11カ月、TS-1+シスプラチン併用13カ月で、有意に生存期間を2カ月間延長させた。2年生存率はTS-1単独が15.3パーセントなのに対して、TS-1+シスプラチン併用は23.6パーセントだった。
一方、化学療法による副作用については、グレード(副作用の重症度)3、4の副作用は単独より併用で多く認められたが、治療に関連する死亡は両方とも認められなかった。
この試験結果の意義は、大きい。この結果を受けて日本では、進行・再発胃がんの初回治療における標準治療として、TS-1+シスプラチン併用療法が推奨されるようになった。
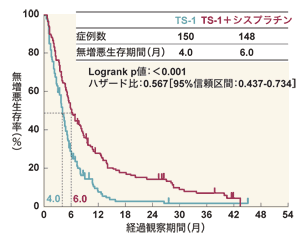
分子標的薬にも期待
もちろん、これで今後の再発胃がん治療は心配がなくなるかというとそんなことはない。
「今まで有効な薬がなかった再発胃がんが、TS-1+シスプラチンによってかなりよくなることがわかってきました。奏効率(腫瘍縮小効果)は、約70パーセントと高い数字を示しています。ところが、がんは小さくはなるけれど、生存期間はなかなか延びないのが現実です。いったんはがんが小さくなっても、ジッとしていないでまた大きくなっていく。そこで、ファーストラインはTS-1+シスプラチンでもセカンドラインではこれを超えた別の抗がん剤がないだろうか、と新たな模索が始まっています」
TS-1の次に期待されているのが、分子標的薬である。
現在、再発・転移した胃がんに対する有効性を確かめる国際的な臨床試験が行われている分子標的薬としては、すでに大腸がんで使われているアバスチン(一般名ベバシズマブ)、乳がんで使われているハーセプチン(一般名トラスツズマブ)など。ほかにも、腎細胞がんで使われているネクサバール(一般名ソラフェニブ)、スーテント(一般名スニチニ��)、乳がん治療薬のタイケルブ(一般名ラパチニブ)なども臨床試験が行われている。
今のところ1番早く日本で再発胃がんに使われる可能性があるのは、ハーセプチンである。胃がん患者のうち、HER2陽性の患者にはハーセプチンが有効と考えられている。
「推奨レジメンは、TS-1とシスプラチンですが、いいからといって全部の人に効くわけではありません。シスプラチンは腎障害があらわれやすいので、腎機能が悪い人にはTS-1単独とか、それも有効でないという場合は、カンプト/トポテシンとかタキサン系薬剤のタキソテール(一般名ドセタキセル)などが効く例もあります。タキサン系薬剤は腹膜への移行性が高く、腹膜播種に効果があるだろうと、TS-1とタキサン系薬剤併用の臨床試験も行われています。分子標的薬が使えるようになれば、さらに治療の選択肢が広がっていくでしょう」
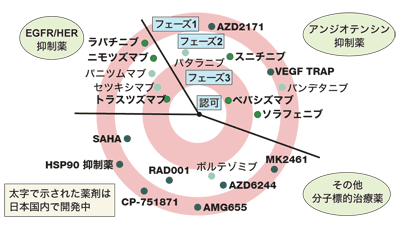
確実に増える高齢者の治療
現在、治療にあたって、今野さんが気にかかっている点は高齢者に対する薬の使い方である。
臨床試験の参加者の選択基準としては75歳未満という制限が多く、75歳以上の再発胃がんにどこまで化学療法が有効か、不明な部分が多い。しかし、高齢者人口が増える中で、高齢者の再発胃がんが増えていくのは間違いない。
「エビデンス(科学的根拠)では75歳以下を対象とした投与量ではあっても、量を減らしたり、投与間隔を変えるなど、高齢者にふさわしい治療法を工夫することが必要」と指摘する。
また、TS-1は経口剤だが、切除不能の再発胃がんの場合、幽門狭窄があると経口摂取が難しいことがある。そんな場合も、バイパス手術などと併用することで化学療法が可能になるケースがあるという。経口摂取ができるようになれば、TS-1も飲めるようになり、がんも小さくなっていくというわけだ。
あらかじめ肝転移など他臓器への転移が明らかで、外科手術では根治が難しいという場合も、術前化学療法としてTS-1+シスプラチン併用療法を行い、転移を小さくしてから手術で切除するという方法もある。この有効性も、臨床試験で検証中という。
「このようにしてオーダーメードともいえる治療法で抗がん剤を使い、予後を改善していくのが、これからの胃がん治療の流れになると思います」
再発予防の研究にも注目
ところで、再発予防の取り組みもめざましいものがある。特に、日本の胃がん治療が確実に変わることを示したのがTS-1を使った胃がん術後補助化学療法の有効性を評価するため、日本人を対象に行った多施設共同臨床試験(ACTS-GC試験)だ。
胃の3分の2以上切除に加えてD2郭清した2期または3期の胃がん(1059症例)を対象に、手術+術後補助化学療法としてTS-1投与を行った群と、手術のみの群とを比較したところ、3年生存率が手術単独群の70.1パーセントに対し、手術+TS-1投与群は80.1パーセントと生存率が有意に上昇することが証明された。従来、胃がんの術後補助化学療法では「延命効果のある治療法はない」といわれてきただけに、胃がん治療のターニングポイントとなるのは間違いない。
「アメリカなどほかの国に比べると、日本のほうが手術のレベルが高い。手術の内容も違いがあり、アメリカだとリンパ節郭清はD1郭清といって1群リンパ節しか取らないが、日本では2群までを取るD2郭清を行っているので、アメリカの臨床試験をそのまま日本に持ってくることはできません。日本に合った独自の治療法が必要であり、その有効性が今回の試験で確かめられたといえます」
こうした試験等の結果を受けて、日本胃癌学会による「胃癌治療ガイドライン」の改訂作業が進行中で、来年に改訂版が発表される予定だ。
また、胃の粘膜に棲みつくヘリコバクター・ピロリ菌を除菌すると胃がんの再発が3分の1に減るという研究結果を北海道大学の浅香正博教授らがまとめ、英国の医学誌「ザ・ランセット」(08年8月2日号)に発表、注目されているという。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


