これだけは知っておきたい!胃がんの基礎知識 抗がん剤の研究が進み、進行がん治療にも希望が!
進行がんで標準的治療となったTS-1の術後化学療法
進行がん(2期)
2期は、以下のいずれかの状態にあるものを指します。
(1)がんが漿膜に達し、胃の表面に出ているが、リンパ節には転移が見られないもの
(2)がんは粘膜・粘膜下層にとどまっているが、第2群のリンパ節まで転移があるもの
(3)がんが筋層・漿膜下層に達し、第1群のリンパ節に転移があるもの
治療は基本的に定型手術となりますが、術後補助療法としてTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)という抗がん剤を投与する化学療法に延命効果があることが確認され、今日「標準的治療」として広く行われています。
この薬は昔からある5-FUという抗がん剤の効果を高めると同時に、副作用を抑えた5-FUの改良薬ですが、胃がんの抗がん剤として承認された99年の当初から、単剤での延命効果が44・6パーセントという、高い奏効率(腫瘍縮小効果)で注目を集めました。そのうえ、経口薬なので通院治療が可能です。しかも、抗がん剤としては副作用が少ないため、休薬期間をおきながら1~2年という長期間に服用できます。TS-1に他の抗がん剤を組み合わせるなど、今後も進行胃がん治療の大きな柱になっていくことは間違いないでしょう。
進行がん(3A期)
(1)胃の表面に出たがんが、ほかの臓器まで広がっている状態だが、リンパ節転移がないもの、
(2)がんが漿膜に達して胃の表面に出てしまい、同時に、第1群のリンパ節に転移があるもの、
(3)がんは筋膜にとどまっているが、第2群のリンパ節まで転移があるもの、
のいずれかの状態をさします。
手術は定型手術、または、拡大手術というものを行うことがあります。拡大手術には、切除するリンパ節の範囲を広げる手術(拡大郭清)と、胃がんが大腸や膵臓など他の臓器に浸潤している場合、これらの臓器を一緒に切除する手術(合併切除)があります。遠くに転移のない場合は合併切除が行われますが、リンパ節の再発を予防するために、遠くのリンパ節(第3群)を切除しても手術の成績は上がらないことがわかりましたので、現在、リンパ節の拡大手術は行わないのが標準的です。
進行がん(3B期)
(1)がんが他の臓器まで広がり、第1群のリンパ節に転移がある、
(2)がんが漿膜に達して胃の表面に出ており、しかも、第2群のリンパ節まで転移がある、
という状態のがんを指します。
治療法としては、定型手術、拡大手術、抗がん剤単独治療、手術+術後補助療法としての抗がん剤治療、などが行われます。
TS-1とシスプラチンの抗がん剤治療を術前に
標準治療とはいえない段階ですが、効果が期待されているのは2期、3A期、3B期の患者さんに対する術前化学療法です。これはTS-1と、プラチナ系の抗がん剤であるシスプラチン(商品名ランダ、またはブリプラチン)の2剤併用療法を、術前補助化学療法として行う方法です。
腫瘍を小さくする効果があることは、すでにわかっていますが、延命効果があるかどうかはまだ明らかではありません。また、シスプラチンはほかの抗がん剤と比べても格段に副作用がきびしく、蓄積毒性(投与量が増えれば増えるほど毒性が強まる)もありますから、効果と副作用を慎重に秤にかける必要もあります。
とはいえ、がんを小さくしたり、リンパ節転移の数を減らすことで、胃がんを手術で「治癒」させる――というのが、この治療の目的です。進行がんでも、延命にとどまらない可能性を追求しているのです。ただし、結果が出るまでまだ時間がかかりそうなので、標準治療になるかどうかは不明、というのが現状です。
進行がん(4期)
原発病巣の状態にかかわらず、肝臓や肺、腹膜など、離れた場所に胃がんのがん細胞が飛び、腫瘍ができている状態を4期といいます。完治は望めず、予後もきびしい病期ですが、状態は人それぞれで、中には腹膜播種(腹膜にがん細胞が散らばった状態)があるけれど、通過障害もなくものが食べられ、普通に社会生活を送っている方もいます。
一方、治療法はやはり、出血や狭窄を解除する緩和手術や抗がん剤治療になります。
以上、簡単に各病期の標準治療について説明しました。くり返しになりますがガイドラインに示されたこれらの標準治療は、患者さんが自分の治療法を不安に感じている際のルートマップになるはずです。ただし、人それぞれ条件も事情も違うのですから、医師と相談し、納得のできる治療を受けていただきたいと思います。
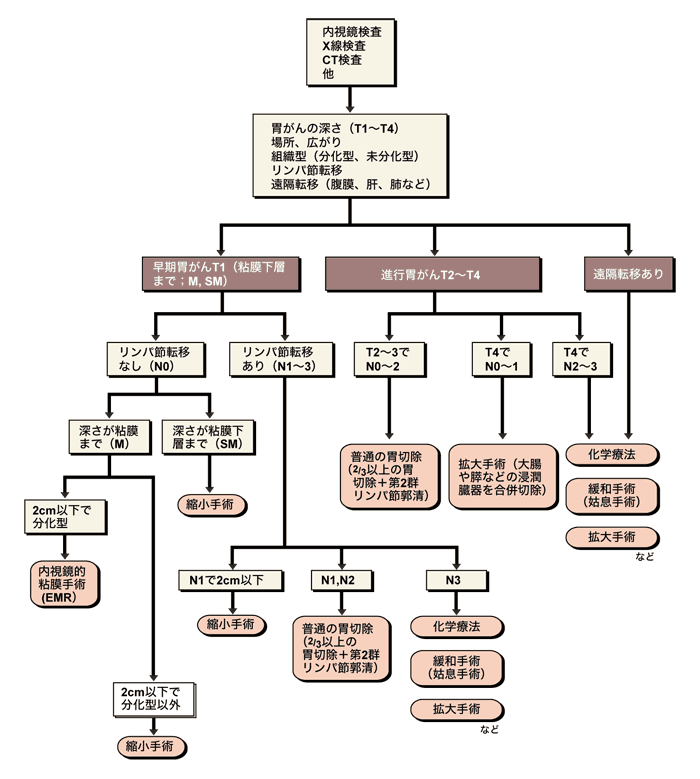
手術に伴う後遺症工夫次第で軽減できる
最後に、治療に伴う副作用や後遺症について、ふれておきます。
胃がん治療に伴う副作用は、大きくわけて2つ。手術で胃を取ることから起こる後遺症と、抗がん剤のために起こる副作用です。
手術の後遺症は、手術そのものが縮小手術になり、幽門部や迷走神経を残すようになって、ずいぶん軽減されました。が、それでも食べ物が小腸に急激に流れ込んだりして起こるダンピング症候群、胃の内容物が食道に逆流することで起こる逆流性食道炎、切除した部分の癒着などによって起こる腸閉塞など、患者さんにとって不快な症状が出ることもあります。
しかし、それぞれの症状を和らげる薬も開発されていますし、患者さん自身が食べ方や消化時の姿勢などを工夫することで、軽減できる部分もあるようです。
抗がん剤による副作用は医師と相談を
一方、抗がん剤TS-1は副作用の少ない薬ですが、それでも、色素沈着や湿疹、ドライアイなど、副作用はいろいろ起こります。また、自分では気づきませんが、白血球の減少など危険な副作用もあり、定期的な血液検査が必須です。これらの副作用に対しては医師と相談して、休薬期間の取り方を工夫するなど、副作用の少ない服用方法を見つけることが大事です。
また、最近は吐き気や食欲不振などの副作用を和らげる薬も、たくさん開発されています。積極的に使い、副作用を上手に乗り切っていただきたいと思います。
なお、再発予防に関してもうひとつお話ししておくと、早期胃がんで縮小手術を受け、胃を残せた場合、ピロリ菌の除菌を行うことをお勧めします。ピロリ菌はご存じのように、胃がんの大きな要因ですが、残った胃にピロリ菌がいる場合、除菌した人としなかった人とを比べると、除菌した人に新しく胃がんのできる確率は非常に低いのです。残念ながら保険は適用されませんが、せっかく早期治療でがんを治せた幸運を、ぜひともキープしてほしいと思います。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


