有効な治療法がなかった時代から、TS-1との併用や腹腔内投与に期待感 新しい治療法が生まれつつある腹膜転移の治療
TS-1と他の抗がん剤併用による治療
腹膜転移のがんは、ほんのわずかな細胞がこぼれただけでも再発する場合がある。目に見えないほどの大きさであるため、手術で完全に除去するのが難しいことに加え、進行した場合は、腹膜全体に広がっているため、外科手術での全摘出は難しい。
「そのため、基本的に全身投与の抗がん剤による治療が行われます。しかし、これまでの抗がん剤は全体的に効果が弱かったことと、腹膜や腹膜転移巣に薬剤が移行しにくいということがあって、あまりいい効果が得られませんでした」(田村さん)。
化学療法に代わるものとして、42度ほどの温水を腹腔に入れることでがん細胞を死滅させる「温熱療法」も行われてきた。だが、「温熱療法も、温度管理が難しく過熱による腸管の穿孔などの危険な合併症が起こったり、腹腔内の癒着などによってお湯が入り込まないところがあったりすることから、効果的に何回か繰り返して行うことが難しく、今では行っている医療機関は少なくなっています」(田村さん)
しかし、近年になって、TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)やタキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ドセタキセル)といった胃がんに有効に働く新規抗がん剤が登場したことで、腹膜転移のがんの治療も変わってきている。
それらの中でも現在、とくに注目されているのが、抗がん剤のTS-1だ。
TS-1は、従来の5-FU(一般名フルオロウラシル)よりも効果が高く、副作用が少ない抗がん剤である。また、錠剤の飲み薬のため、外来治療が可能であることもあり、現在の胃がん治療における化学療法の中心薬となっている。
さらにこのTS-1は、単独で使っても効果が高いだけでなく、他の抗がん剤と一緒に使用する、いわゆる「併用療法」でさらに高い効果を生むことがわかっており、現在、さまざまな医療機関で、他の抗がん剤と併用した臨床試験が進められている。
田村さんは、TS-1を用いた抗がん剤の併用治療に使われる薬について次のように解説する。
「併用療法で使われる抗がん剤の種類としては、シスプラチン(一般名)やカンプト(一般名イリノテカン)、タキサン系の薬剤が用いられています」
抗がん剤併用による治療により、高い治療効果を上げている医療機関が多い。
「当院でもTS-1をベースにした治療法により腹膜転移症例の成績も向上し、2002~2007年の腹膜転移を伴う初回治療がん51例では1年生��率は約51パーセント、3年生存率は約18パーセント、5年生存率も約6パーセントという結果です」と田村さんは言う。
また、TS-1が効かなかった症例では、これまで長年に渡って消化器系のがんに使用されてきた注射用抗がん剤5-FUと、同じく胃がんや乳がんの治療に60年以上も使用されてきたメソトレキセート(一般名メトトレキサート)」を併用して使用し、効果を上げている症例も報告されている。
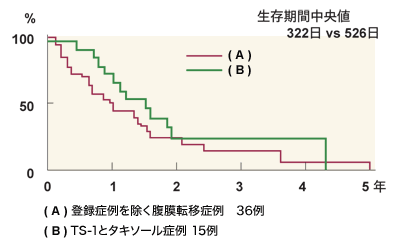
腹腔内化学療法に良好な結果が
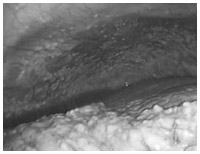
治療前
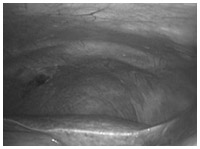
治療後
一方、胃がんの中でも進行が進んだステージ4にあたる、主に切除不能と診断された患者に対しては、抗がん剤を腹腔内投与する治療法(腹腔内化学療法)の臨床試験が進められている。「腹腔内化学療法は、腹腔内に直接抗がん剤を投薬する療法で、直接がん細胞に抗がん剤が届くようにと考え出されたものです」と田村さんは説明する。
この言葉にあるように、腹腔内化学療法の利点は、全身投与法では達成不可能な非常に高濃度の抗がん剤であっても、腹膜播種の存在する局所に投与できる点にある。さらに、薬の種類によるが、腹腔内に投与した抗がん剤で長時間局所に残るものもあることから、抗腫瘍効果を増強するとも考えられている。
腹腔内化学療法は、大阪大学をはじめ、金沢大学や福井大学など多くの医療機関で臨床試験が行われており、良好な成績が報告されているが、中でも注目を集めているものに、福井大学などで進められているタキサン系抗がん剤の腹腔内投与がある。
このタキサン系薬剤は腹腔内投与後1週間たっても高濃度のまま腹腔内に留まるため、腹腔内化学療法に非常に適しているといわれている。主に後腹膜のリンパ管に吸収されるタキサン系抗がん剤は後腹膜再発、さらに、後腹膜再発による水腎症や合併しやすいスキルス胃がんに対しても再発を予防する可能性があることが報告されている。
「ただし、まだ、それぞれ単一施設での成績ですから、現段階では標準的な治療とはなり得ていません。しかし、十分に検証する価値がある治療法だと思います。当院でも過去に5例ほど治験を行いました」と田村さんは説明する。
関西ろうさい病院では、腹膜移転のがんがステージ4にまで進んだ患者に協力してもらい、腹腔内への化学療法の投与を行い、それぞれに延命効果が現れただけでなく、そのうち1人は治療から5年目になる現在も存命しているという。
ただし、腹腔内への化学療法を行う場合、腹腔内投与された抗がん剤は腫瘍の表面からしか浸透しないため、あたかもタマネギの皮を1枚1枚はぎとるように繰り返し投与させる必要がある。そのため、腹腔内へ反復投与できるように腹腔内リザーバーを皮下へ埋め込む必要がある。
とは言うものの、「全身に対する副作用が比較的少ない治療ですし、外来通院で実施可能ということもあって、患者さんのQOL(生活の質)の維持にも貢献します。また、タキサン系薬剤は、従来の抗がん剤の腹腔内投与で懸念された腹膜癒着はほとんど起こさないという利点もあります」(田村さん)
これから期待される治療法
前述のように、これまでの抗がん剤併用は、TS-1に加えて、シスプラチンなど、あと1種類の抗がん剤の併用が基本だった。しかし、その2つに、さらにタキソールを加えた治療も行われようとしている。「TS-1+シスプラチン+タキソールを使った治療が臨床試験中ですが、効果が期待される治療法の1つと思われます」と田村さんは言う。
さらに、先に“腹膜転移には、抗がん剤の全身投与を行っても効果があまり出ない”と書いたが、TS-1を用いた通常の化学療法であっても、腹膜をダイレクトに通過し、しかも腹腔内の胃がん細胞に高濃度に取り込まれることが明らかになったという報告もされている。
現在、手術では切除できない腹膜播種を伴う胃がん患者に対して注射剤の5-FUや5-FUとメソトレキセートさらにタキソールの少量分割投与法などの臨床試験が終了しており、その結果が待たれる。
ただし、腹膜転移の臨床試験には難しい面もある。「肺がんなどの治験に比べて、腹膜播種の場合は、何が効いて、何が効果的だったかがはっきりわかりにくいため、治療効果の評価が難しい面があります。そのため、標準治療法が確立されるまでは、まだ時間はかかると思います」と田村さんは説明する。
この言葉にあるように、新しい治療法は、実際に標準治療になるまでは、安全性も含めた副作用など多くの検証が必要だが、各医療機関で手応えがありそうなことから、これまで確立されていなかった腹腔転移のがんに対する新たな治療の道筋を生み出すものとして、それらの研究結果への期待はふくらむ。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


