「化学放射線治療」は、胃がんにも有効だった! 手術不能の転移がんでも完全消失10%、生存期間18カ月、副作用も穏やか
懸念の化学放射線治療による副作用は?
このように慶応大学病院の重度の胃がん患者を対象にした新たな試みは着々と成果を収めている。しかし患者にとってみれば、化学放射線治療というと、やはり気になるのが副作用という問題だ。慶応大学病院では、前述のように穏やかな治療プランが設定されている。しかし、それでもやはり一抹の不安は残るのも事実だろう。もっとも才川さんは胃がん患者を対象にした化学放射線治療で、これまで副作用が問題になったことはほとんどないという。
「ひと昔、ふた昔前には、放射線照射の精度が低く、患部以外に照射された放射線の影響が問題になったこともありました。しかし現在では照射精度の向上に加え、画像診断技術も飛躍的に進歩しており、誤照射の不安はまったくありません。当大学放射線科の久保敦司教授・茂松直之講師の高度な技術によるところが大きいと思います」
では抗がん剤による影響はどうだろうか。投与量が抑えられているとはいえ、やはり抗がん剤による副作用が生じることが少なくない。とくに多くの人に現れやすいのがシスプラチンによる影響だ。
「薬がよく効く人は治療の早期から吐き気などの症状が現れることが少なくありません。またそうでなくても、治療の後半では同じ症状を訴える人が増えてくる。またシスプラチンの影響で骨髄抑制が起こり、白血球や血小板が大幅に減少することもある。しかしこれらは一時的な現象に過ぎません。治療が終わると、必ずまた自然に改善していきます。また、現在のところは吐き気などの症状も、それほど深刻なケースは出ていません」
と才川さんは語る。
化学放射線治療というと、どうしても副作用の不安が頭をよぎる。しかし、穏やかな慶応大学病院の治療では、副作用も軽微に抑えられているようである。
噴門部の胃がんにはとくに高い効果が
この慶応病院と同じように北里大学東病院消化器内科でも進行胃がん患者を対象に、化学放射線治療による治療が行われている。ここではこの治療が適用される症例には大きく2つのタイプがあるという。
「ひとつは胃の入口の噴門部にがんがある場合。このタイプの胃がんは噴門が狭窄して食事がとれず栄養状態が悪化することも少なくない。またこのタイプの胃がんでは胸部や食道にがんが転移していることも多く、その場合には手術は大がかりなものになり患者さんの負担も増大します。そこで原発部の胃がんに放射線を照射するとともに抗がん剤で転移したがんを叩きます。もうひとつは胃がんが進行して、肝臓の肝門部に転移が進んでいる場合。この場合には転移部である肝門に放射線を照射します」
と語るのは消化器内科講師の小泉和三郎さんである。小泉さんは20年以上も前から胃がん治療に放射線治療を取り入れており、この分野ではパイオニア的な存在だ。
具体的な治療法としては、噴門部がんの場合には、嚥下が困難なことから抗がん剤による治療は5-FU、シスプラチン、あるいはカンプト、シスプラチンの組み合わせで点滴投与が行われる。一方、肝門部に転移がある場合は経口剤のTS-1とシスプラチンの組み合わせが基本となる。
放射線の照射線量は根治治療として行われる場合と手術を前提とする場合によって異なっている。前者では照射総量は限界値の60グレイまで、後者の場合は体力を温存するために照射総量も40グレイにとどめられる。もちろんいずれの場合も分割照射が行われ、1回の治療での照射線量は1.8グレイが基本だ。さて効果のほどはどのようなものか。
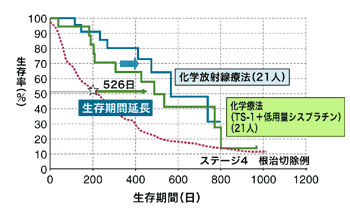
胃がんに対しても放射線は欠かせない
「まだデータをまとめていないので正確なところはわかりません。しかし、とくに噴門部がんの場合には、この治療は高い効果があることを実感しています」
と小泉さんは指摘する。
もっとも肝門部にがんが転移している場合でも、化学放射線治療で完全寛解が実現しているケースもあるし、また、放射線照射によりQОLが向上するメリットもある。肝臓にがんが転移すると、合併症状として閉塞性黄疸が生じることも多いが、程度が軽ければ、放射線治療によって症状をうまくコントロールできる。そうなると患者はうっとうしいドレナージから開放されることになる。
「1人でも多くの患者さんのがんを完全に治したい。そのために放射線は欠かせない治療法です。もちろん胃がんの場合もその例外ではありません」
と小泉さんは語る。
――これまで医療現場では、胃がんは放射線に対する感受性が弱く、放射線治療は胃がんには無効と考えられてきた。しかし、そうした従来の「常識」を覆す試みが日本を代表する大学病院で行われ始めているわけだ。慶応大学病院の才川さんは、「近い将来にはステージ3の胃がん患者さんにも、化学放射線治療を導入する可能性がある」という。
やっかいな再発・進行胃がんの治療水準を高めるために、同じ試みがさらに広がっていけばいいのだが――。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


