最新標準治療――胃がん編 メスだけではない。内視鏡、腹腔鏡、抗がん剤で治療する時代
進行がんの拡大手術
回復に時間を要し合併症も多い
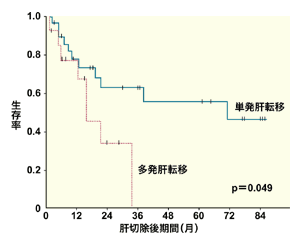
一方、この縮小手術と対照的なのが拡大手術です。
「がんが胃壁のしょう膜を破って外側に顔を出し、さらに近くの膵臓、肝臓、大腸などの臓器に食い込んでいる場合は、がんを取りきれる可能性があれば、その臓器を胃と一緒に合併切除します」(山口さん)
合併切除する臓器が複数になる膵頭十二指腸切除術や左上腹部内蔵全摘術などという拡大手術が行われることもあります。しかし、この拡大手術は、手術時間が長くなり、術後の回復にも時間がかかったり、合併症も多い傾向があり、安全性、有効性の点で海外では批判的です。
「リンパ節転移も、第2群までなら転移を取りきれる可能性がありますが、大動脈周囲にある第3群のリンパ節まで転移が進んでいると、がんはそこから胸管という太いリンパ管に入り、静脈へ流れて全身へ周っている可能性が高いのではないか。そうだとすれば、郭清するのは意味がなく、化学療法をするほうが効果的といえます。第3群までのリンパ節郭清は手術時間も相当かかるうえ、体にも相当の負担を強い、リンパ液が漏れる影響で腸の動きが悪化し回復が遅れることなどを考えれば、そんな無理をする必要はないのではないか。外国では第2群の郭清ですら危険だと疑っているのですから」(山口さん)
手術不能・再発がんの治療
TS-1の出現で変わった治療状況
では、がんが取りきれず、手術ができないほど進んだ場合は、どうすればいいのでしょうか。抗がん剤による化学療法をするのがいいと、山口さんはこう語ります。
「胃がんをめぐる抗がん剤の状況は、TS-1が出現してから随分変わりました。手術できない進行・再発がんに対して、以前の抗がん剤なら、奏効率は20~30パーセント、生存期間は半年程度でしたが、最近は、奏効率が60~70パーセント、生存期間は1年以上に伸びて、効果が飛躍的に上がり��した。何よりいいのは、経口薬で副作用も軽減されているため、入院せずに外来で治療ができることです。しかも、寝たきりにならずにすみ、食べ物も食べられることは元気の源になります」
TS-1は、正式な薬剤名をテガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル剤と言います。ちょっと舌をかみそうな長たらしい名称ですが、これは3つの成分が配合されていることから、その成分名が並べられているのです。カプセルに配合されている3種類の成分とは、(1)5-FU系の抗がん作用を持っているテガフール成分、(2)テガフールの副作用を軽減する成分、(3)テガフールの抗がん効果を高める成分です。これでわかるように、昔からある抗がん剤5-FUの効果を高め、副作用を抑えた、5-FUの改良薬がTS-1というわけです。
このTS-1が胃がんの抗がん剤として承認されたのが99年です。臨床試験で単剤での奏効率が44.6パーセントという、それまでの抗がん剤の常識を破っての出現でした。この数値は未だに破られていません。
このTS-1以後も、新しい抗がん剤が次々と出てきて、胃がんに対する抗がん剤の選択の幅も広がりました。イリノテカン(商品名カンプト、トポテシン)、タキソール(一般名パクリタキセル)、タキソテール(一般名ドセタキセル)といった薬です。当然ながらですが、選択の幅は薬の組み合わせにも広がっています。さまざまな組み合わせが考えられていますが、ただ、どの組み合わせがよく、どういう順で使うのが適切なのかは、まだわかっていません。
しかし、奏効率の高さから考えると、TS-1が軸になるのは異論がないところのようで、それを軸にした併用療法が考えられています。
その1つ、TS-1にシスプラチンの組み合わせが、小規模な臨床試験ですが、すでに70パーセントを超える奏効率を記録しています。
がんをたたいてから手術で取る
このように、最近の抗がん剤の飛躍的な効果アップは、新しい抗がん剤のパワーばかりが要因ではないようです。抗がん剤の使い方にも秘密があると、山口さんは言います。
「昔に比べて副作用を抑えるやり方を考え、その分投与量を増やし、しかも休薬期間を設ける工夫したところに効果を上げる秘密があります。これによって患者さんも使いやすくなったのです」
抗がん剤の使い方としては、この進行・再発がんに使うほかに、術後の再発予防に使う使い方と、術前に使って、がんをたたいてから手術をする使い方がありますが、実は今注目を集めているのが、後者の使い方です。これは術前補助化学療法と呼ばれています。
「この方法は、現在臨床試験段階で、有用性は証明されてはいませんが、実は、今どんどん広がっているんです。とくにTS-1とシスプラチンを併用した治療法は、TS-1は3週間飲み続けた後、2週間休み、シスプラチンは8日目に点滴するという方法です。これが1クールで、これを終わったところで手術するか、もう1クール繰り返した後で手術をするかのどちらかで、印象として7~8割の効果を上げています」(山口さん)
進行・再発がんに対する治療ではありませんが、先ほどの、術後の再発予防を目的に抗がん剤を使う使い方もあります。
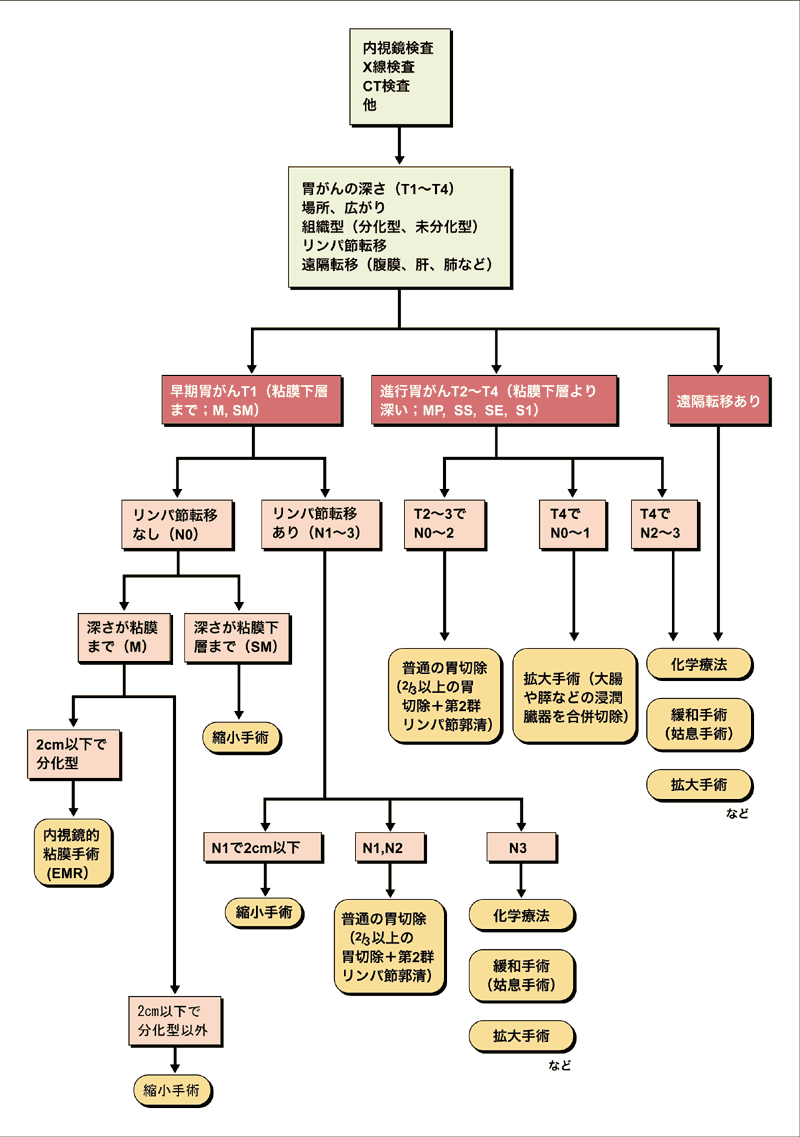
再発予防の可能性
がんの進行度が高かったり、リンパ節転移が広がっていたりすると、やはり手術で取りきれたといっても、再発が心配になります。その再発を予防できれば誰もが安心するものですが、実は、そんな方法も薬もまだ証明されたものはないと山口さんは言います。
「しかし、突破口が開かれました。TS-1よりも1世代前の5-FUの改良薬のUFTを術後に服用した臨床試験があり、解析したところ、若干効果があったとASCO(米国臨床腫瘍学会)で発表されたのです。残念ながらこの臨床試験は、途中からTS-1が出たため、最後まで完遂できなくなり、だからその途中までの解析でしかないのですが、それでも結果が出たことは、TS-1に寄せる期待も膨らんできます」
どうやら、今後の胃がんをめぐる抗がん剤治療も、TS-1を中心に展開されていくことは間違いなさそうです。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


