高度な技術力が必要。手術の場合、症例数の多い外科医を選べ! 痛みが少なく、回復も早い腹腔鏡手術の現在
開腹手術と同等の治療成績
手術中の出血が少ないのも特徴で、開腹手術だと300~400㏄の出血を覚悟しなければいけないが、腹腔鏡だと少ない人では出血ゼロから20㏄ぐらい、多い人でも100㏄ほどで、平均では80㏄にすぎない。
一方、腹腔鏡手術は開腹手術に比べて手術時間が長い点があげられているが、現在ではかなり短くなって、開腹手術が3時間半~4時間ぐらいなのに対して、腹腔鏡手術は4時間ぐらいと、ほとんど同じになってきた。
「治療成績も開腹手術と遜色ない」と小嶋さん。
厚生労働省からの助成金を得て行われた「がんにおける体腔鏡手術の適応拡大に関する研究」(主任研究者・北野正剛大分大学医学部教授)によると、腹腔鏡手術を行った早期胃がん1,622例のうち、再発はわずか6例で、全体の5年生存率は99.4パーセント。また、組織学的病期別5年生存率では、1A期が99.6パーセント、1B期が100パーセントで、開腹手術と同等の良好な成績を示したという。
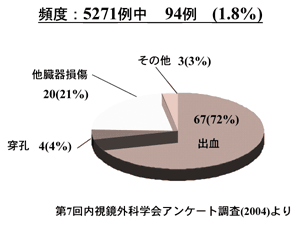
[術後の合併症]
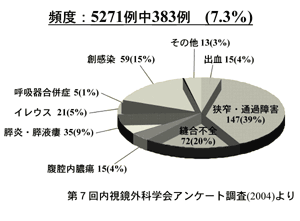
同研究では術中に起こった偶発症や術後の合併症についても検討していて、術中偶発症は全体の2パーセント(33例)に生じ、うち14例が開腹手術に移行したという。術中偶発症の内訳は出血(61パーセント)、他臓器損傷(15パーセント)、機器トラブル(12パーセント)など。術後後遺症は12パーセント(180例)に生じていて、内訳は吻合部の狭窄・通過障害(25パーセント)、腸腔内膿瘍(17パーセント)、縫合不全(16パーセント)、創感染(12パーセント)など。従来の開腹手術の際の術中偶発症や術後合併症の発生率と差はなかった。
さらに進行胃がんに対する腹腔鏡手術の結果でも、272例のうち再発は14例で、全体の無再発5年生存率は91.0パーセント。組織学的病期別では、1B期が98.7パーセント、2期が91.2パーセント、3A期が58.0パーセントで、やはり開腹手術と同等の良好な成績だった。
術中偶発症は33パーセント(7例)に生じていて、うち3例が開腹手術に移行したが、出血がもっとも多く71パーセント。また、術後合併症は12パーセント(32例)で、内訳は縫合不全(21パーセント)、創感染(16パーセント)など。
これも開腹手術の術中偶発症や術後合併症の発生率と差はなく、同等の安全性を有している、としている(平成16年度の研究報告による)。
開腹手術と同等の成績で根治性があり、合併症の発生も少ない。それでいて、患者の体への負担は著しく軽いというのであれば、むしろ、開腹手術より優れているといえるかもしれない。
| 深達度 | リンパ節 | 肝 | 腹膜 | 5年生存率 |
|---|---|---|---|---|
| 粘膜(m) | 3.3% | 0% | 0% | 93.3% |
| 粘膜下層(sm) | 17.6% | 0.1% | 0% | 88.9% |
| 筋層(mp) | 46.7% | 1.1% | 0.5% | 81.3% |
| しょう膜下層(ss) | 63.6% | 3.4% | 2.2% | 65.8% |
| しょう膜外(se) | 79.9% | 6.3% | 17.8% | 35.5% |
| 近くの臓器に浸潤(si) | 89.7% | 15.5% | 41.6% | 10.1% |
デメリットは唯一、難しさ
| 腹腔鏡下手術の利点 |
|---|
| 1. 術後の腸の動きが早く早期に食事が摂れる 2. そのため入院日数が短い 3. 痛みが少ないため翌日から歩行可能である 4. そのため肺炎などの合併症が少ない 5. 手術中の出血量が少ない 6. 術後の腸閉塞の発生頻度が少ない |
| 腹腔鏡下手術の欠点 |
| 1. 開腹手術に比べて手術時間が1~2時間ほど長い 2. 施行可能な施設が限られている |
では、腹腔鏡手術のデメリットは何かというと、手術そのものより、技術的な難しさと、設備や道具などにコストがかかるということだ、と小嶋さん。
「開腹するのと比べると視野が限られているため、ほかの臓器を損傷する可能性があり、思わぬ出血のときに対処しづらいという問題もあります。このような場合、危険が伴うので従来の開腹手術に移行するなどの対応が必要になってきます。しかし、これらの問題点は術者の技術でクリアできることであり、患者さんにとってのデメリットは何もないといっていい。しっかりとトレーニングを受けた人が無理をせずにやれば、普通に、安全にできる手術です」
道具も重要だが、必要な道具を揃え、基本どおりのやり方さえしていれば、まず問題はない。それなのに、使い古しを使うとか、細かい血管を剥離するためにはそれに合った道具が必要なのに、いい加減なもので剥離しようとするとか、尖った鉗子で傷つきやすい臓器をつかんだりと、基本からはずれた、誤った道具の使い方をしてトラブルに至るケースが少なくない、と小嶋さんは指摘する。
技術の未熟さが招いたと思われる事故で記憶に新しいのは、02年11月に起きた「慈恵医大青戸病院事件」だろう。前立腺がんの腹腔鏡手術を受けた男性が翌月に死亡。この手術の経験がほとんどない医師のミスによる事故だとして、同病院泌尿器科の医師3人が逮捕・起訴され、現在、裁判が行われている。
小嶋さんは次のように語る。
「経験の乏しい医師が、いきなりガイドラインと同じ適応で手術をやろうとしたら、合併症も多くなります。はじめは適応を絞り、間違いなくできると確認した上で、少しずつ適応を広げて行くべきです」
こう話す小嶋さんも、最初は粘膜がん、ないしは、粘膜下層まで進んだがんでもSM1がんに絞って手術を行っていたという。噴門側胃切除とか胃全摘をやるようになったのはずっとあとのこと。胃全摘にしても、昨年の秋までは早期がんしかやっていなくて、進行がんの胃全摘はそれ以降という。ガイドラインで認知されたすべての胃がん領域まで適応を広げるのに、6年以上かかったという。
「それだけ時間がかかったのは、うちの大学が慎重すぎるくらい慎重だからで、ほかのところがどんどんやりはじめても、すぐに広げることはせず、自分のところで間違いなくできると確認できるまで、慎重にやってきました。ただ、教育は熱心で、かなり早くから取り組んできましたよ」
このように話す小嶋さんによると、患者が腹腔鏡手術を選択しようとするとき、目安となるのは、何といっても腹腔鏡下の胃切除を数多く手がけているかどうか。50例以上の執刀経験があるならある程度の実力を持っていると見ていいという。100例以上ならスペシャリストといえるが、そこまでやっている人は全国でも数えるほどしかいない。また、胃がんの腹腔鏡手術は20例ぐらいでも、大腸がんの腹腔鏡手術なら100例以上やっているという人なら、それなりの信頼がおけるという。
なお、小嶋さんは腹腔鏡手術を行っている医師らと「関東腹腔鏡下胃切除研究会」を組織していて、研究会や講演会などを積極的に開いている。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


