新しい抗がん剤TS-1やタキソールの出現で生存率も上昇 ここまで進んでいる進行・再発胃がんの化学療法
TS-1を中心に動く胃がん治療
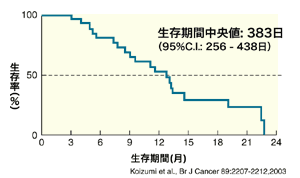
じっさいの効果はどんなものだろう。
同じ年に実施された101人の患者を対象にしたフェーズ2の臨床試験での奏効率は経口薬単剤としては画期的な44パーセントに達し、生存率も8.1カ月を記録している。そして、さらに同じ年に小泉さんらが行ったTS-1とシスプラチンの併用療法による臨床試験では、対象患者が少ないものの74パーセントもの奏効率を記録し、生存率は約383日と1年を上回っているのである。こうした効果の高さからこの薬剤が日本の胃がん治療の主役に抜擢されていったわけだ。
もちろん日本でも他の抗がん剤の臨床試験も行われ続けている。しかし、TS-1はすでに日本の胃がんの化学療法の現場にしっかりと根を下ろしている。小泉さんも強い口調でこう語る。
「アンケート調査では胃がん治療を手がけている医師の8割がTS-1を治療に用いていると回答しており、私たちのデータでは2年生存率も16パーセントに達しています。現段階ではまだTS-1による治療がエビデンス(根拠)にともなった標準治療として確立されているとはいえないし、まだ5-FUとの効果を比較するための大規模な臨床試験が行われている段階です。しかし日本の胃がんの化学療法がTS-1を中心に動いていくであろうことは間違いないでしょう。私たちも何とかこの薬剤を中心に日本で世界標準治療を確立したいと願っています」
さらに、このTS-1の新たな可能性を探るために現在もこの薬剤を単独で用いた場合とシスプラチン、イリノテカン、タキソテールをそれぞれ加えた併用療法の比較試験も進行中だ。いずれにせよTS-1がこれからの胃がんの化学療法の中核となることは間違いない。その具体的な手法について模索が行われているのが日本の胃がんの化学療法の最前線の状況といえそうだ。
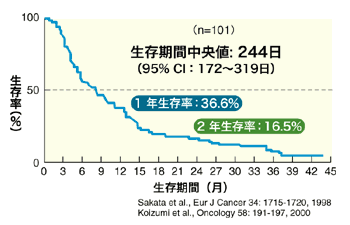
地域によって異なる治療の方向性
もっとも世界の胃がんの化学療法の方向性は日本のそれとは、微妙にニュアンスを異にして���る。
「ヨーロッパでは5-FU、シスプラチンに、さらにファルモルビシン(一般名エピルビシン)を加えたECFという治療法がすでに臨床試験によって効果を確認され、スタンダードな治療法として定着しつつあります。一方、アメリカでは同じ5-FU、シスプラチンの組み合わせに、さらにタキソテールを加えたTCFという治療法がFDA(米国食品医薬品局)の承認を得ています。さらにイギリスや韓国では、TS-1に換えて、やはり日本で開発されたゼローダ(一般名カペシタビン)という5-FU系でフルツロンを進化させた抗がん剤を主力に採用する動きもある。地域によって治療の方向性はまったく違っているのが実情です」
と、小泉さんは指摘する。
とはいえ海外でもTS-1に対する注目が高まっているのも事実だ。
「たとえば世界有数のがん治療機関、アメリカのMDアンダーソンがんセンターのアジャーニ博士らはTS-1の効果を検証するために北米、南米、ヨーロッパ、ロシアさらにアフリカまでを含めた世界26カ国、180施設での大規模な臨床試験を継続しています。この試験は5-FUとシスプラチン、TS-1とシスプラチンの併用療法の効果を比較するもので、2年後には結果が報告されることになっています。また中国でも同じようにTS-1とシスプラチンの効果を確認するための臨床試験が行われています」
このように世界の胃がんを対象にした化学療法の状況はかなり混沌としている。世界標準治療が確立するにはまだ少し時間がかかりそうである。
しかし、そんななかでも、さらに将来を見据えた取り組みにも着手されているという。最近になって多くの医療機関や研究者によって、新たな化学療法の切り札と期待される分子標的薬の導入が考えられているのだ。
「現在、同じ消化器がんである大腸がん治療の適応を取得するために、アバスチン(一般名ベバシズマブ)、アービタックス(一般名セツキシマブ)という2種類の分子標的薬の臨床試験が行われています。これらの薬剤の適応が認められれば、胃がん治療でもすぐに同じ動きが起こるでしょうね。私個人としても、胃がん治療の最強のレジメン(組み合わせ)を完成させるためには分子標的薬の導入が不可欠だと思います。たとえばTS-1、シスプラチン、アバスチンといった組み合わせのように、3剤併用という形が、将来的にはスタンダードになっていくのではないでしょうか」
と、小泉さんは胃がんの化学療法の今後を展望する。
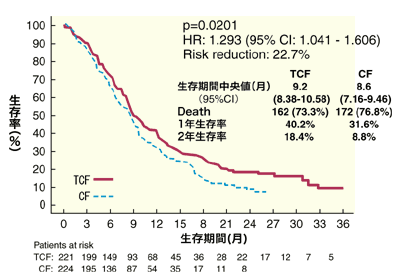
[世界各国の進行胃がんのファーストライン治療]
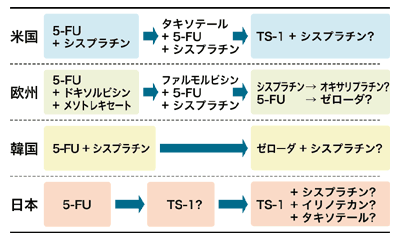
副作用が重ならない組み合わせ
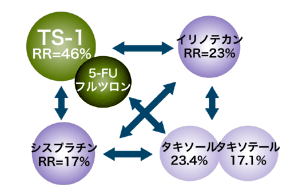
このように手術不能の進行・再発胃がんを対象にした化学療法は大きく様変わりを続けている。では、患者はそうした変化とどう向き合えばいいのだろうか。日本ではこれからの胃がん化学療法のスタンダードとして、TS-1とシスプラチンの併用療法が期待を集めているが、副作用など薬剤の併用によるマイナス要因はないのだろうか。
「当たり前のことですが抗がん剤の使用には副作用がともないます。もっとも現在では副作用についてもデータが蓄積されており、治療継続を困難にする要因となる副作用も把握が可能になっています。そこで薬剤を組み合わせる場合には副作用が重ならないように配慮しています」
と、小泉さんはいう。
たとえばTS-1のような5-FU系の薬剤では、消化器毒性や骨髄抑制による白血球減小が最大のネックになるが、シスプラチンの使用で問題になるのは腎毒性や神経毒性で、骨髄抑制はほとんどない。見方を換えれば、このように副作用が分散しているからこそ、これらの薬剤の併用も可能になっているわけだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


