手術困難な高齢者の早期胃がんにも適用できる レーザーと内視鏡の併用療法「EMR-PDT」
“限界”を改善した新治療法
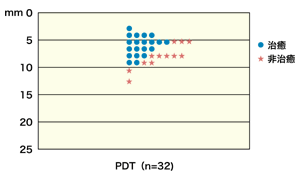
[EMRの手順(ストリップ・バイオプシー法)]
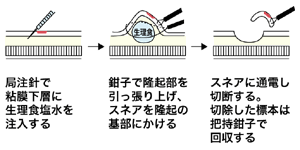
[がん病巣の厚さと治療効果]
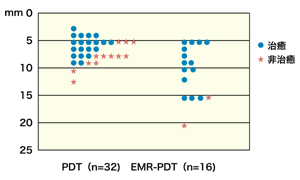
[生存率曲線]
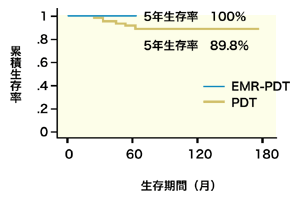
本来、PDTの真価が発揮されるのは、手術が必要な粘膜下層のがん(SMがん)に対してだ。
ところが、前述のように、肝心なSMがんの治癒率は、「70パーセント」にとどまった。この成績を何とか上げたいと、東野さんたちは考えた。
なぜなら、手術を行った場合、MがんとSMがんを合わせた「粘膜のがん」の5年生存率は、91.6パーセントにまで達しているからだ(同センターの1985~1994年の治療成績)。
「70パーセント」をさらに上げるため、スタッフたちは患者1人ひとりのがんについて詳しく分析した。その結果、SMがんに関して、「治るもの」と「治らないもの」の違いがわかってきた、という。
「治らないもの」は、大きな隆起のあるがんの場合で、深い部分にレーザー光線が届いていなかった。レーザー光線はふつうがんの表面から10ミリの深さまで届くが、がんの形状によっては、5ミリの深さでも届いていないものがあった。
そこで、まず内視鏡でがんの隆起した部分を大きく取り除き、病巣をできるだけ薄くしてから、レーザー光線を照射するアイデアが生まれた。
内視鏡の治療では、最初にがんのできている粘膜の下に生理食塩水���注入する(粘膜がんの場合)。すると、粘膜が押し上げられる。鉗子でその隆起部をひっぱり上げておいて、輪状のワイヤーで締めつける。通電によって、がんが焼き切られる。
「このEMRの代わりに、ITナイフを使った切開・剥離法(ESD)でもいいんですが、EMRのほうが短時間ででき、出血や穿孔の危険性も低い。どっちみち後でレーザー光線による治療を加えるので、大まかに、早く取れるほうがいいわけです」
同センターがSMがんの人48人に行った治療では、PDT単独(32人)よりも、EMRを組み合わせた場合(16人)のほうが、より効果的に治療できることがわかった。PDT単独ではがんの厚みが5ミリでも治癒しないケースがあるのに対し、EMR-PDTでは厚さ12ミリまでのがんはすべて治癒した。
さらに、最高で15ミリ厚のがんも、4例中3例が治癒していた。
まだ数は少ないものの、53人を対象にした5年生存率では、PDT単独が89.8パーセントだったのに対して、EMR-PDTでは、Mがん、SMがんともに100パーセントという結果が出ている(観察期間の中央値は3年6カ月)。
この数字は、「手術ができない」と、治療をしなかった場合の5年生存率63パーセントに大差をつけている(このデータは津熊秀明氏らによる、「Gut」2000;47;618-621より)。
ただし、もともと手術できない持病をかかえている人が対象になるので、“5年生存率が100パーセント”といっても、心臓疾患で3人が亡くなっている。
内視鏡治療の1週間後にレーザー光線を当てる
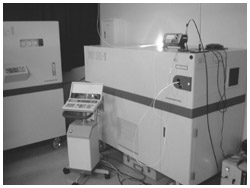
では、EMR-PDTの治療の流れを具体的にみていこう。
まず、EMR(あるいはESD)でがんを大まかに取る。SMがんの場合は、術前に他の臓器に転移がないことをCTなどの画像でチェックしておく。また、EMRで切除したがんの組織検査を行って、がんが取りきれているか、追加治療としてPDTが必要かどうかを確認する。
その数日後、PDTの準備に入る。PDTは、レーザー光線が特定の物質を含んだ細胞を破壊する性質を利用している。
がん細胞にたまりやすい性質のある、光感受性物質のフォトフリンを静脈注射で患者の体内に入れる。
その直後から、患者は日焼けを防ぐために、暗幕を張った薄暗い病室で生活する。まれに、それが引き金となって、認知症の症状が出る人もいる。
48~72時間後、フォトフリンのほとんどが、がんにだけ残っている状態になる。その状態でレーザーの治療となる。
レーザー光線(パルス波)は小さいがんで30分間、大きければ1~2時間当てる。光の反応によって、活性酸素である一重項酸素が発生し、これががん細胞を破壊する。

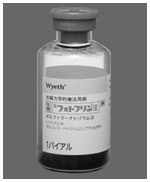
治療中、患者はじっと横たわっていなければならない。それでも、何度も内視鏡を出し入れするわけではないので、苦痛はさほど大きくはない、という。
PDTはEMRの1週間後に受ける。内視鏡でがんを取ってすぐだと出血があるからだ。血液中のヘモグロビンがじゃまをすると、レーザーが十分に届かない可能性がある。そこで、1週間おいてPDTを行う。
進行がんで6年経過した人も
レーザー光線を当てた後、約1週間は特別な個室で、光の量を徐々に増やしていく。部屋から出る場合は日焼け止めクリームを塗り、長袖を着るなど、日焼けを予防する。その後、総室(いわゆる大部屋)に移り、1~2週間様子をみる。たまに強い“やけど”のような症状が出ることがあるからだ。全部で1カ月程度かかる。
日焼けが長期間残る人もいるものの、それ以外には、フォトフリンやレーザー光線による目立った副作用はない、という。
ただ、レーザー光線を当てた後に、内視鏡で経過を詳しく見ていく必要がある。最初、患者は頻繁に検査を受けることになる。術後1週間、2週間、4週間、2カ月、といった具合だ。それが負担に感じられるかもしれない。 手術のできない局所進行胃がんにも、PDT-EMRは有効だと、東野さんは言う。
「かつてPDT単独で治療した進行がんの6人の方は、5年経たずにみなさん亡くなっています。それがEMR-PDTをした6人では、現在3人が生存されています。そのうち1人は6年を経過しています。
ただし、治療できる進行がんは、上から3層目の筋層ぐらいまでですね。それ以上深いものは、他に転移している可能性が高いんです」
内視鏡的治療にも事故は起こりうる。十分な心構えが必要だ。それでも、手術を受けられない人にとって、このEMR-PDTが“がんを根治しうる有効な治療法”であるのは、間違いない。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


