患者のHLA(ヒト白血球抗原)のタイプ別に術後補助療法を選択する 胃がんのテーラーメイド治療
免疫療法で悪くなる患者もいる
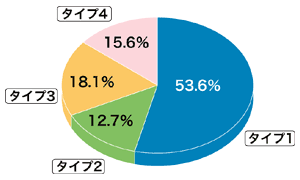
さてHLAを4つの群に分けてその分布をみると、生越さんが治療に当たった胃がん患者1926例中、タイプ1が54パーセント、タイプ2が13パーセント、タイプ3が18パーセント、タイプ4が16パーセントという割合だった(図3)。そして胃がん手術後に10年から15年の術後補助療法を行い、予後が追跡できた患者1559例について調べた。
胃がん手術後、「フッ化ピリジン剤(UFTやTS-1など)投与群」、「クレスチン投与群」、そして「フッ化ピリジン剤とクレスチンの両剤投与群」、それから「なにも服用しない群」の4群で比べた。その結果をHLAの4つのタイプごとに、それぞれの患者群の推定生存曲線を描いたのが図4である。
タイプ1の患者では、「フッ化ピリジン剤のみ」が最も成績がよかった。タイプ2は「フッ化ピリジン剤とクレスチン」、タイプ3は「フッ化ピリジン剤のみ」、タイプ4は「フッ化ピリジン剤とクレスチン」がよかった。この成績に対する生越さんの解釈は次の通りだ。
「タイプ3は化学療法が良好で、免疫療法が悪かった。これは重要な発見なんですね。薬には作用と副作用があるけれど、それが患者によって逆転して出る。日本人の場合、幸運なことに免疫療法は70パーセントの人には効いた。だから免疫療法は効くと信じられるようになったんですが、15パーセント程度の人は、免疫療法をやると逆転して早く死んでしまった。それが一番重要な発見です」
免疫療法を行うことで、かえって予後の悪くなる患者がいるのだという。そのグループがHLAを手がかりにして推測できるのであれば、重要な治療指針になる。この研究では免疫療法としてクレスチンのみで調査しているが、他の同種の薬剤でも同じような傾向が見られるのかもしれない。しかしそれは未確認である。抗がん剤がよく効くグループが10数パーセントいることも判明したという。
さらに生越さんはHLAを調べた群と調べなかった群の2群で、胃がん患者の予後の調査を行った。インフォームド・コンセントにより同意を得られた患者76人(pTNM stage 1B-4)にはHLAを測定し、4つのタイプに分類した。胃切除後、タイプ1、2、4の患者にはクレスチンとフッ化ピリジン剤を併用した免疫化学療法を行い、タイプ3にはフッ化ピリジン剤を用いた化学療法を行った。
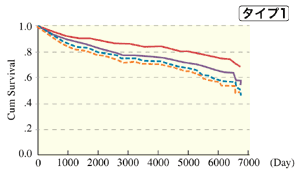
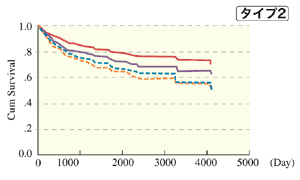
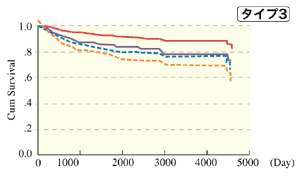
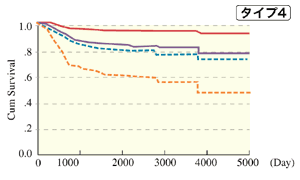
![]()
一方、HLAの測定を希望しなかった同時期の患者101人(pTNM stage 1B-4)には胃切除後、前記の免疫化学療法と化学療法を交互に施行した。その結果が図5である。生存期間に大幅な差がついた。
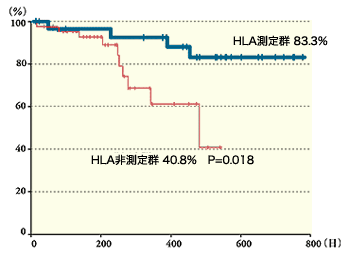
メカニズムは解明できないが
「このデータを信じますか?」と生越さんに聞かれたが、なんとも判断がつかない。この研究に対する同業専門家の評価はどうなのだろう。生越さん曰く、信用する人は少ないという。海外の有名雑誌に何度も投稿したが受け付けてもらえなかった。まず、なぜがん細胞のがん遺伝子ではなく、正常リンパ球のHLA遺伝子で調べるのかという疑問が発せられる。
「なぜがんの治療にがん細胞の遺伝子を使わないのかとよく聞かれるのですが、発想が違うんです。HLAは遺伝子の機能の分類ではなく、人の分類に利用したんです。がんが何年後かに再発したときに、この間に変わらないマーカーとして正常のリンパ球の遺伝子であるHLAを利用したわけです」
また分類方法についての疑問も呈される。なぜ数量化Ⅲ類なのかと。多種多様なHLA遺伝子の分類に最適な解析法として、著名な統計学者である林知己夫さんが開発した独創性の高い労作なのだが。
「この統計法はヨーロッパでは認められているのですが、P値(危険率)が出ないことから(もともと分類法なのでP値の概念はない)アメリカでは認められていないのです」と、生越さんは残念がる。動物実験によってメカニズムが明らかになれば信用する人が増えてくるはずだがと言う。
「ポジティブに働くリセプターを持っている人とネガティブに働くリセプターを持っている人がいて、薬が入ってくると作用が逆に出るのではないか。それはあくまでも私のスペキュレーション(仮説)です。“データは面白いんだけどね”と関心は寄せられるのですが、メカニズムが明らかにならないからなかなか信用されない。基礎的な文献が出ればみんな信用するんですが、ぼくは外科臨床医だから、こういう現象があるぞという、現象論でいいだろうと、いまはそういう気持ちです」
生越さんは1994年に最初にこの研究を発表したが、その後誰からも追試がない。
「追試が出ないと誰も認めないでしょう。私の不幸はそこです。600例集めるのに何年かかると思いますか。私はこの研究を30年もやっている。そんな気の長いことを誰もやりませんからね」と生越さんは苦笑する。
臨床応用をしながら
研究に対する評価はこのような状況だそうだが、得られた成果を生越さんは臨床で有効活用している。
「HLAを調べてテーラーメイド医療をやっています。当然そのほうが予後がいい。HLAの1個の遺伝子はそんなに重要ではないんです。全体が重要なんですね」
胃がんの手術を行った後、生越さんは病理の結果を見ならが患者さんに術後補助療法について説明する。HLAの検査をすれば、最適な先輩グループがわかり、もっともよい術後補助療法をリコメンドできると説明する。タイプ1、2、4の患者には概ねクレスチンおよびフッ化ピリジン剤を併用した免疫化学療法を推奨し、タイプ3の患者にはフッ化ピリジン剤を使用した化学療法を推奨しているそうだ。
HLAの検査に必要な血液は10CCほど。経費は生越さんの研究費から出すので患者の負担はなし。データは常にブラッシュアップして、より精度の高いものに日々補正している。この理論を生かして新しい薬をつくりたい。それが生越さんの夢だそうだ。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


