渡辺亨チームが医療サポートする:胃がん編

サポート医師・高宮有介
昭和大学病院横浜市北部病院
呼吸器センター 専任講師
たかみや ゆうすけ
1985年 昭和大学医学部卒業後同外科に入局。
1988年 英国ホスピスでがん疼痛研修後、昭和大学ペインクリニックでがん疼痛患者の治療に加わる。
1991年 「がん疼痛対策マニュアルの試作と実践」で医学博士。
1992年 昭和大学病院に緩和ケアチーム創設。
2001年 昭和大学横浜市北部病院に籍をおき、大学病院における緩和ケアの臨床、教育を追及している。
疼痛緩和の方法が多様化。緩和ケア病棟で癒される日々
| 青木良一さん(65)の経過 | |
| 2001年 10月 | 人間ドックで、3a期の胃がんを発見。T病院で胃の3分2の以上を切除、第2群リンパ節まで郭清。 |
| 2003年 3月 | 術後の定期検査で、肝臓と腹膜への転移を発見。「余命半年」と告知される。 |
| 4月 | T病院のT医師の紹介で、抗がん剤治療専門のC大学付属病院腫瘍内科に転院。抗がん剤TS-1単剤による治療を開始。著効が見られる。 |
| 2004年 5月 | 肝臓と腹膜に再々発。イリノテカン+シスプラチンのセカンドラインの治療を開始。 |
| 7月 | セカンドラインの治療は効果が見られず、緩和ケア病棟に入院。 |
| 8月 | 永眠 |
抗がん剤治療の限界が訪れたことを告げられた青木さんは、緩和ケア病棟に入る決心をする。
ここで痛みのコントロールをしてもらいながら、家族とともに最期の日々を過ごす。
充実した施設と温かなスタッフに囲まれ、青木さんは自分自身の意味を再確認し、やすらかに旅立って行った。
痛みで七転八倒しないようにお約束します

これまでの病歴が整理されているカルテ
004年6月25日、青木良一さんは、C大学病院腫瘍内科のF教授から抗がん剤治療に限界が訪れたことを告げられた。すでに腹水のためお腹が重苦しく感じられ、顔色も目の色も黄疸で黄色くなっている。「緩和ケア病棟の先生を紹介してほしい」と申し出ると、F教授はその場で同じC大学付属病院の緩和ケア科に電話をしてくれるとともに、紹介状を書いてくれたのである。
青木さんは妻の滋子さんとともにそのまま別棟にある緩和ケア科を訪れた。すでに夕方5時をま���っていて外来受付は閉まっていたが、講師のT医師は診察室で青木さんを待っていてくれたのである。
「青木さんですね。お待ちしていました。私がTです」
今年50歳になるT医師は椅子から立ち上がって柔らかい笑顔で青木さんを迎え、握手のために手を差し出した。
「よろしくお願いします」
青木さんはその手を握り返しながら、ほっとした思いだった。
「今、電子カルテを拝見していたところです。青木さんの状況はだいたいわかりました。ただし、申し訳ありませんが、現在空きベッドがありません。青木さんの症状に合わせてできるだけ早くお部屋を確保するようにしますが、当面はご自宅でお待ちいただくことになります。よろしいでしょうか?」
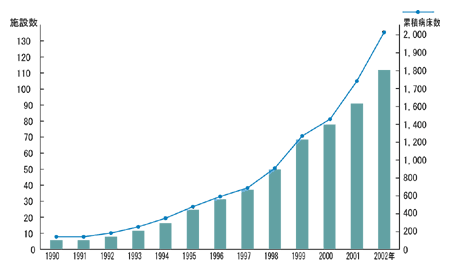
T医師の話を、青木さんはむしろ歓迎した。薬で症状のコントロールができるなら、できる限り住み慣れた我が家で過ごしたいと考えていたからだ(*1在宅での緩和ケア)。そうなれば息子夫婦や孫とも最期の時間を一緒に過ごすことができる。 「今日はお腹だけ見せていただきましょう」
T医師にうながされ、青木さんは前を開ける。T医師は腫れ上がっているお腹を、いたわるかのようにさわりながら聞いた。

鎮痛剤の種類も増えている
「今、どこがいちばんおつらいですか?」
青木さんは、「お腹が張る」「だるくてしかたがない」「食欲がない」と正直に自覚症状を話していく。
「では、リンデロンというステロイド剤をお出ししましょう。多少ラクになると思います。それから、がんだというと七転八倒する疼痛を連想されるかもしれませんが、今の時代はいろいろなお薬が登場しています(*2がんの疼痛治療)。そういった苦痛が起こらないようにお約束できるようになりましたから、ご安心ください」
そのほかT医師は栄養補給など、在宅ケアのための日常生活上の注意を丁寧に説明してくれた(*3終末期の栄養管理)。
落ち着けるすばらしい環境だ
7月4日の日曜日の午前中、青木さんは緩和ケア病棟に入院することになった。前日、C大学付属病院より、「明日入院してください」との連絡あったのだ。
右のわき腹に少し痛みが強く感じられるようになっていて、もう自宅でのケアは難しくなっていた。リンデロンのおかげか、一時はだるさも減り、食欲が出ていたが、再び身の置き所のないだるさにさいなまれるようになり、食事もあまりのどを通らなくなっている。自分の力でトイレに行くことも難しくなってきた。「もうこれ以上家族に負担をかけるわけにはいかない」と考えていたところだ。
長男夫婦が用意してくれた車に向かうとき、我が家を振り返り、「あー、もう戻って来れないかもしれないんだな」と涙が流れそうになる。そのとき、小学1年生の孫が、「僕もおじいちゃんを送っていくよ」と、一緒に車に乗り込んでくれたので、青木さんは救われた思いだった。
緩和ケア病棟にやってきてナースステーションで入院手続きをしているとき、窓から大きな公園の緑が見えた。周囲は、まるでリゾート地のようなすばらしいロケーションとなっている。
病室のなかの様子は、病院案内のパンフレットで見ていたが、実際に入るのは初めてである。とても明るく、ベッドをおいたスペースに隣り合って、家族で食事ができるようにしたテーブルを置いたスペース、3畳ほどの和室風にしつらえたスペースがあった。
「この部屋は落ち着けるなあ」
青木さんは、すばらしい環境に満足していた。そこへ、緩和ケアチームのスタッフが揃って挨拶に訪れた。T医師とともに、若い研修医や看護師、薬剤師、栄養士、ケースワーカー、ボランティアなどが次々自己紹介をし、青木さんと握手した。
入院をすると、疼痛緩和はモルヒネを中心にした薬剤に切り替わった。副作用も予防的に対応され、痛みそのものもかなり軽快した(*4モルヒネの副作用と対策)。
気持ちが癒されてきた
2004年7月15日、青木さんは妻と長男夫婦、長女夫婦、さらに3人の孫に囲まれ緩和ケア病棟のベッドに横たわっていた。病室の窓の向こうからはかすかにセミの声も聞こえ、すっかり夏がやってきたことをうかがわせる。
死が迫っていたが、青木さんはそれほど悔しいとは思ってはいない。入院以来2週間のうちにT医師や研修医のH医師、レジデントのY医師、看護師などと、いろいろ話すことができた。
「自分のことをわかってほしい」
「自分は生きる意味があったのだろうか」
「自分にはこの世に何か役割があったのだろうか」
誰かに聞いてほしかったこんな疑問に、医師や看護師はベッドサイトに腰を下ろして辛抱強く付き合ってくれた。話しをするうちに、苦しかった気持ちが癒されてきた気がする(*5苦痛の理解)。傍らでは妻の滋子さんが温かい視線を送り続けてくれた。
「がんとは可能な限り闘うことができた。平均寿命には届かなかったかもしれないが、自分は愛する家族に囲まれながら死を迎えることができる。仕事やお金やいろいろ人生で思いはあったが、家族の絆が一番大切なことに気づくことができた。十分幸せな人生だったと思う」
青木さんは、こんな気持ちになっていた。
緩和ケア病棟では、何組かのボランティアグループが立ち働いていた。あるグループは音楽療法を提供し、あるグループはアロマテラピーで患者を癒してくれ、また、鍼灸やマッサージをしてくれたり、本の読み聞かせをしてくれるグループもある。青木さんはハーモニカを聞かせてくれるという青年に病室に来てもらった。
「何かリクエストがありますか?」
こう聞かれた青木さんは、顔をほころばせる。
「昔、倍償千恵子が歌っていた『下町の太陽』を聞きたいな」
ボランティアは若いのに、昔の曲を見事に暗譜で聞かせてくれた。まだ、独身だった頃、今は妻である滋子さんとデートする度にこの歌を二人で歌っていたものである。
「よかったわね、おとうさん」
滋子さんは、青木さんの手をしっかり握り締めていた。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


