渡辺亨チームが医療サポートする:胃がん編
抗がん剤治療から緩和ケアへギアチェンジするとき
滝内比呂也さんのお話
*1 TS-1の有効性
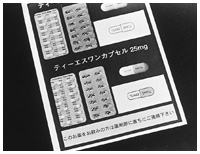
抗がん剤の使用は、2剤以上を組み合わせて抗腫瘍効果(腫瘍を小さくする効果)を高めようとする多剤併用療法が普通になっていますが、TS-1は単独で投与しても抗腫瘍効果が47パーセントと、多剤併用療法と変わらない効果を示します。しかも多剤併用療法の場合は、併用により効果を高めようとする反面、毒性も増すことになり、時には治療が継続できなくなるという問題も生じがちです。これに対してTS-1は単剤で利用できるので、QOL(生活の質)の面で期待できます。
従来の抗がん剤の多くは点滴であるのに対して、TS-1は経口剤なので、外来での治療がしやすいところも特長です。
TS-1の薬剤承認試験における生存期間中央値(臨床試験の対象となった患者の、半分の患者が死亡した日数)は244日で、これ自体は従来の薬剤と大きな違いはありません。しかし、1年生存率が37パーセント、2年生存率が17パーセントでした。これは、従来の抗がん剤に比べて優れている可能性が十分に期待できます。
*2 TS-1の副作用
TS-1の主な副作用には、骨髄の造血機能を低下させる好中球、血小板の減少の他、下痢、口内炎、食欲不振、吐き気、全身倦怠感、皮疹、皮膚の黒ずみなどがあります。5-FUの合剤で、作用を増強しようと二つの成分を入れて作っていることもあって、5-FUよりも白血球減少、好中球減少、血小板減少が強く出ることがあります。経口剤といっても、重篤な白血球減少、好中球減少ということもありえますので、慎重な対応が必要です。
渡辺亨さんのお話
*3 余命告知
患者が治療を始めてから死亡するまでの生存期間中央値というデータは、どこの医療機関にも過去のデータの蓄積としてあります。例えば胃がんが再発した場合の余命は約6カ月というように。しかし、この数字の解釈にはいろいろ問題があって、まず一つは、これはあくまでも中央値であって、実際の患者さんでは余命の長い人もいれば短い人もいる。もう一つは、これは過去のデータであって、今の治療を受けた人のデータではないのであまり参考にはならないということです。それに、患者さん個々で治療に反応する度合いが異なりますので、余命数字は一応の目安にはなるけれども、あまりそれに捕われて死までのカウントダウンのような愚かなことはしないほうがいいでしょう。
滝内比呂也さんのお話
*4 再発胃がんのセカンドラインの選択肢について
「胃がん編-2」でもご紹介しましたが、進行・再発胃がんの抗がん剤には、TS-1や5-FUという系列、タキソールやタキソテールの系列、シスプラチン、イリノテカン、マイトマイシン、メソトレキセート(一般名メトトレキサート)など、たくさんあります。ただし、現在の段階では、どの薬をどう組み合わせて用いるとより効果的かといった結論は出ていません。患者さんの病態や転移の種類、あるいは生活環境など、いろいろな条件をみながら、より適した治療法を選ぶことになります。
これらの治療法はファーストライン(第一次治療)だけでなく、セカンドライン(第二次治療)の選択肢として実際の臨床の現場で使用されることも増えてきました。今後は薬や併用療法の優劣が少しずつはっきりしてきて、ファーストラインではどういう治療法、セカンドラインではどういう治療法ということが決まっていくのではないでしょうか。
*5 免疫賦活剤
クレスチンなどの免疫賦活剤は、一時期日本ではよく使われていましたが、単独使用の承認を取り消されてからほとんど使われていません。抗がん剤と一緒に使う薬ということになっていますが、これらが抗がん剤にどう影響を及ぼすという科学的データはほとんどないのです。唯一胃がんの術後補助化学療法で、UFTという抗がん剤にクレスチンを併用することによって、UFT単独に比べて有用性があったというデータがあります。ところが、これは手術だけして補助化学療法をしない場合と比較したデータではないので、どこまで信頼性があるのかは疑問だという意見が支配的です。
高宮有介さんのお話
*6 緩和ケア、緩和ケア病棟
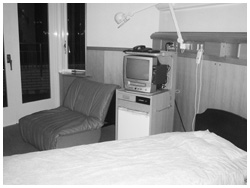
緩和ケアには、三つのキーワードがあります。
第一は全人的なケアです。痛みなどの身体症状の緩和はもちろんのこと、精神的な悩み、家庭のことや仕事のこと、経済的なことなどの社会的な悩み、生きている意味や役割の根源的な問いかけであるスピリチュアルペインの緩和をめざしています。第二にご家族も傷ついた存在として患者さん同様にサポートします。第三にこのようなケアは医師と看護師だけでは実現できません。医療ソーシャルワーカーや薬剤師、理学療法士、ボランティア、宗教家など多職種によるチームでのケアも重要です。
対象はがん患者さんであれば、がんの診断時から心のケア、苦痛の緩和という意味では緩和ケアは始まっています。一般病棟での緩和ケアの実践として、アドバイザー的な関わりの緩和ケアチームがあります。2002年に保険でも加算がつきましたが、全国的には認可を受けたチームは30施設しかありません。認可を受けずにがんばっている緩和ケアチームもありますが、全国的にはまだ不足しています。一般の臨床医への緩和ケアの教育、医学生や研修医への緩和ケアの教育が急務と感じ、私自身もそのような活動に従事しています。
緩和ケアを確実に提供する施設は緩和ケア病棟になります。施設によりホスピスと呼ぶところもあります。厚生労働省の基準により、対象は根治不能のがん患者さんになります。
2004年6月1日現在、全国で134施設です。年間30万人ががんで亡くなっていますが、緩和ケア病棟での看取りはそのうちの4~5パーセントに過ぎません。
緩和ケア病棟、ホスピスというと死に場所というイメージがあるかもしれませんが、反対にその人らしく生きることを援助する場所です。一般病棟にいても死は避けられません。よりよい生を支える場所がホスピスであり、緩和ケア病棟です。
緩和医療の定義
「治癒を目的とした治療には反応しなくなった疾患を持つ患者に対する積極的で総合的な医療ケアである。痛みのコントロール、痛み以外の諸症状のコントロール、心理的な苦痛、社会的な問題、霊的な問題の解決が最も重要な課題となる。緩和ケアの目標は患者とその家族にとって望みうる限りの最高のQOLを実現することである。このような目標を有するもので、緩和医療は末期だけでなく、もっと早い時期の患者に対しても、がんの病変に対する治療と同時に適応すべきである」(1990年WHO)
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


