渡辺亨チームが医療サポートする:胃がん編
疼痛緩和の方法が多様化 緩和ケア病棟で癒される日々
高宮有介さんのお話
*1 在宅での緩和ケア
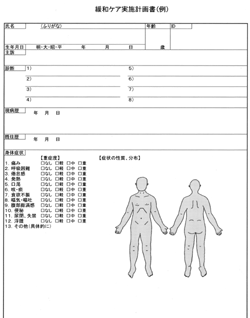
緩和ケアの先進国であるイギリスなどでは、緩和ケアの中心になっているのは在宅によるケアです。ホスピス病棟は全英に500施設ほどあるといわれていますが、自宅で家族や専門スタッフに見守られながら最期を迎える人も多くあります。
日本でも最期の時間は自宅で過ごしたいと希望する患者さんは少なくありません。現状では主に地域の訪問看護師や往診医が在宅での末期医療に対応しています。在宅へのコーディネート役として、緩和ケアチームが活動している施設も増加しています。
*2 がんの疼痛治療
がんによる身体的な苦痛はとても多様で、かつつらいものです。これに対して疼痛緩和の方法もとても進歩し、ずいぶん多様になってきました。一口に鎮痛剤といっても、経口薬のほか、坐薬、貼付薬、持続皮下注入法、持続静注入法など、多くの薬剤と投与方法があります。WHO(世界保健機関)は鎮痛薬の使い方は、痛みの強さによって、ステップ1からステップ3まで順次選択するように定めています。
| ステップ1 | 非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)±鎮痛補助剤 |
|---|---|
| ステップ2 | 軽度から中程度の強さの痛みに用いるオピオイド±非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)±鎮痛補助剤 |
| ステップ3 | 中程度から高度の強さの痛みに用いるオピオイド±非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)±鎮痛補助剤 |
ステップ1では、私は経口剤として胃腸障害の少ないハイペン(一般名エトドラク)という薬を1日400ミリグラムを2回に分けて処方しています。また、さらに疼痛緩和の効果を期待する場合は、胃腸障害の副作用はありますが、ボルタレン(一般名ジクロフェナクナトリウム)を胃薬と併用しながら使用します。
ステップ2としては、最近発売されたオキシコンチン(一般名オキシコドン)という薬を1日10ミリグラムで2回に分けて処方するケースが多くなっています。オキシコンチンは麻薬ではありますが、モルヒネではなく、患者さんの抵抗が少ないようです。
さらに次のステップ3の段階では、モルヒネを処方します。医師にいわれたようにきちんと服用すれば、今まで言われてきたようなせん妄などの精神症状や中毒症状はなく、安全に使用できます。
モル���ネの中でも一般的に使用されることが多いのは、一度服用すると長時間効果のある徐放剤というタイプの薬剤です。これも1日2回でよいMSコンチン(一般名硫酸モルヒネ徐放剤)や1日1回でよいカディアン(一般名硫酸モルヒネ徐放剤)など多くの製剤があります。また、痛みをすぐに緩和する目的で即効性のあるモルヒネ剤を必ず準備します。オプソ(一般名塩酸モルヒネ水溶液)5ミリグラムまたは10ミリグラムの使用が中心です。
*3 終末期の栄養管理
終末期の患者さんは腸閉塞などの消化管の通過障害があれば、点滴で栄養補給をする必要がありますが、最後まで少量ずつ経口で栄養を確保できる場合も少なくありません。ただ問題は、患者さんにも、ご家族にも、「食べられないとおしまいだ」という考え方があって、食欲がないのに無理に「食べなければ」「食べなさい」となることがけっこう多いことです。患者さんにはこれが苦痛になることもあります。PS(パフォーマンスステータス=活動能力)が下がれば全身の活動量も減るのですから、食べる量が減ることに、あまり神経質にならないことが大切です。
| 0 | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる。 |
| 1 | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働(軽い食事など)、座業(事務など)はできる。 |
| 2 | 歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助がいることもある。軽労働はできないが、日中の50%は起居している。 |
| 3 | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している。 |
| 4 | 身の回りのこともできず、つねに介助が必要で、終日就床を必要としている。 |
*4 モルヒネの副作用と対策
モルヒネの副作用は便秘と吐き気と眠気です。必ず現れる便秘の対策のためには、ラキソベロン(一般名ピコスルファートナトリウム)という薬が服用しやすく量の調整もしやすいことから、予防的に使用します。また、吐き気・嘔吐対策としては、ノバミン(一般名プロクロルペラジン)という薬を予防的に投与すると効果的です。眠気は慣れてくる場合が多いのですが、不快な場合は眠気止めとしてリタリン(一般名メチルフェニデート)を処方する場合もあります。
また、最近、麻薬の貼付剤もよく使用します。デュロテップパッチ(一般名フェンタニル)と呼ばれています。とくにモルヒネで吐き気や眠気、便秘などの副作用が調整できない患者さんには有用です。また、3日おきの張り替えのため、在宅の患者さんにも重宝されています。ただし、急に痛くなったときのために先ほど述べた即効性のモルヒネを準備する必要があります。
さらに、モルヒネでも効きにくい痛みの場合もあり、その場合は鎮痛補助薬を併用します。鎮痛補助薬には抗うつ薬、抗けいれん薬、ステロイド、抗不整脈薬、ケタミンなどがありますが、処方する医師にも緩和ケアの経験のある専門的な知識が必要です。
*5 苦痛の理解
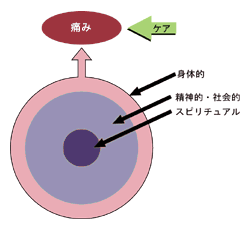
末期がんの患者さんと会話することの意味は、一般に医療者にはなかなか理解されづらいところがあります。多くの医療者は患者さんに対して病状説明はしますが、症状の訴えの裏にある患者さんの感情や気持ちを聴くにはいたっていません。
末期がんの患者さんの苦痛というのは、身体だけではなく、精神的、社会的な苦悩が小さくありません。また、スピリチュアルペインと呼ばれますが、自分の存在を認めて欲しい、また自分は生きている意味はあるのだろうか、これまでの人生に自分の役割はあったのだろうか、といったことを振り返り、誰かに傾聴してほしいのです。相手が医師であることもあれば、看護師であることもありますが、「この人は信頼できる人だ」と思える相手と話すことによって、自分自身の意味を再確認していかれます。
こうした会話は症状緩和にもなるし、患者さんの安定にもつながります。緩和ケア病棟では短期間の出会いの中で心をこめて向きあい、患者さんが「ここで過ごせてよかった。このスタッフと自分の人生の最期に出会えてよかった」と思っていただければ、緩和ケアにかかわるものとしてこれ以上の喜びはありません。緩和ケア病棟や緩和ケアチームは、身体の苦痛を緩和するだけでなく、全人的な苦悩を和らげる努力をしています。
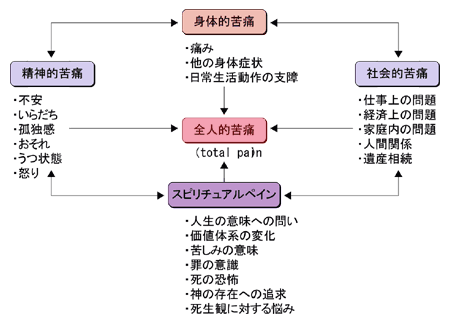
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


