進行別 がん標準治療【胃がん】 早期がんなら内視鏡、縮小手術、それ以外は定型手術が基本
1A期
内視鏡で治療できる条件
胃壁は、内側から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜下層、漿膜という5層から構成されています。このうち、がんの深さが粘膜下層までにとどまり、リンパ節転移のない状態が1A期です。胃に接したリンパ節に転移があるか、あるいは筋層までがんが食い込むと1B期になります。早期がんはほとんどがこの段階にあります。1A期は、内視鏡による手術と開腹による縮小手術、腹腔鏡による手術という方法があります。1B期は、一部をのぞいて定型手術か腹腔鏡による手術が行われます(1頁図参照)。
●内視鏡的粘膜切除術(EMR)
粘膜内にがんがとどまる1A期のがんならば、内視鏡で治療ができます。内視鏡的粘膜切除術は、口から入れた内視鏡で内側から胃がんを切除する方法です。生理食塩水などを注入して盛り上げた胃がんの病巣部にワイヤー(スネア)をかけ、高周波によって焼き切ります。体への負担が少ないだけではなく、胃もそのまま残るので、後遺症の心配もほとんどありません。
ただ、内視鏡的粘膜切除術では胃の周囲にあるリンパ節は1個ですら取ることはできません。したがって、リンパ節転移がないこと、加えて、一度にワイヤーで切除できる(一括切除)大きさであることが条件になります。こうした条件から、基本的に(1)2センチ以下の、(2)分化型の腺がんで、(3)粘膜内にとどまり、(4)潰瘍やその痕跡がないがんが適応とされています。
再発率が低い一括切除
粘膜下層まで進むと、約15パーセントにリンパ節転移がありますが、粘膜内にとどまり前の条件をクリアすれば、極めてリンパ節転移の危険は低いとされています。分化型のがんは、周囲の非がん部粘膜と似た顔つきをしており、未分化型のがんに比べるとおとなしいがんです。ただし、潰瘍ができるとその部分が繊維化したり、がんが下にもぐりこみ、内視鏡で治すことが難しくなります。
内視鏡的粘膜切除術で「一括切除できる」大きさは、��でもできる方法であるストリップバイオプシ法では通常は2センチ以下です。内視鏡的粘膜切除術では、切除した組織を顕微鏡で見て(病理検査)、周囲にがんの取り残しがないか、粘膜より下に食い込んでいないかを確認することが極めて重要です。「十分なマージン(安全域)をとって切除できていれば、局所再発はほとんど起こりません。しかし、手術前の診断は、2割ぐらいで間違っている」といいます。正確ながんの広がりや深さを把握するためには、切除後の組織の病理検査が必須なのです。そのために一括切除することが必須なわけです。
2センチを超えるがんをいくつかに分割して切除することも可能ですが、こうなると分割した境目の部分は熱変性を受け、病理診断が非常に難しくなります。
「実際に分割切除のほうが再発率が高いのです。一括切除と分割切除では安心感が全く違います」と笹子さんは語っています。
病理検査で、予想を超えてがんが広がっていた場合には、ただちに定型手術などに変更して手術が行われます。万が一の場合、遅滞なく開腹手術に移れるのも、内視鏡的粘膜切除術の大きな利点といえます。
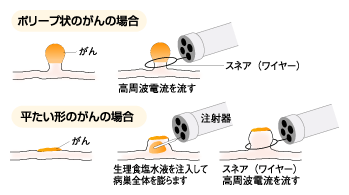
手術後遺症や合併症を防ぐ
●縮小手術
リンパ節転移の可能性は低いけれど、内視鏡的粘膜切除術の対象にはならないという場合、縮小手術が標準的です。
定型手術では、胃の3分の2以上を切除するのに対し、縮小手術では胃の切除範囲を小さくしたり、リンパ節郭清の範囲を狭くします。
具体的には、がんの病巣部を含む胃を部分的に切除したり、胃の下にある大網という脂肪組織を残す、あるいは胃の出口を残す(幽門保存胃切除術)などの方法があります。大網温存手術をすれば癒着(腸がくっつく)による障害を軽くできます。幽門保存胃切除術をすれば食べ物が小腸に急に流れ込むことや、胆汁が胃の中に逆流してくるのを防止できるようになります。リンパ節も、定型手術では第2群まで郭清しますが、縮小手術では1群、つまり胃に接したリンパ節を郭清し、これにある範囲のリンパ節郭清を加えます。郭清するリンパ節の範囲によって、縮小手術はAとBに分かれています。
縮小手術と定型手術の差
これらは、いずれも患者さんの体の負担や手術後の合併症の出現をできるだけ少なくしようという方向で考えられた方法です。しかし、笹子さんによると「ガイドラインの改定版では、診断に自信がない場合は、1ランク上の手術を行うようにと書き加えます」と語っています。1.5センチ以下のがんといっても、実際に胃を切除して調べてみるとそれ以上の大きさだったといったことは決して少なくない。それだけ、一般の医師にとって手術前の検査でがんの大きさやリンパ節転移の有無を判別するのは、難しいことなのです。
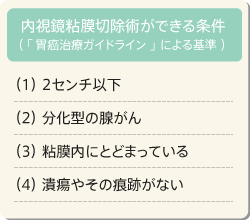
また、縮小手術Bでは*第1群のリンパ節に加えて、7、8、9番のリンパ節の郭清を行いますが、これに11番の一部を加えると第2群のリンパ節郭清になります。「こんなわずかな郭清を省いても、あまり大きなメリットは考えられません」と笹子さん。
実際には、3群に含まれる13番や14番の一部のリンパ節を郭清しないというのが、標準的な定型手術との違いです。しかし、笹子さん自身は外科医としてこう語っています。「胃の出口に近い粘膜下層のがんで、14番のリンパ節をとらないというのは不安なものです。実際には転移がある場合もない場合もありますが、安心感が違うのです。6番のリンパ節にかりに転移があったとしても、その先の14番を取っていれば安心です」。
*第1群のリンパ節=リンパ節は胃に近いほうから遠くへ行くにしたがって第1群、第2群、第3群、それ以上と分類され、部位により名称(番号)がついている
2センチを超える早期がんと内視鏡的粘膜切除術
最近では、2センチを超える大きながんでも、ITナイフなどにより一括切除できる方法が開発されています。粘膜内にとどまり、脈管侵襲(血管などに食い込んでいる)などがなければ、大きくてもリンパ節転移はないだろうという前提の下に行われている方法です。ただし、笹子さんは「過去のデータで、こういう条件ならばリンパ節転移はないだろうという予測の下に行われるもので、実際再発しないかどうかはまだ不確実です」と語っています。
病理検査といっても実際にはリンパ節の中央を切ってがんの有無を検査しています。頻度は少ないとはいえ、リンパ節の端にがんがある可能性も皆無とはいえないのです。「がんが大きくなるほどリンパ節転移の可能性も出てくるので、再発してくる人も中にはいるかもしれません」。こうした点も含めて内視鏡的粘膜切除術の予後について、日本胃癌学会でも調査を行う予定だそうです。
同じカテゴリーの最新記事
- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場
- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!
- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少
- 薬物療法が奏効して根治切除できれば長期生存が望める ステージⅣ胃がんに対するコンバージョン手術
- 胃がん新ガイドライン「条件付き承認」で増える治療選択 1次治療でオプジーボ承認
- 術後合併症を半減させたロボット支援下手術の実力 胃がん保険適用から3年 国産ロボット「hinotori」も登場
- 適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法
- 術前のスコア評価により術後合併症や全生存率の予測も可能に 進行胃がんに対するグラスゴー予後スコアが予後予測に有用
- ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん
- 新規の併用療法による治療効果改善に期待 ステージⅢ胃がんにおける術後補助化学療法の現状


